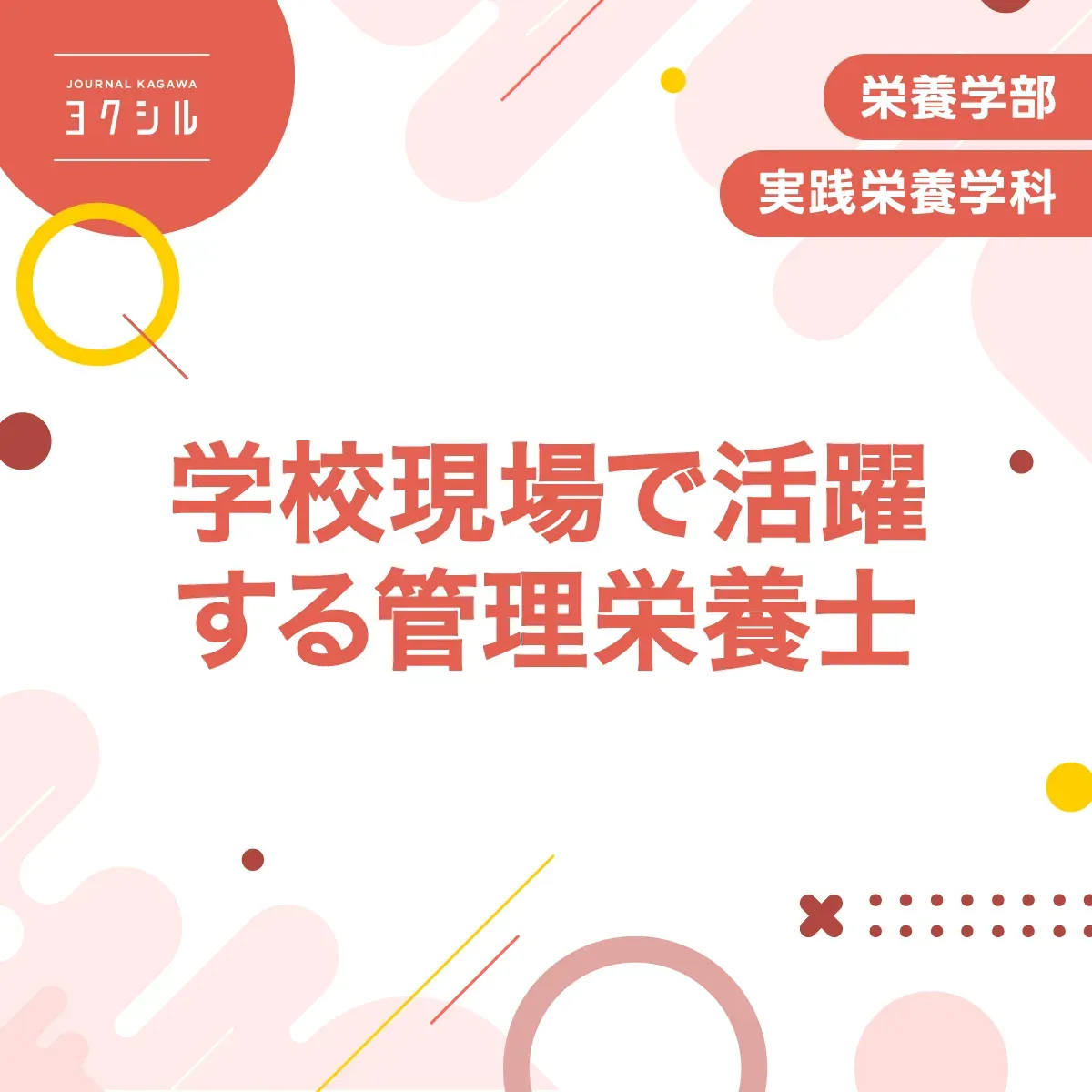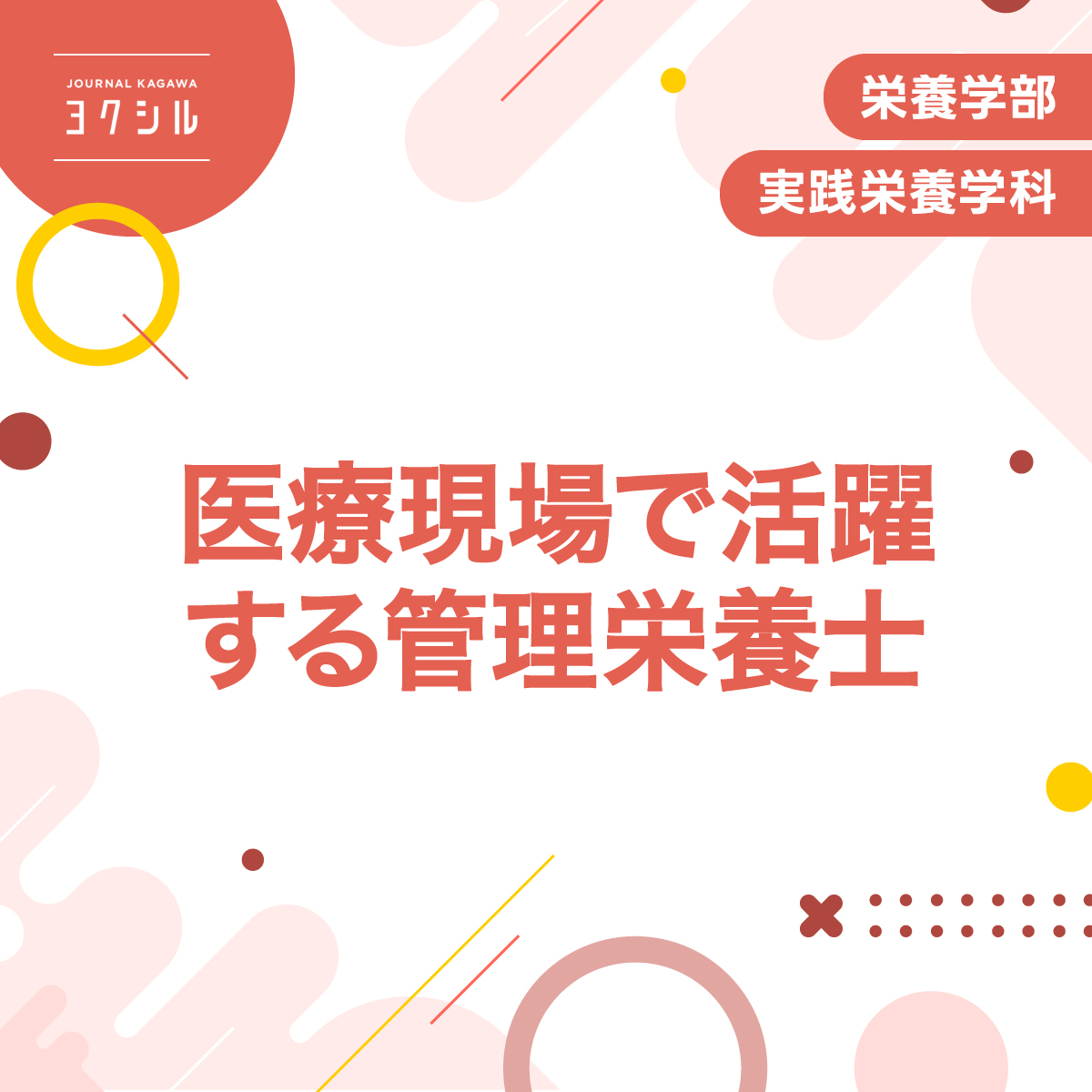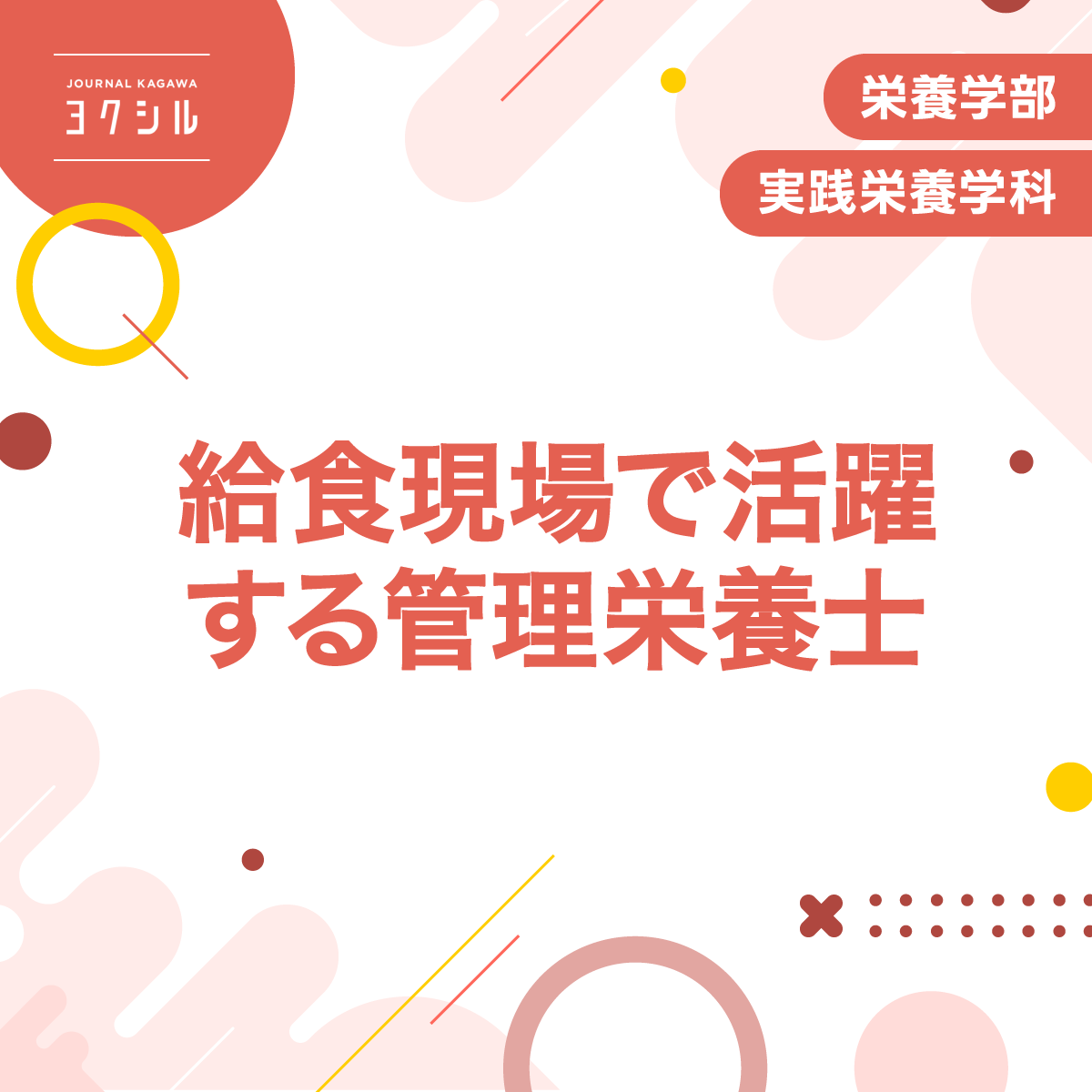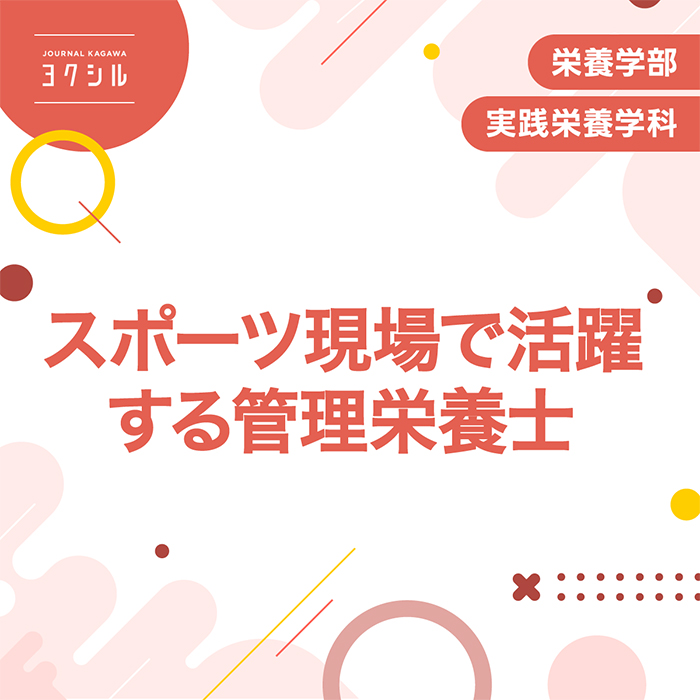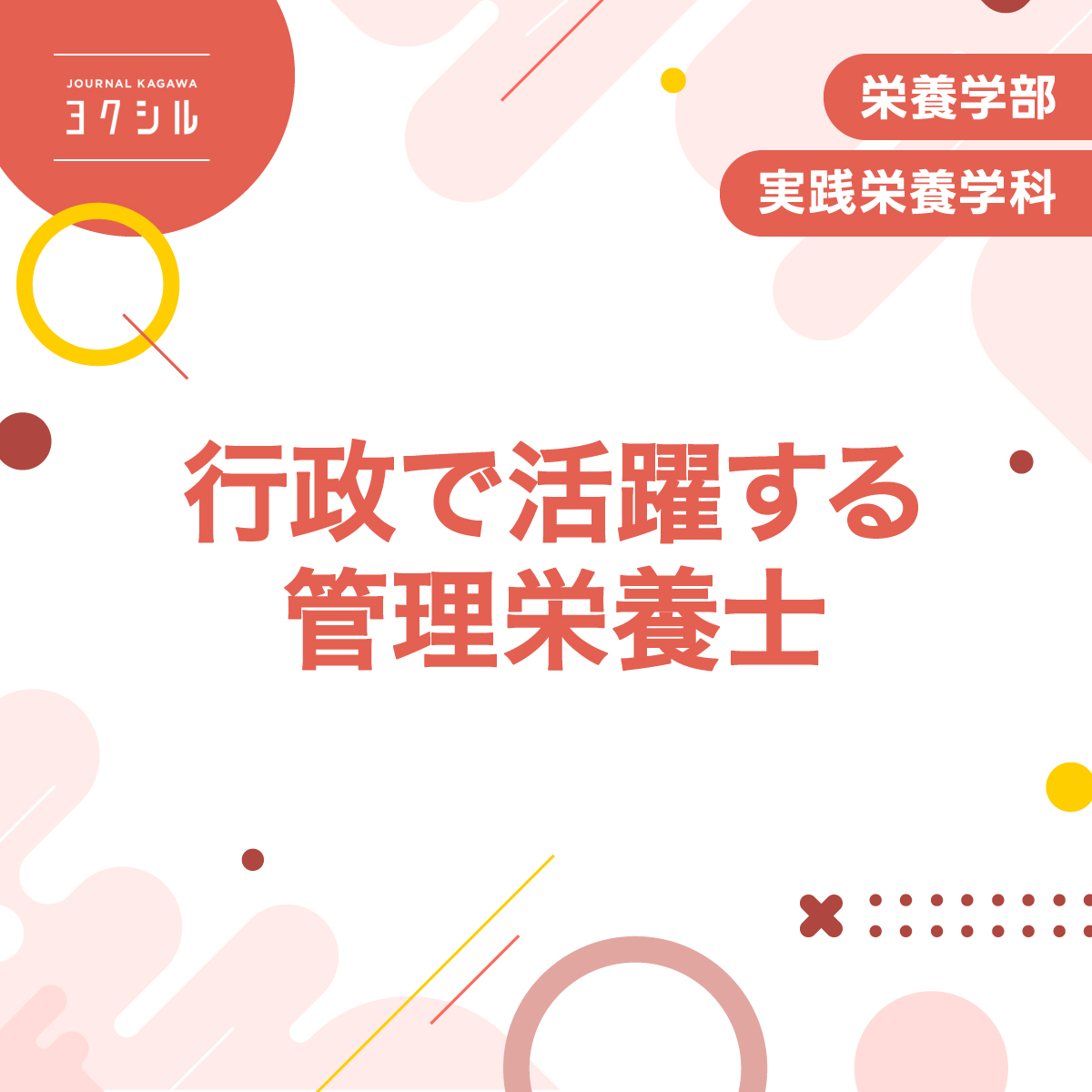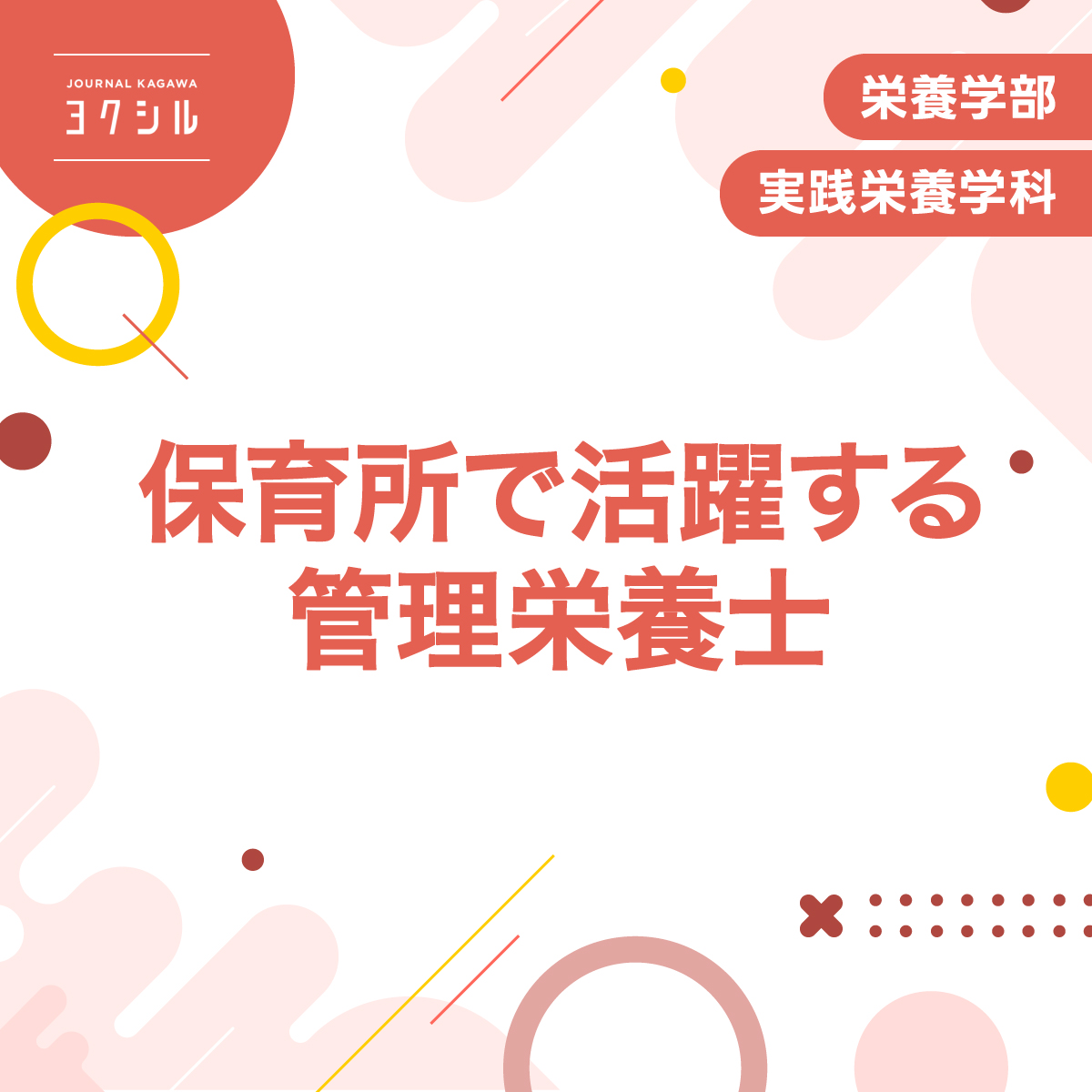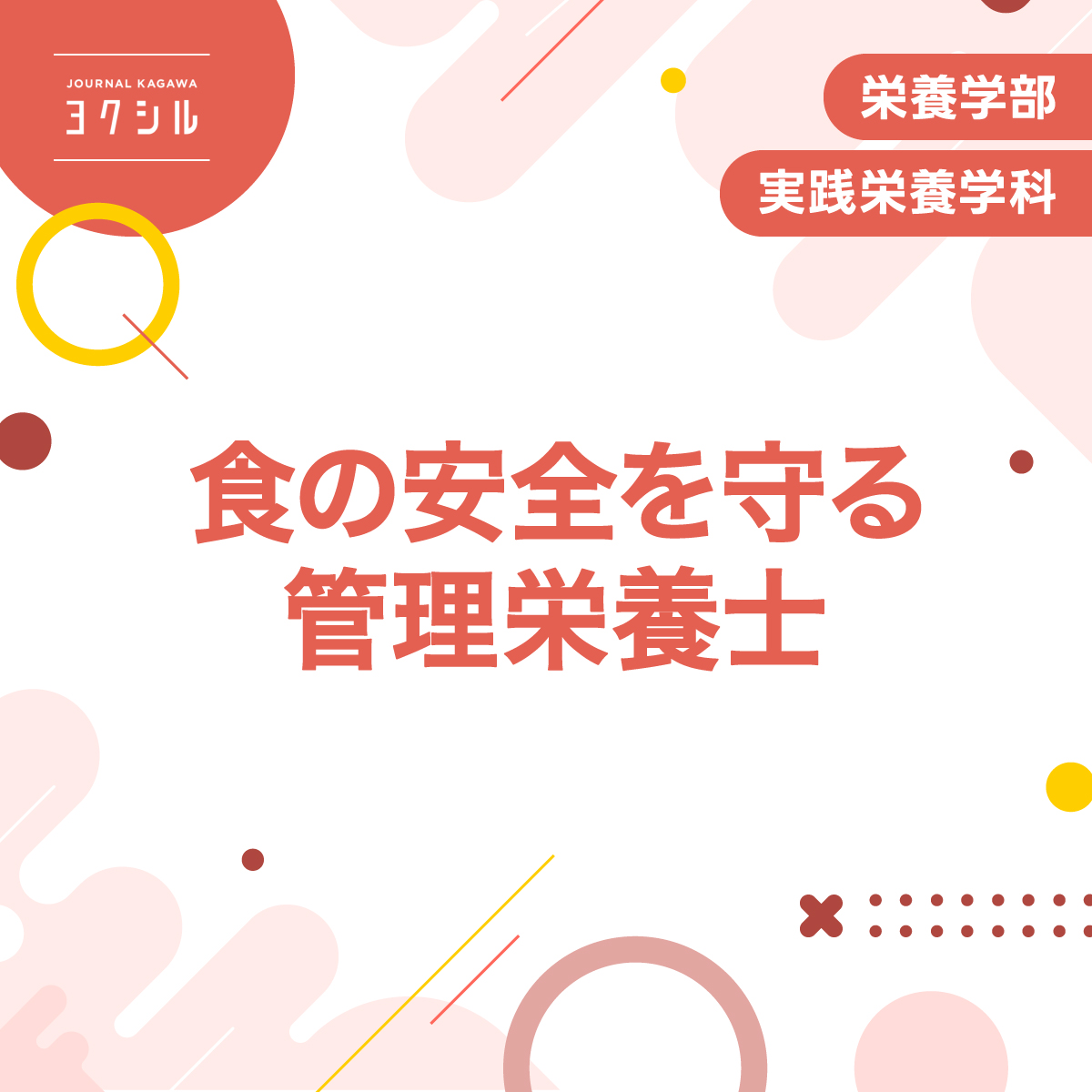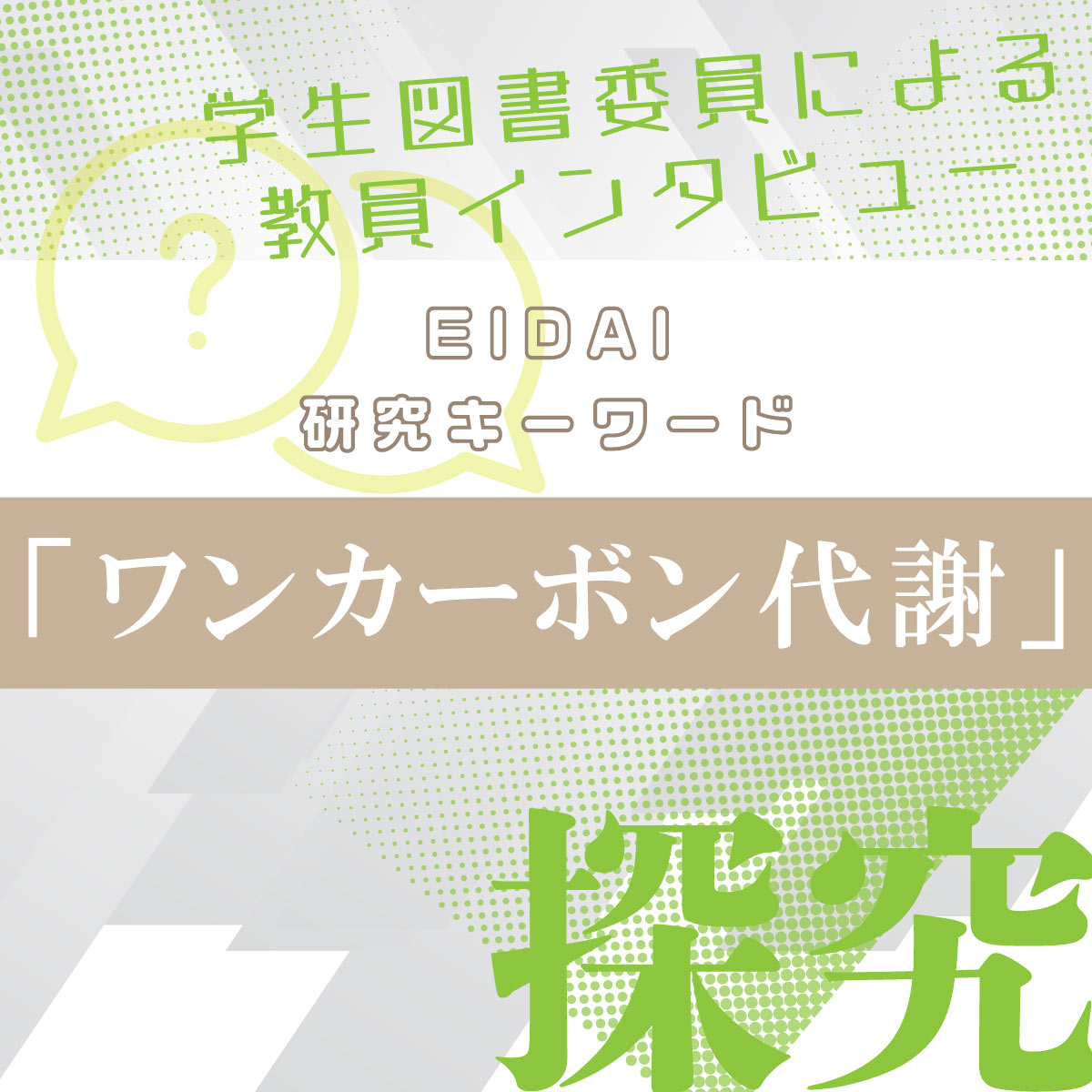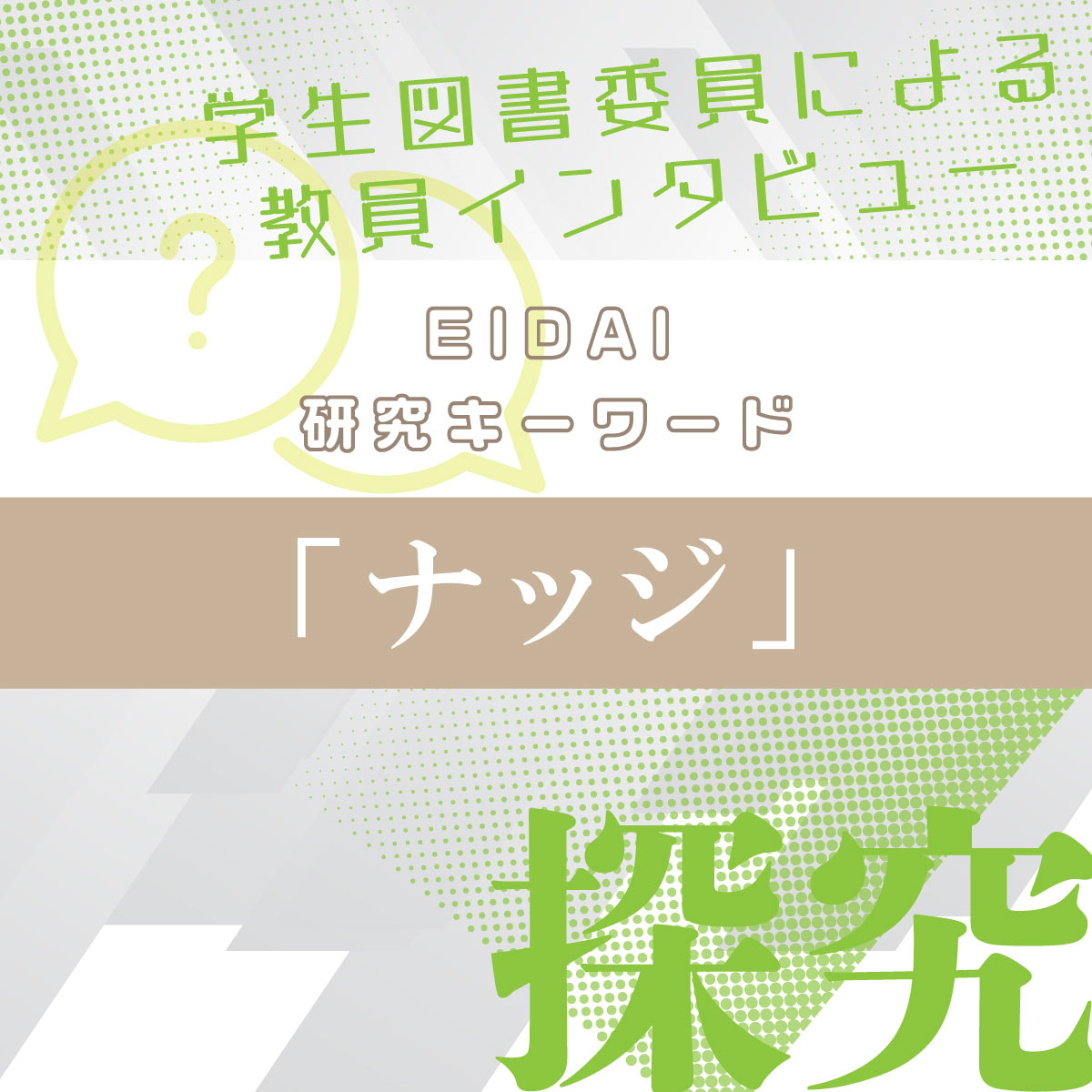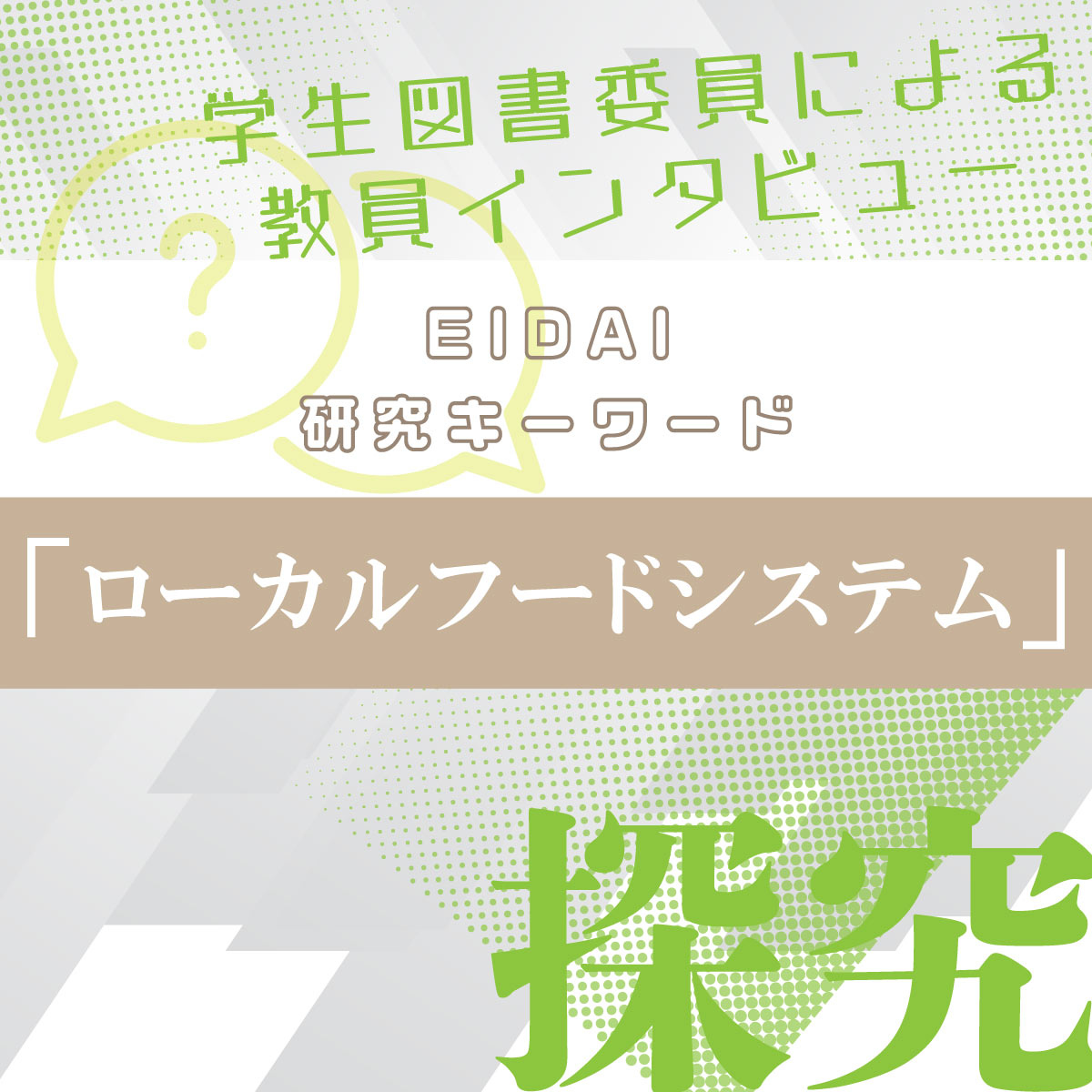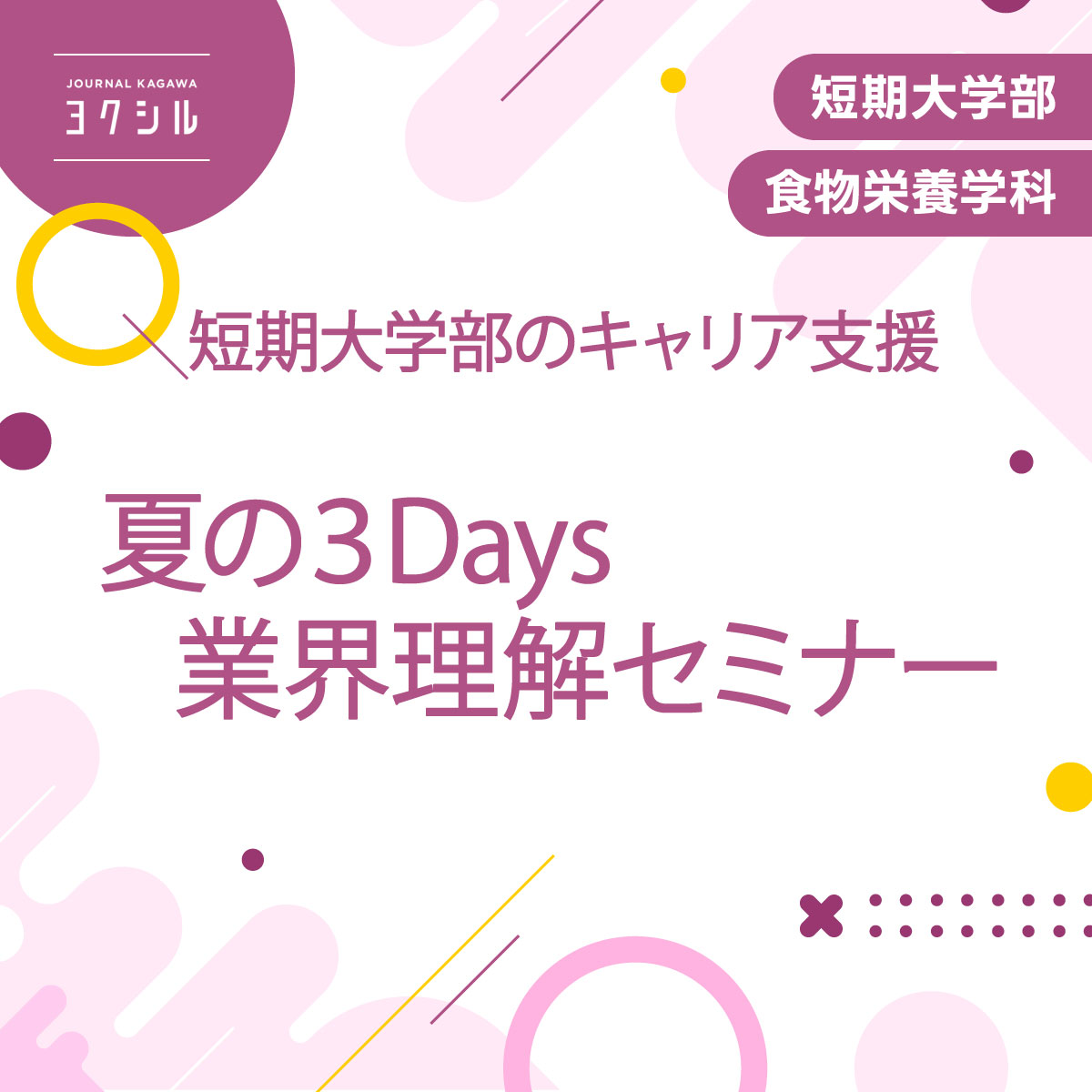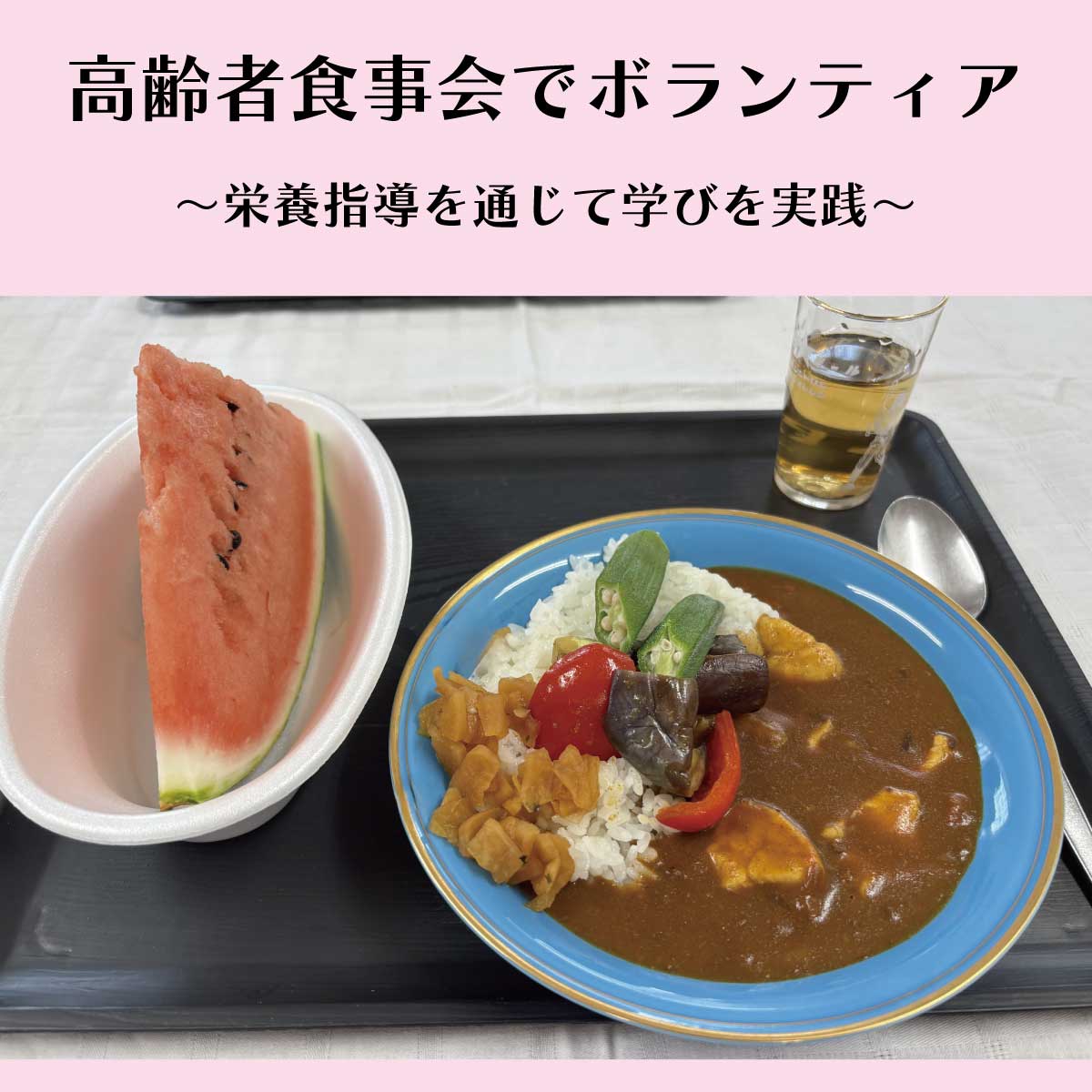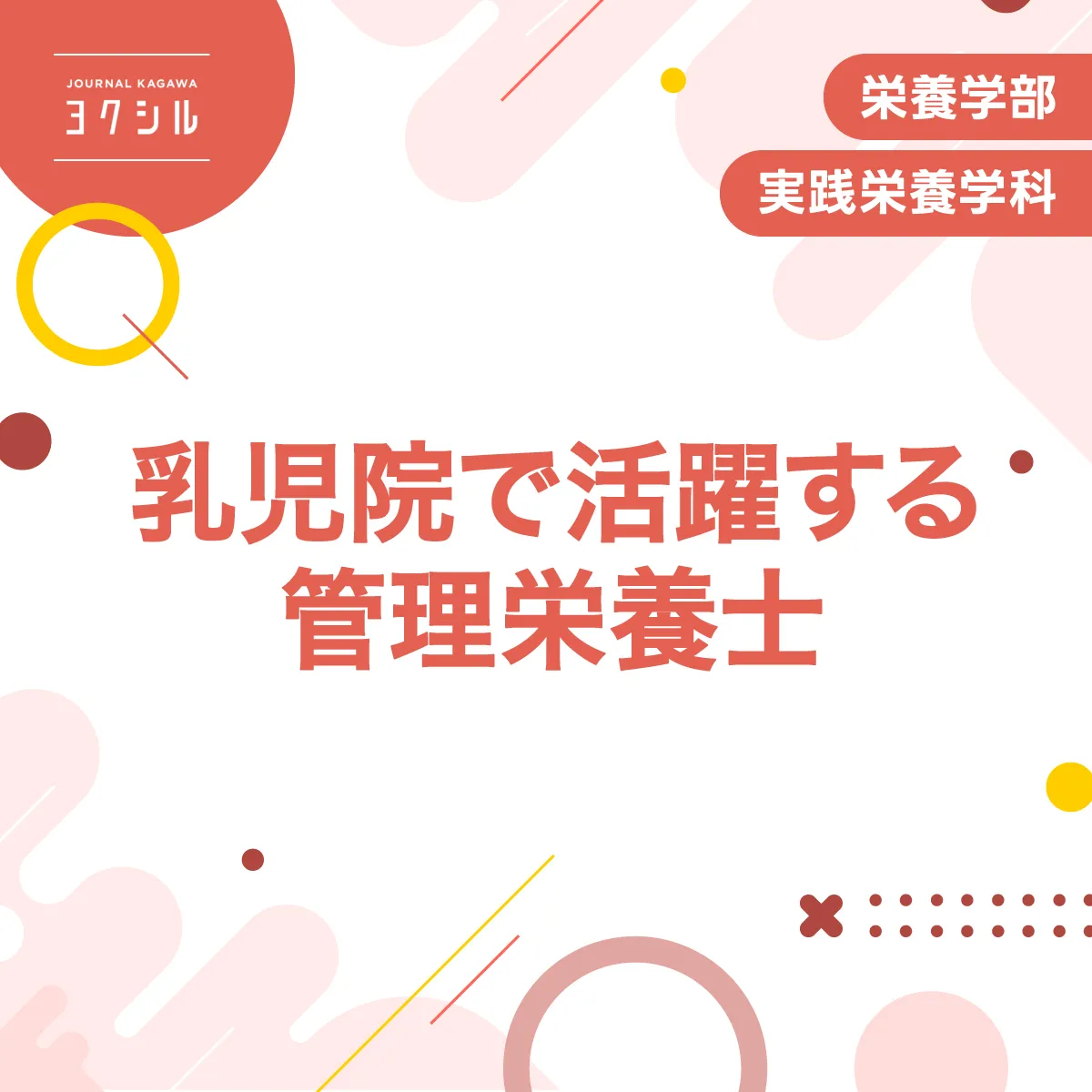
実践栄養学科
卒業生紹介
多職種のスタッフとの連携により、食を通して子どもたちの心身の健康を支える
活躍する卒業生

お名前:伊藤 希さん
勤務先:乳児院
卒業年:2015年3月(実践栄養学科卒)
多職種連携で子どもの食の自立をサポート
乳児院では、様々な理由で家庭での生活が困難な新生児から就学前までの乳幼児が24時間365日暮らしています。管理栄養士は食事計画の作成、栄養アセスメント、献立作成、発注、調理等を主に行っています。ミルク、離乳食、幼児食、おやつを用意しています。離乳食や幼児食は年齢や発達に応じた食べやすい形状の食事を用意しています。保育所や幼稚園とは異なり、離乳食で初めて食べる食材もあり、看護師等とも相談し進め、時にはアレルギー食も用意します。また、体調を崩した際には、病児食を用意する事もあります。
管理栄養士の役割は、栄養士、調理師、ケアワーカー、看護師、心理士、ファミリーソーシャルワーカー等の多職種と連携し、食を通して子どもたちの心身の健康を支えることです。
勤務先の乳児院では「食」の在り方のひとつに“何を食べるか”だけではなく“どのようにミルクを飲んだか”“どのように食べたか”という事にも重要な意味があるとの考えのもと、食卓が子どもたちと食を通じた関わりの場、関係作りの場としての役割を持つことも大切にしており、子ども達の食の自立に向けてサポートしています。
私の勤務する法人には、他の児童福祉施設があり、女子栄養大学の卒業生が多数就職しています。先輩方には日々助けていただいています。
建学の精神に基づく大学での学びを子どもの養育で実感
女子栄養大学では香川綾先生の「食は生命なり」の教えのもとに、食べることは生きることであると「食」について学びました。子ども養育においては、食べることはひとを育てるにはとても大事なことであり、生きていく上では食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を育んでいく事がいかに大切な事であるかを実感しています。
大学のカリキュラムはとても充実しており基礎から応用までを幅広く学ぶことが出来ました。実験や実習では仲間と共に成し遂げることの大変さや大切さも学んだように思います。
また、学外実習では、保健センターと保育所へ行かせていただき、その際に教えていただいた事は現在でも様々な場面で活かされており、子どもを養育するために多職種と共にチームで連携する事がいかに大切なことであるかを実感しています。
一人ひとりの子どもたちの成長にあわせて食から支える
この仕事を選んで良かったことは、子ども達の成長過程を「食」の視点から支えられることです。
ミルクの量や飲み方、離乳食の進め方、幼児食、アレルギー食、病児食等ひとりひとり様々です。子ども達の発達・発育状況等に合わせた方法を考え、子ども達の心身の変化が「食」に現れた際には多職種と連携し検討しています。一緒に楽しい食事を過ごせた時や子どもが“おいしい”と笑顔になった時、苦手なものを克服した時等とても嬉しく思います。
様々な困難もありますが、子ども達が成長していく姿は励みであり、やりがいを感じます。

おせち料理

お食い初め
専門職として学び続ける
大学卒業時に卒業後も視野を広げ、様々なことにアンテナを張ることもとても大切な事と教えていただきました。
就職してからは食に関わる研修会や乳幼児の発達心理等の研修会に参加しています。離乳食や幼児食についてはより専門的に学ぶ為に資格を取得しました。今後も子ども達に「食」の大切さや楽しさを伝えていきたいと思っています。
また、社会は日々変化しており、様々な情報で溢れています。管理栄養士として適切な正しい情報を伝えていけよう日々精進していきたいと思っています。


高校生へのメッセージ
私は、大学入学前、これからどんな生活が始まるのだろうか。どんな仲間に出会うのだろうか。と期待や不安と様々な気持ちであったことを思い出します。女子栄養大学で4年間過ごし、とても貴重な経験をさせて頂きました。
大学で出会った友人とは卒業後も連絡を取り合い、それぞれの道へ進み頑張っている姿は励みになっています。女子栄養大学は幅広く沢山のことを学ぶことができ、先生方もとても熱心な方々が多く、最後の日まで親身になり支えてくれます。これからそれぞれの道に進む皆さんの活躍を応援しています。


![[EIDAI栄養学]栄養学を深く広く学んで、管理栄養士になる](/uploads/2024/12/20241223092839.webp)
![[EIDAI栄養学]栄養学を学んで、多彩な管理栄養士に成長する](/uploads/2024/12/20241223092928.webp)
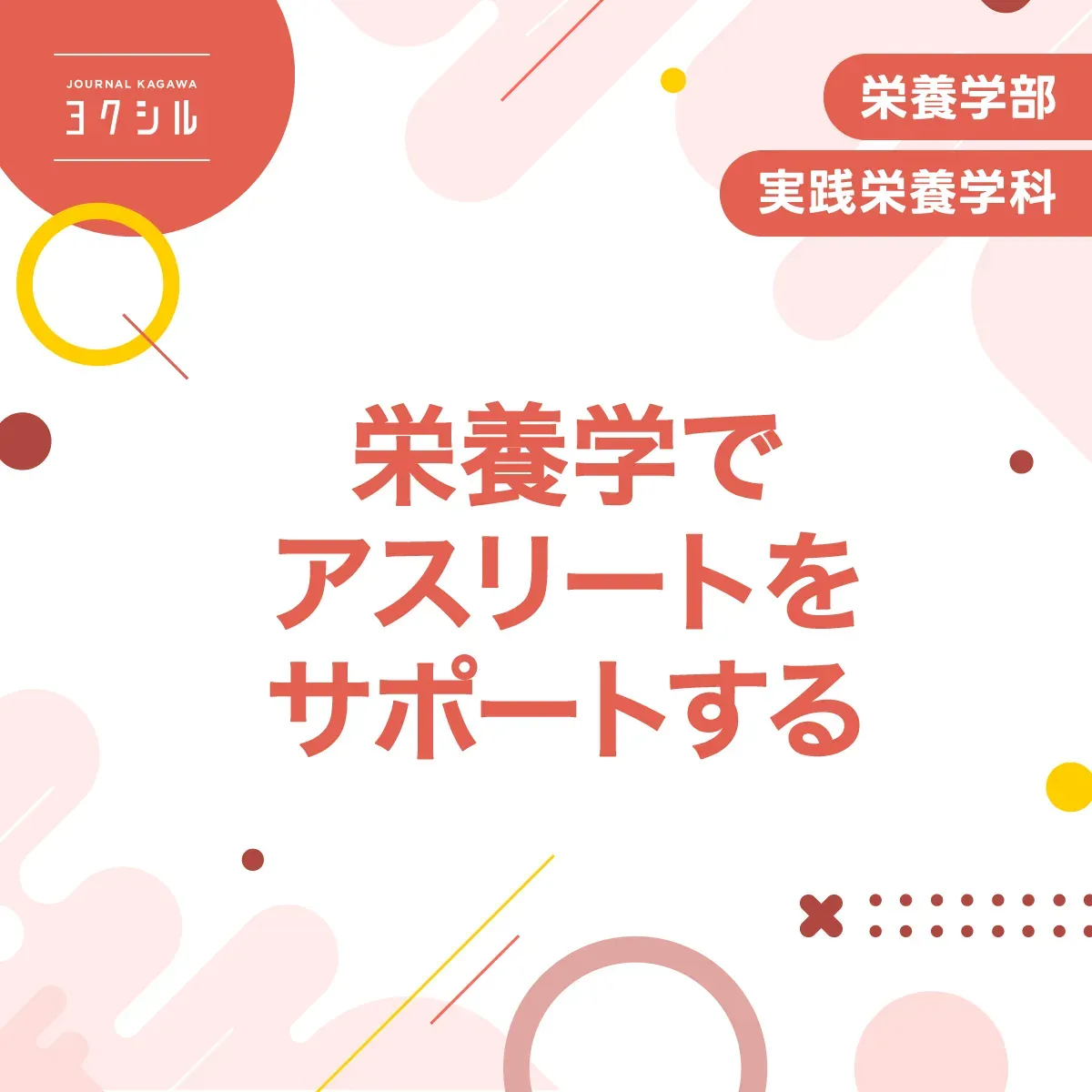
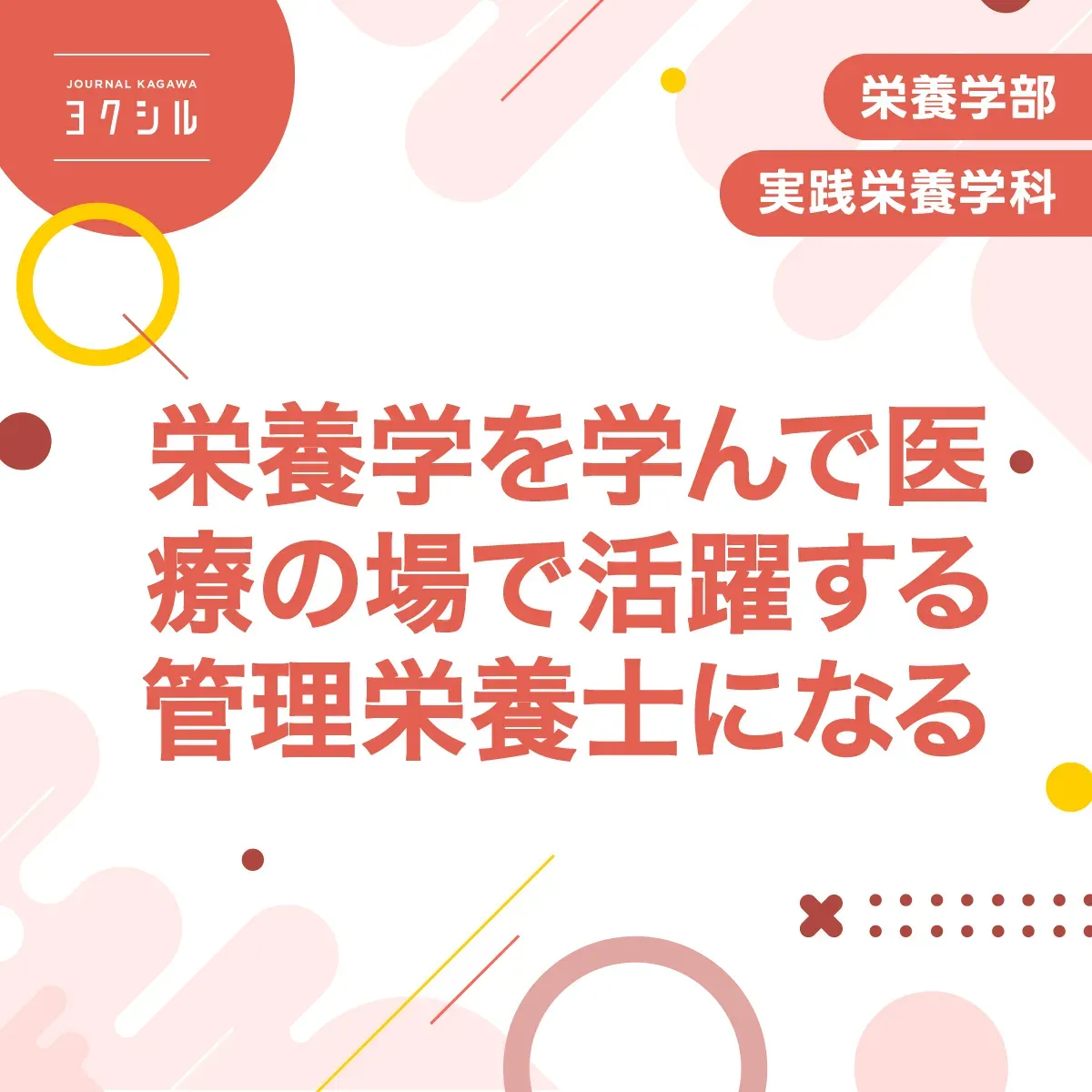
![[EIDAI栄養学]実践栄養学科の学び:食事提供のリアルに近づく(前編)](/uploads/2024/12/20241223093006.webp)
![[EIDAI栄養学]実践栄養学科の学び:食事提供のリアルに近づく(後編)](/uploads/2024/12/20241223093018.webp)