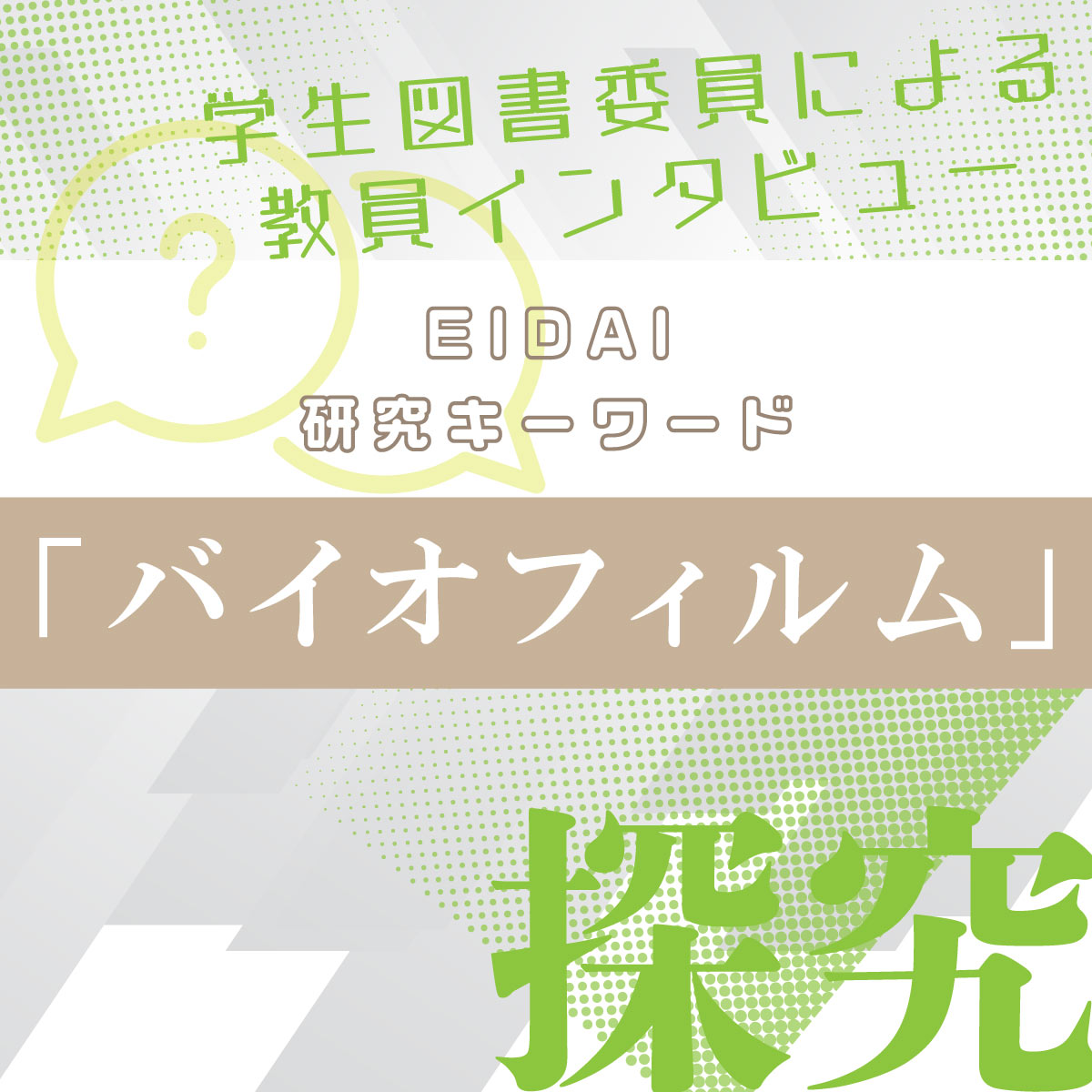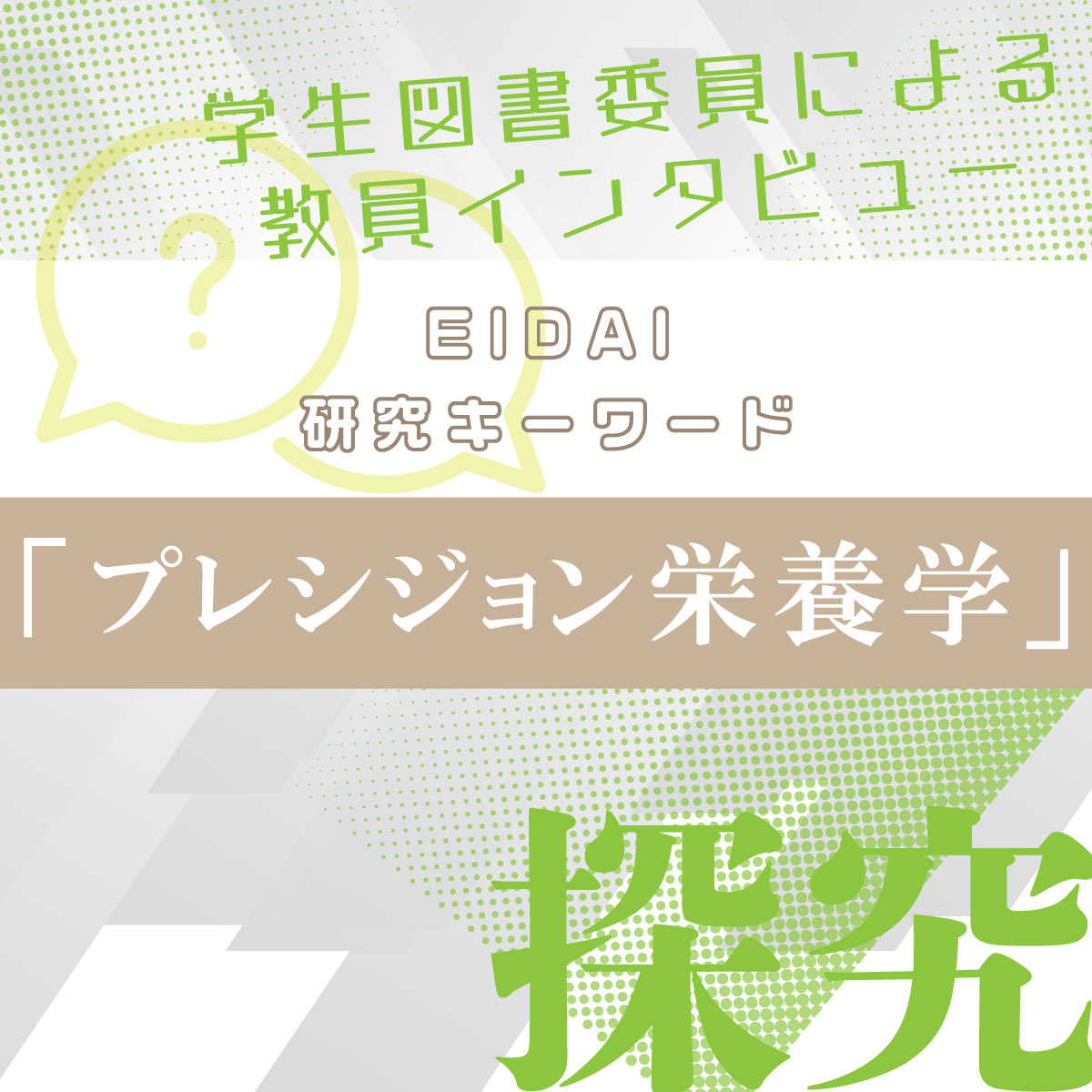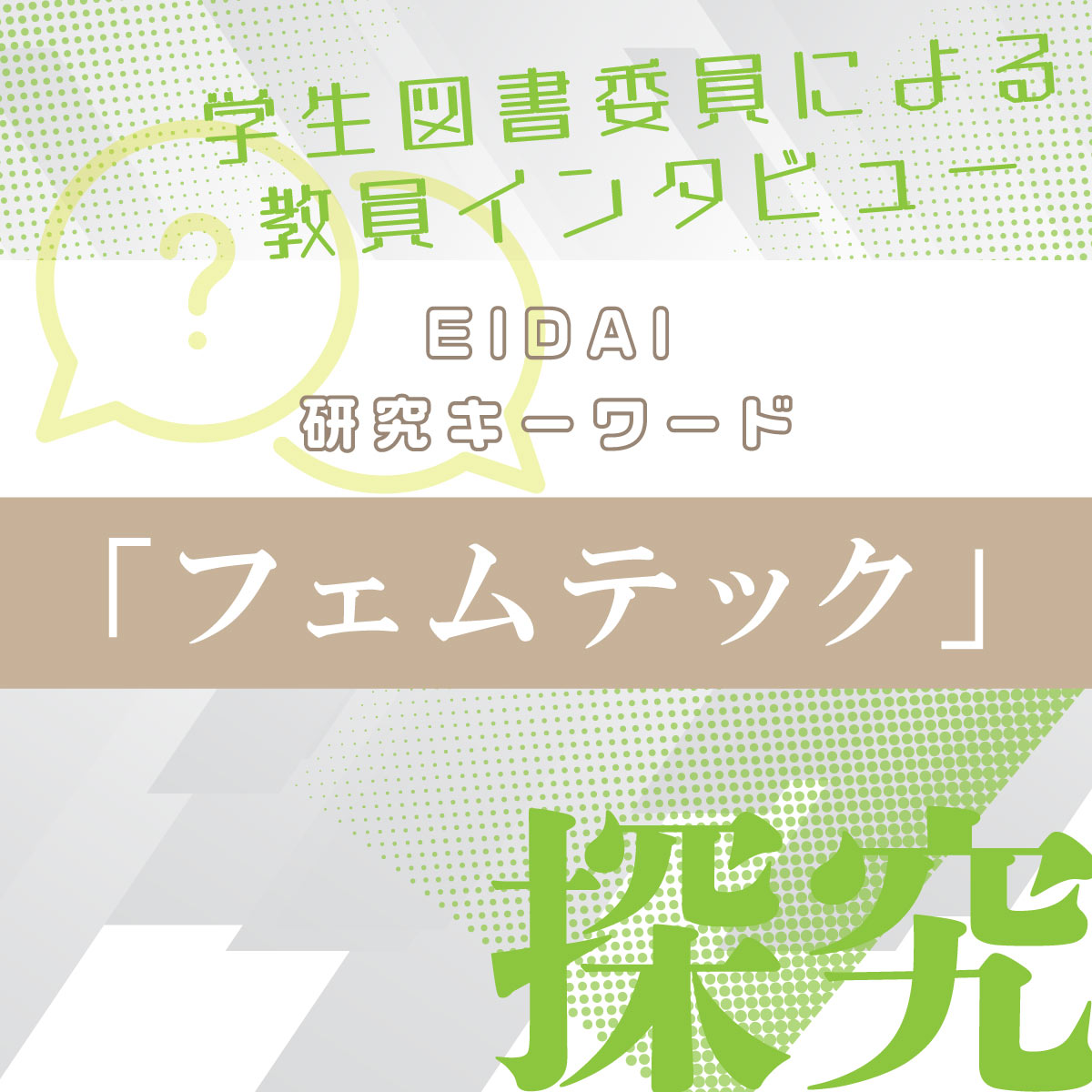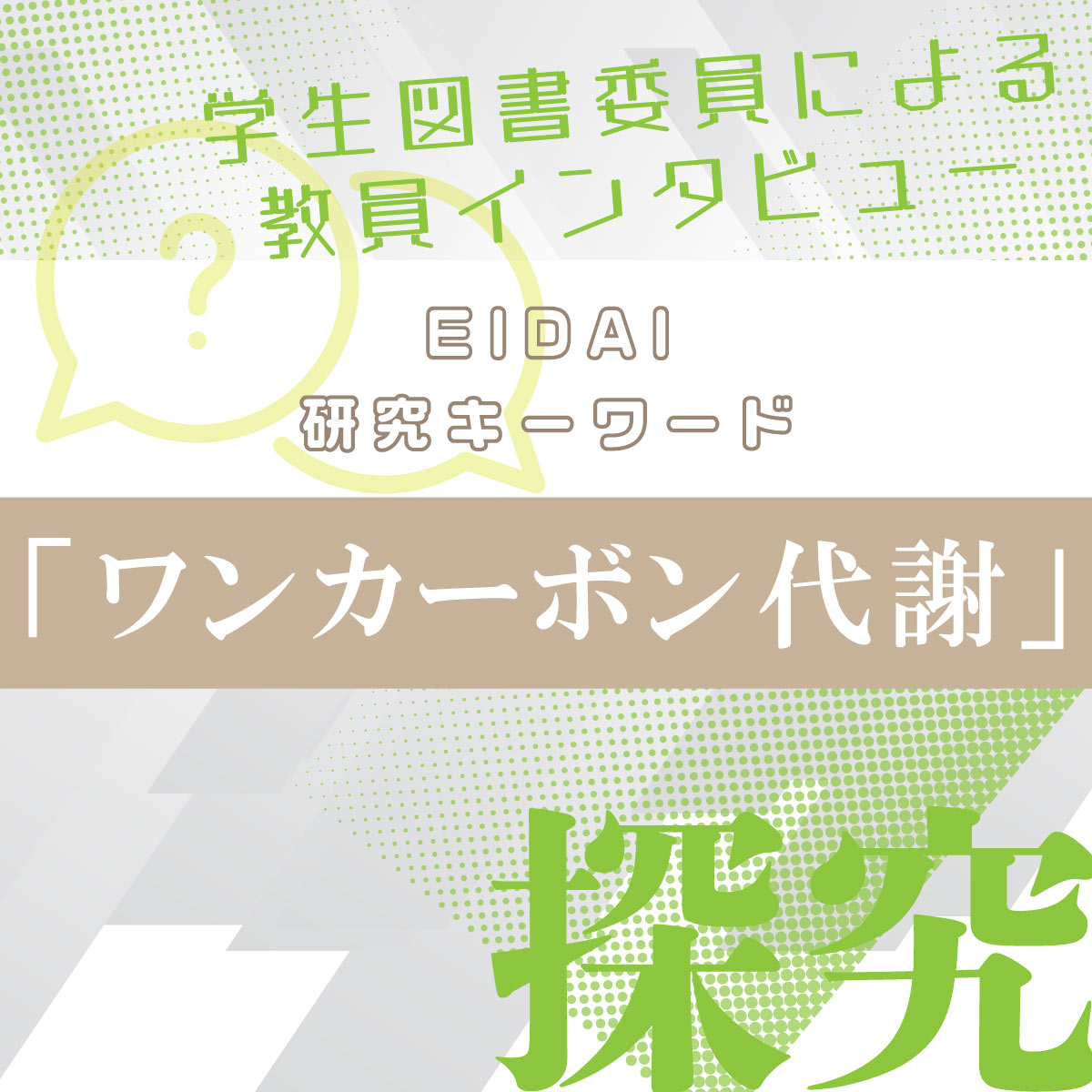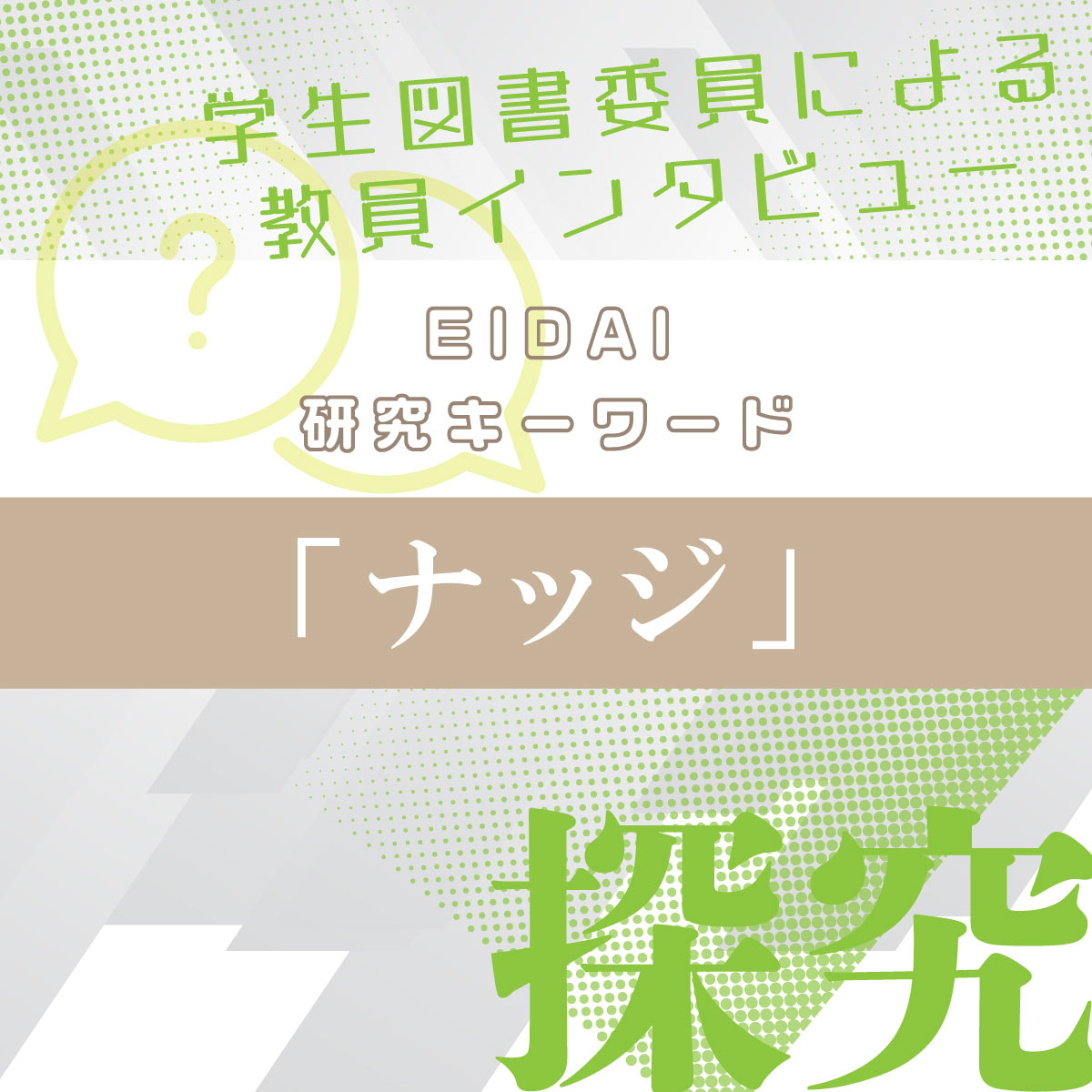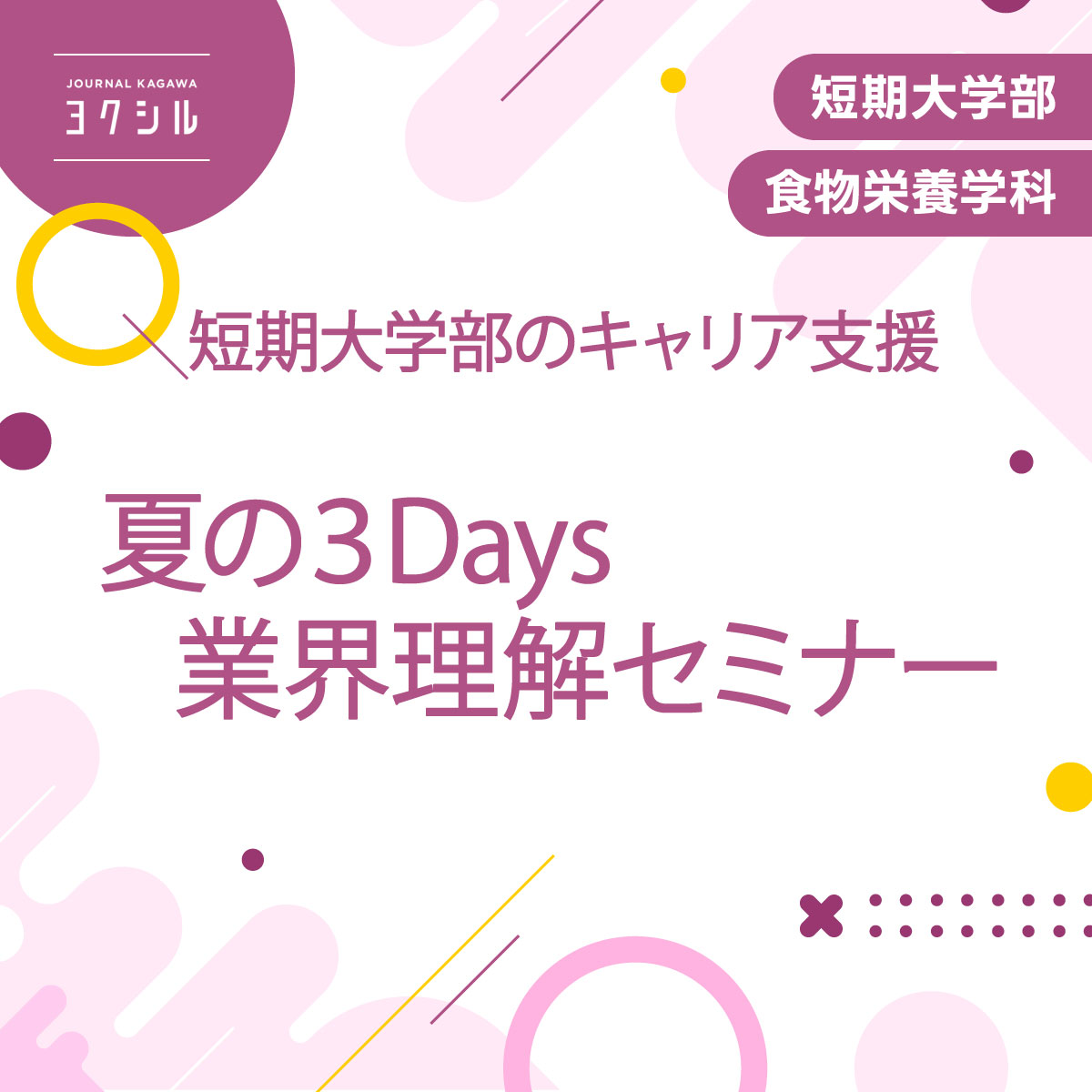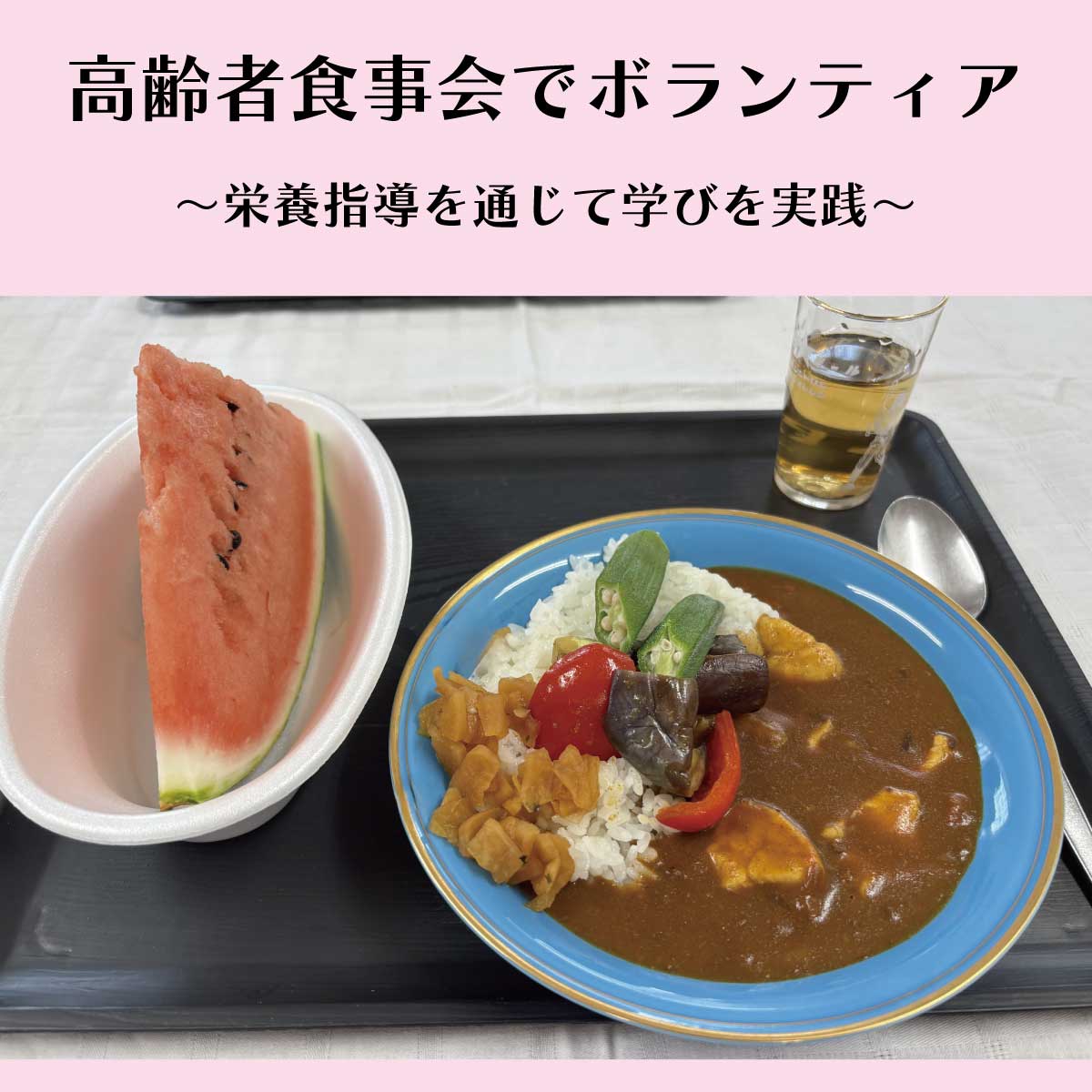本学教員の研究キーワードは実に多彩です。その中から、まだみんなに知られていない、興味深いキーワードをピックアップしました。学生図書委員による教員インタビューで、研究キーワードを探究していきます。

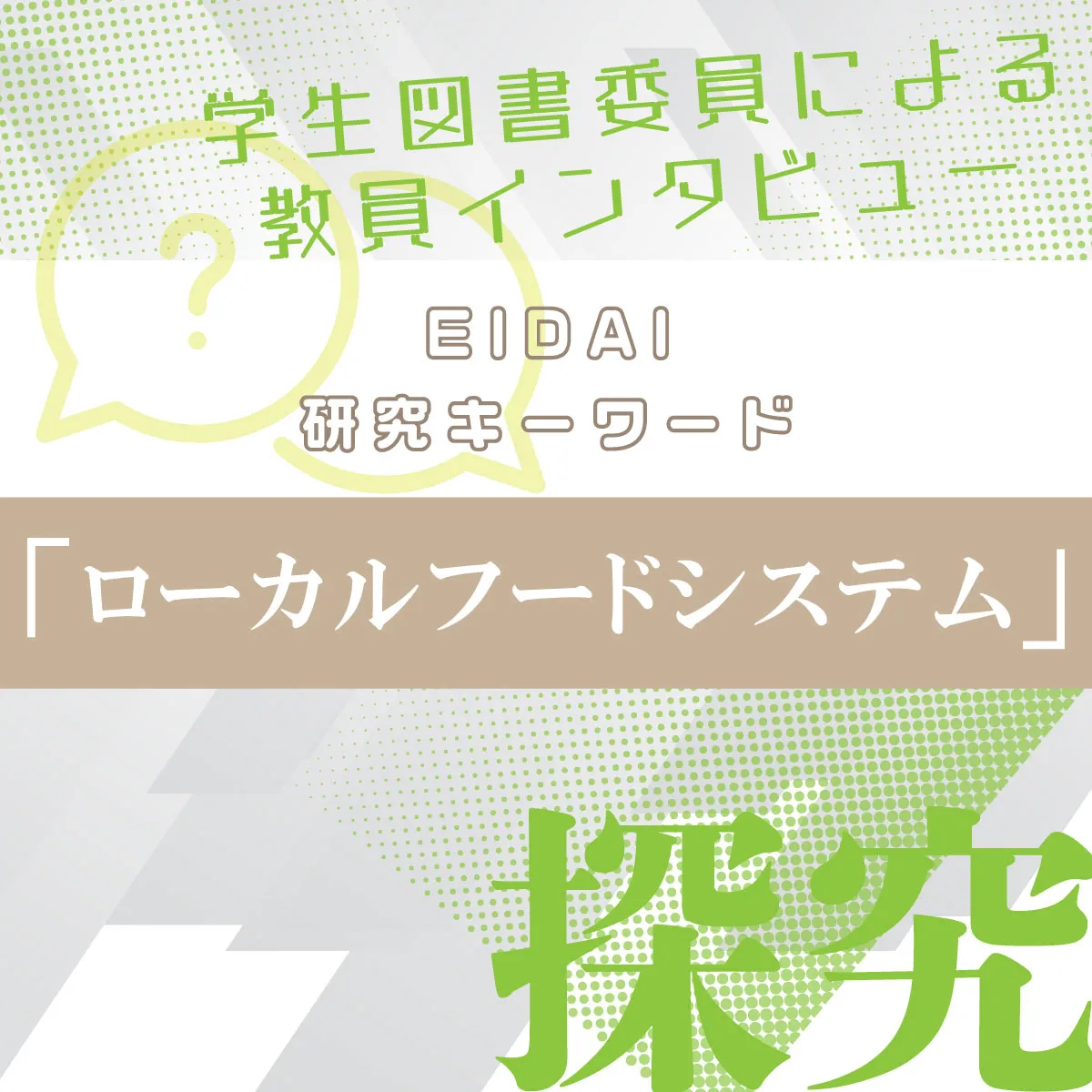
学びと教育
探究:研究キーワード④「ローカルフードシステム」

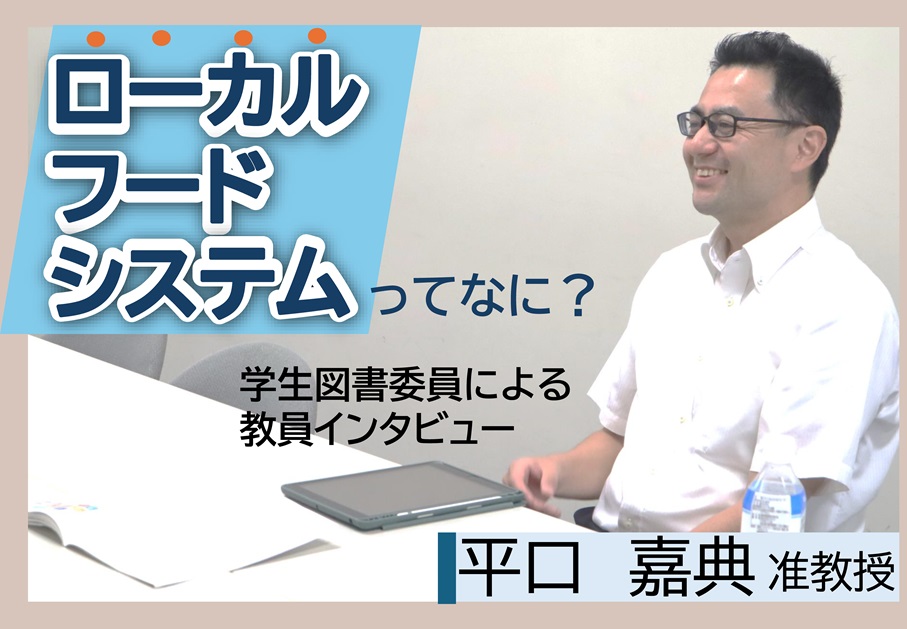
今回のキーワードは、「ローカルフードシステム」
「ローカルフードシステム」について、学生図書委員が、平口嘉典先生にお話を伺いました。
ローカルフードシステムとは、どういうシステムなのでしょうか?

フードシステムとは、簡単にいうと、生産から消費まで食料全体の流れのことですが、その地域版がローカルフードシステムです。
例えば農産物直売所では、農家の方が直接そこに出荷して、消費者の方が直接買いにくる、生産者と消費者の直接的な関係で食料供給が成り立っています。
地産地消という言葉は有名で、地域で生産されたものを地域で消費する取組みもローカルフードシステムに含まれます。諸外国でも取組みが進んでいて、韓国では「身土不二」、イタリアでは「スローフード」、北米では「CSA(Community Supported Agriculture;地域支援型農業)」として実践されています。
食の流通を通して、地域を支え、地域の様々な社会問題の解決につなげていこうとするものです。
地域ごとに特色ある農産物や食文化がありますが、それらを持続的に活用していくために特に重要な要素は何だとお考えでしょうか?
農産物だと作る人、食文化だと実践し伝える人、どちらも担い手がいないと持続的にはなりません。担い手の確保が重要です。
農家に関しては高齢化が急速に進んでいますから、農家の数がどんどん減り、作る農産物も減ってしまいます。そうすると、さらに海外からの輸入に頼ることになってしまいます。農業の技術を引き継いでいく担い手として、若い人を呼び込んでくることが大事なことです。
食文化も同様で、いま中高年の方が実践している作り方や食べ方が、若い人に伝えられ継承されなければ、次代にはつながらず、持続的にはなりません。そもそも若い人たちが情報をキャッチする機会がないということであれば、まずは情報をちゃんと伝える、そうした場を作ることが大切です。
―食文化を継承する場はどこなんでしょうか?
家庭や地域が主な場であり、ローカルフードシステムもそのひとつです。
ローカルフードシステムにおいて、生産者と消費者のつながりを強化する効果的な方法はありますか?
農産物直売所もそうですが、単なるモノの売り買いだけではない関係性を築くことが、つながりを強化することになると考えています。
そのためには、生産者と消費者が交流することが大事です。たとえば、意見交換をしたり、消費者が生産現場を訪ねたりといったことです。交流を通して、安心感や信頼感、お互いに支えたい・助けたいと思い合える気持ちなど、モノの売り買いを超えた関係性が生まれます。

先日実施した「地域振興論実習(食文化栄養学科・3年次開講)」でも、川越市でがんばっている農家さんからお話を聴かせていただきました。消費者とのつながりを大切にしている生産者のお一人です。自分たちが消費者の食料を生産し、安全を確保しているという誇りをお持ちで、将来食の世界で働く本学の学生に安心を担保してほしい、お互いがそれぞれの役割を果たしていきましょうと、熱く語っていました。
―先日の実習に参加して、生産者の方のそうした言葉は確かに刺さり、自分にできることをちゃんとやっていこうと思いました。炎天下でも作物を守り育てていて、人に届けるために自分がやるんだという強い気持ちが伝わってきて、すごいなと思いました。
ローカルフードシステムを発展させることは、フードロス削減にどう結びつく可能性があると思いますか?
市場に農産物を出すと規格が決められているので、形の良いもの、サイズが整ったものしか出荷できません。ですが、形が悪いけれど味がおいしいといったものも直売所では販売することができるので、フードロスの削減につながります。
また、私自身、秋田のネギ農家さんから、ネギの青い部分もおいしいのでぜひ食べてほしいというお話を聞いて、捨てずに食べるようになった経験があります。生産者の実際のお話は、ふだんのなにげない行動を変えるきっかけにもなります。
輸入食材が日常的に流通する現代において、ローカルフードシステムを守り育てるためには、どのような戦略が有効でしょうか?

消費を促進することが大事ですが、そのためには大きく2つの戦略があると考えています。
1つは、消費者の中でも意識が高い人に向けたものです。ローカルフードシステムを進めれば、地域の農家の方々の所得増につながる、あるいは規格外のものにも価値が出てくるといったように、生産サイドに目を向けた情報伝達を行い、積極的に働きかけていくアプローチです。
でも、それだけでは広がらないので、もう1つの戦略としては、そうではない方々に向けてのものです。地産地消にしても、意義や必要性を訴えかけるのではなく、楽しさやおいしさを見つけておすすめしていくアプローチです。
今日はちょうどゼミで三芳町のお弁当開発の試作をしたところです。地元野菜を広めていくために、ただ野菜を売るのではなく、見た目も彩り良く味もおいしく、食べたくなるようなアイデアを学生たちが考えて、お弁当に加工する。それによって三芳町の野菜がどんどん消費されていく。まさに“おいしく楽しく”戦略です。
今後を見据えたとき、ローカルフードシステムはどのような方向に発展していくとお考えですか?
新規の取組みが増えるというよりは、いまある取組みを維持する方向に進むでしょう。農産物直売所の数は、1990年代以降、増えてきました。ただ、ここ10年ほどその伸び方がゆるやかになっています。なぜかというと、高齢化によりやめてしまうこともありますが、直売所をたくさん作りすぎたこともあります。これからは直売所を増やしていくのではなく、今あるものをどうやって盛り上げていくかが大事になります。
一般の方々に直売所に関心を持ちもっと来ていただく、そこでおいしさや楽しさを味わっていただくことができれば、ローカルフードシステムが持続的なものになっていくと考えています。
―学生が関わる余地はあるでしょうか?
学生さんも消費者の一人です。機会を見つけて直売所を利用してみる、地元の食材を使った飲食店に行ってみる。毎日じゃなくて、週に1回、月に1回でも行く機会をつくるだけで、ローカルフードシステムの維持に貢献することができます。
また、本学の食文化栄養学科で学んだ人は、実際に生産側のサポートができます。先ほどの三芳町のお弁当開発もその一例ですが、地域振興に関わることができます。
なにより学生さんには、固定観念ではなく、これまでにはないメニュー、見た目のかわいらしさ、意外な組合せによるおいしさを生み出す感性や力があります。それが、地域に新しい風を吹き込むことにもなります。
食文化もローカルフードシステムも、時代時代で変わっていくもので、若い人たちがやりやすいように変えていっていい、そのチャンスを生産者と消費者が一緒に作っていけたらと思います。
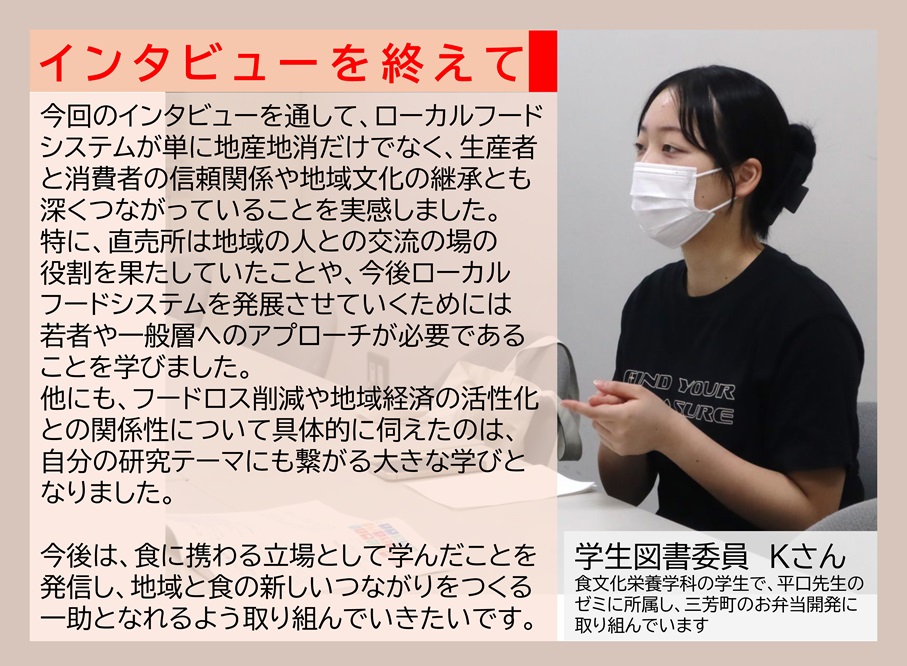
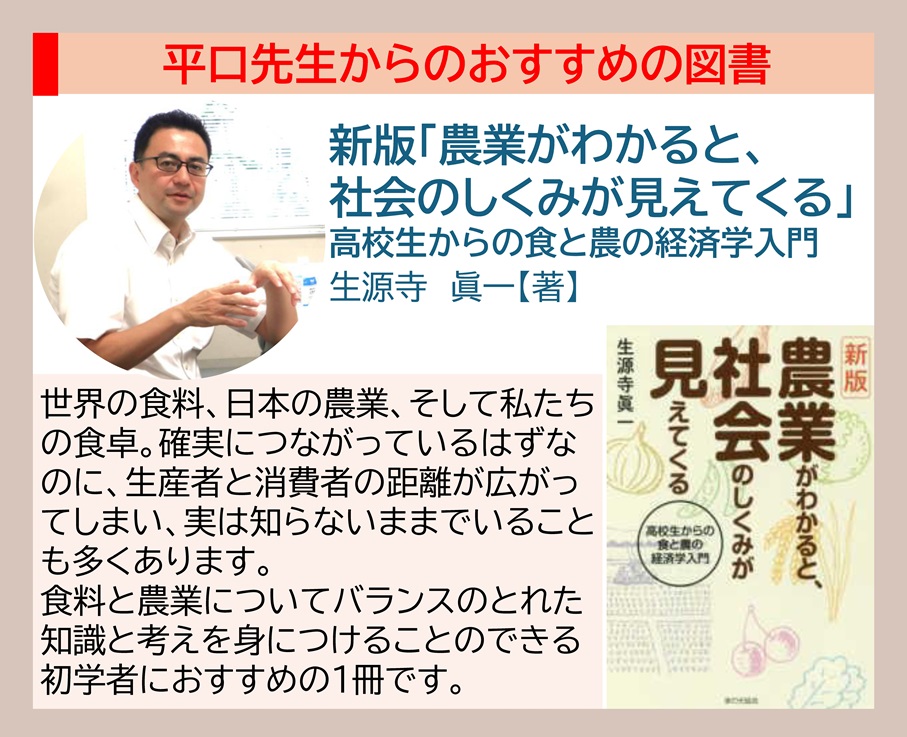
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部は、2026年4月より共学化に伴い、日本栄養大学・日本栄養大学短期大学部に名称変更いたします。