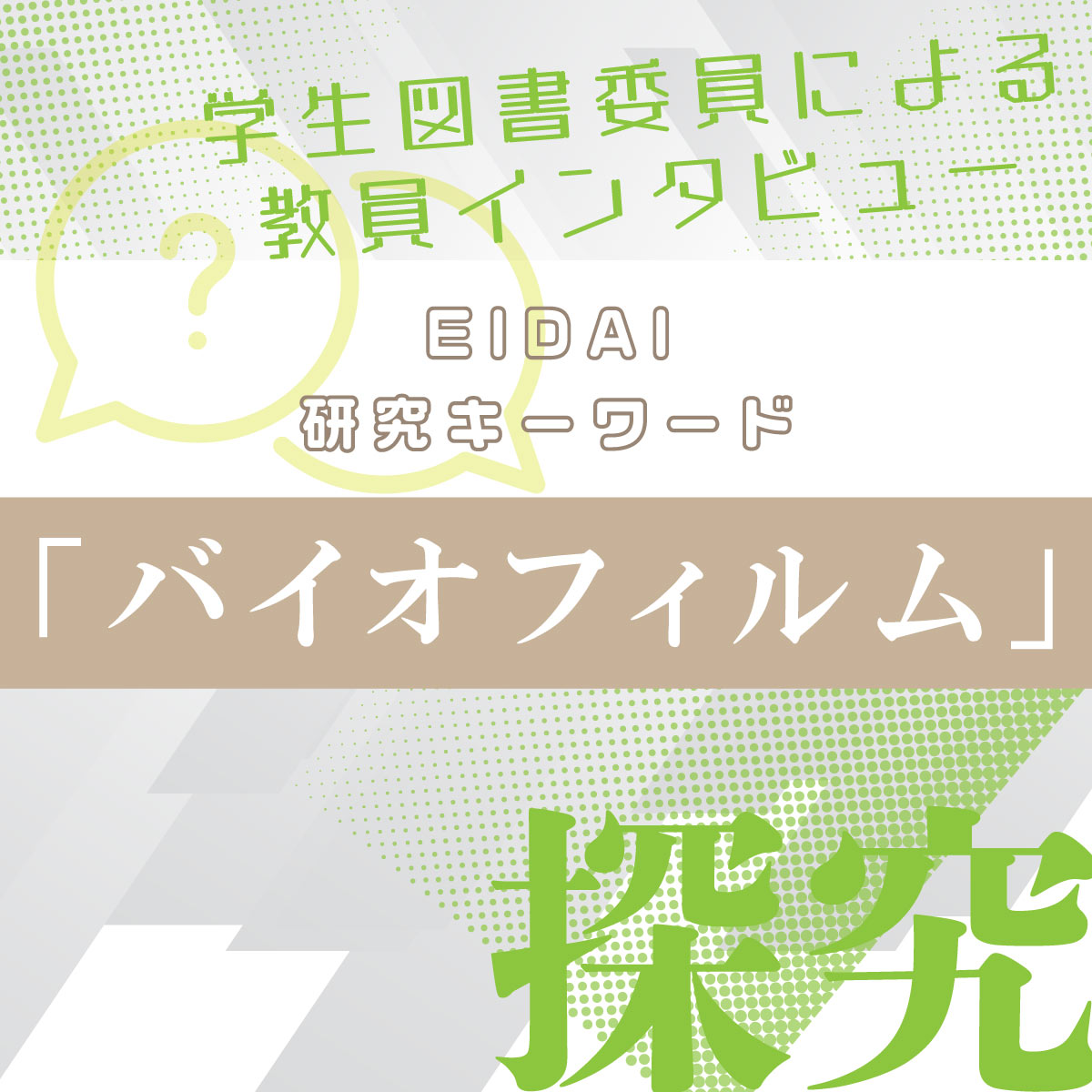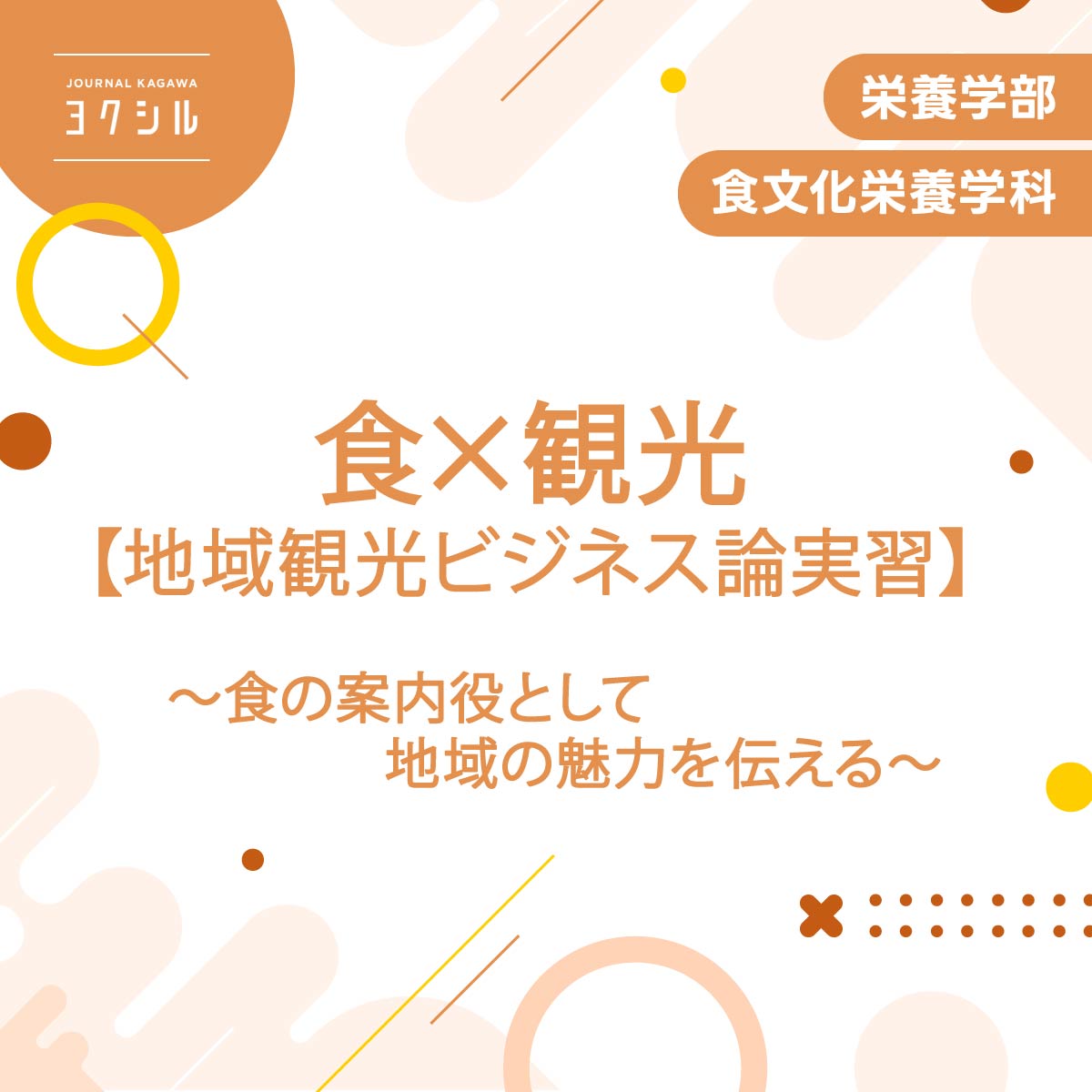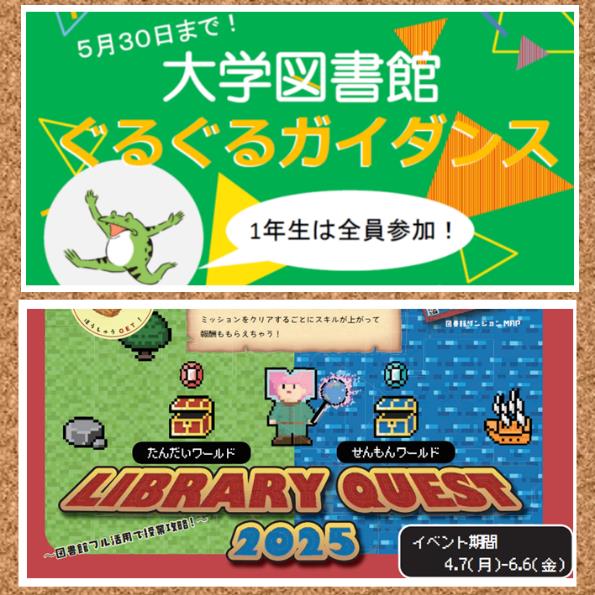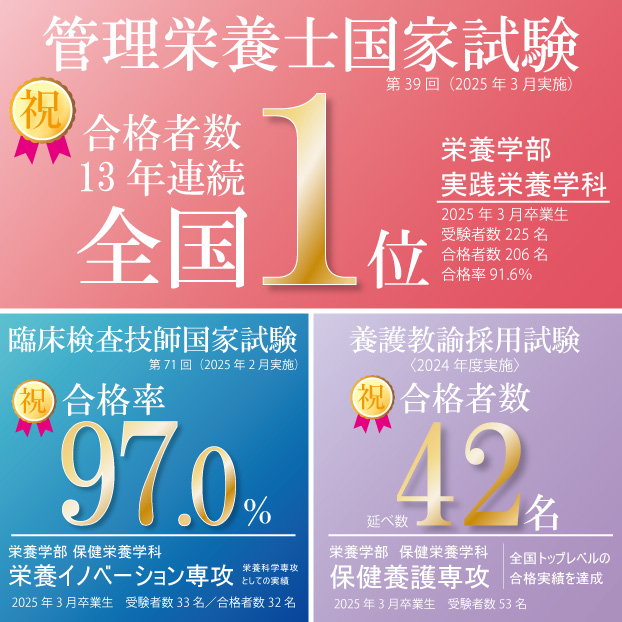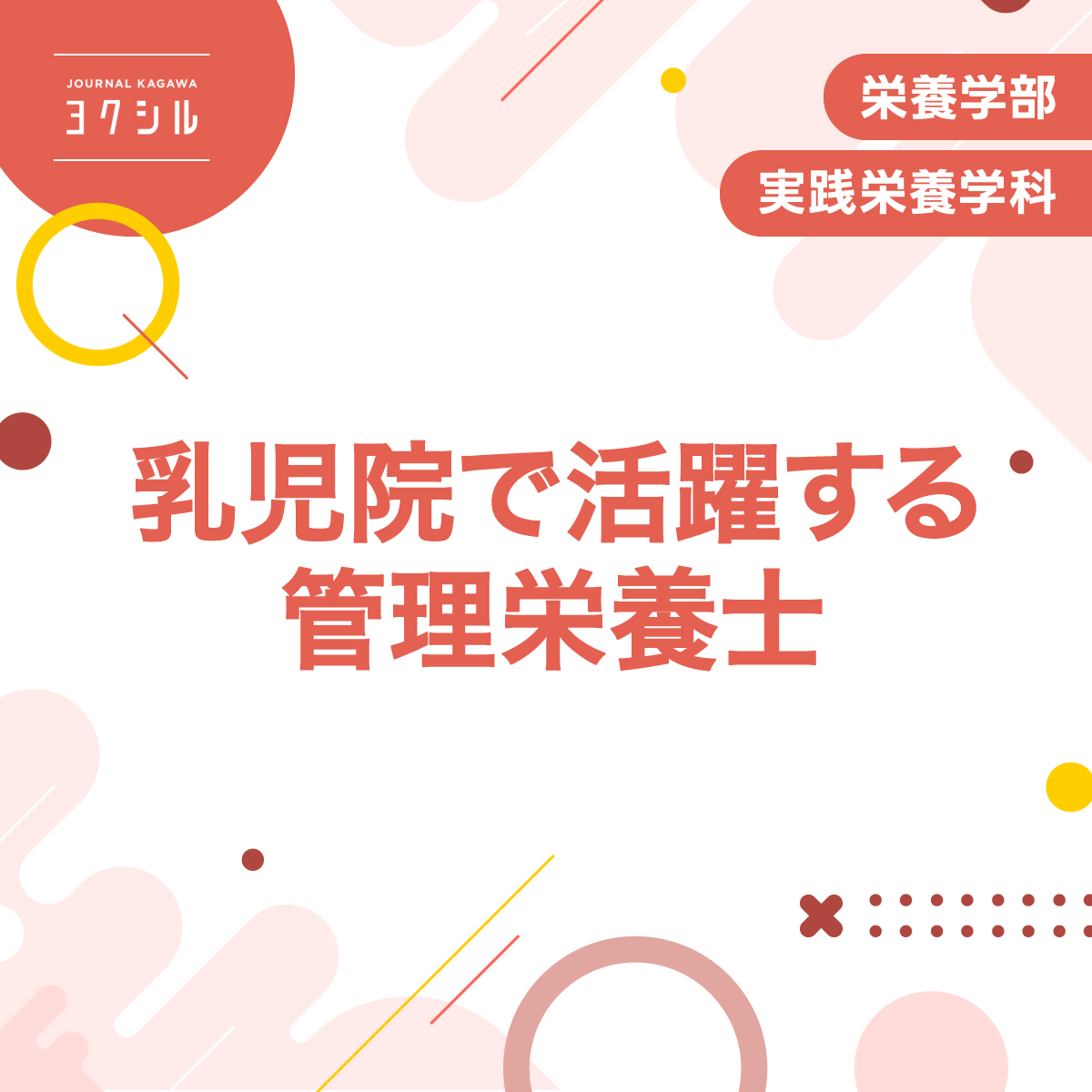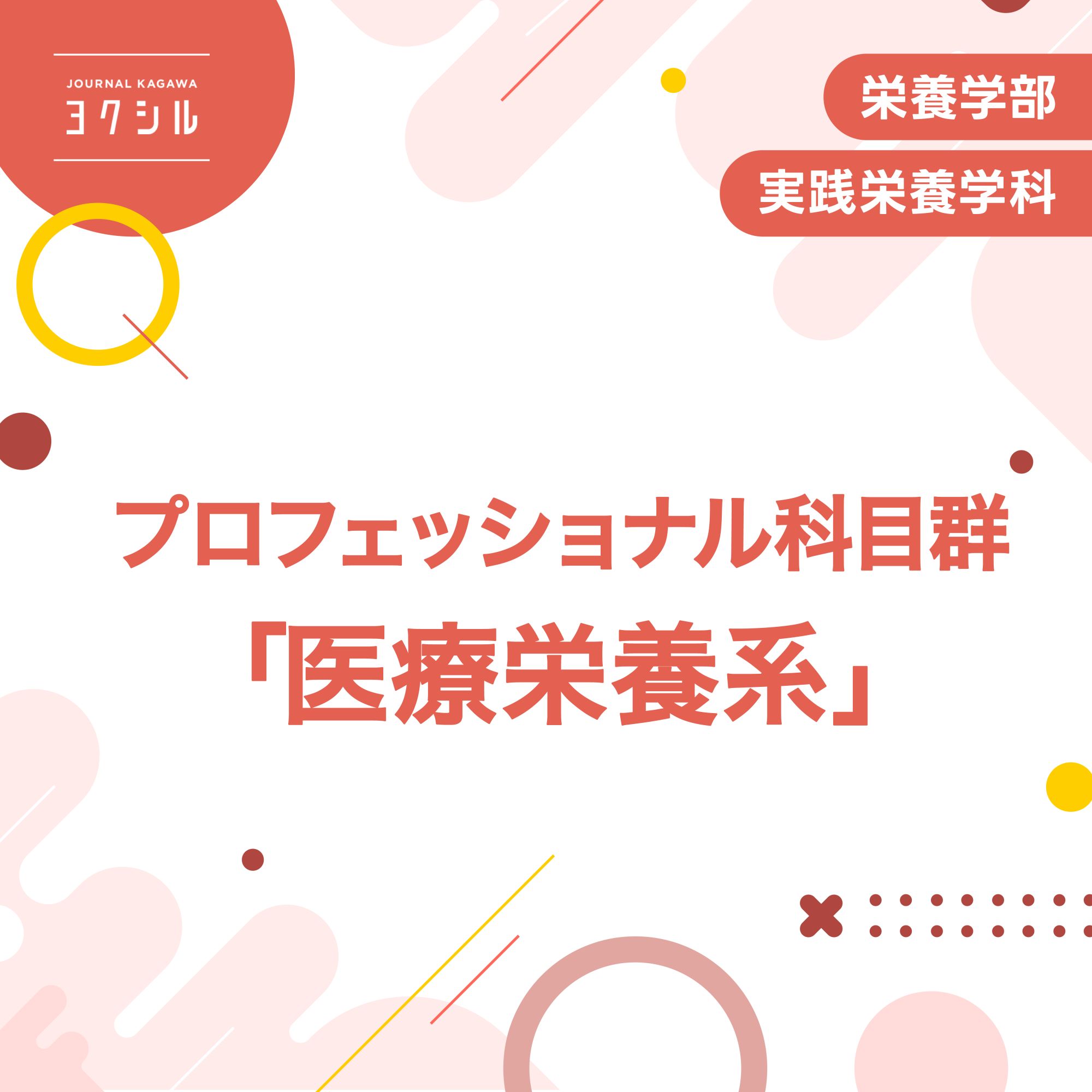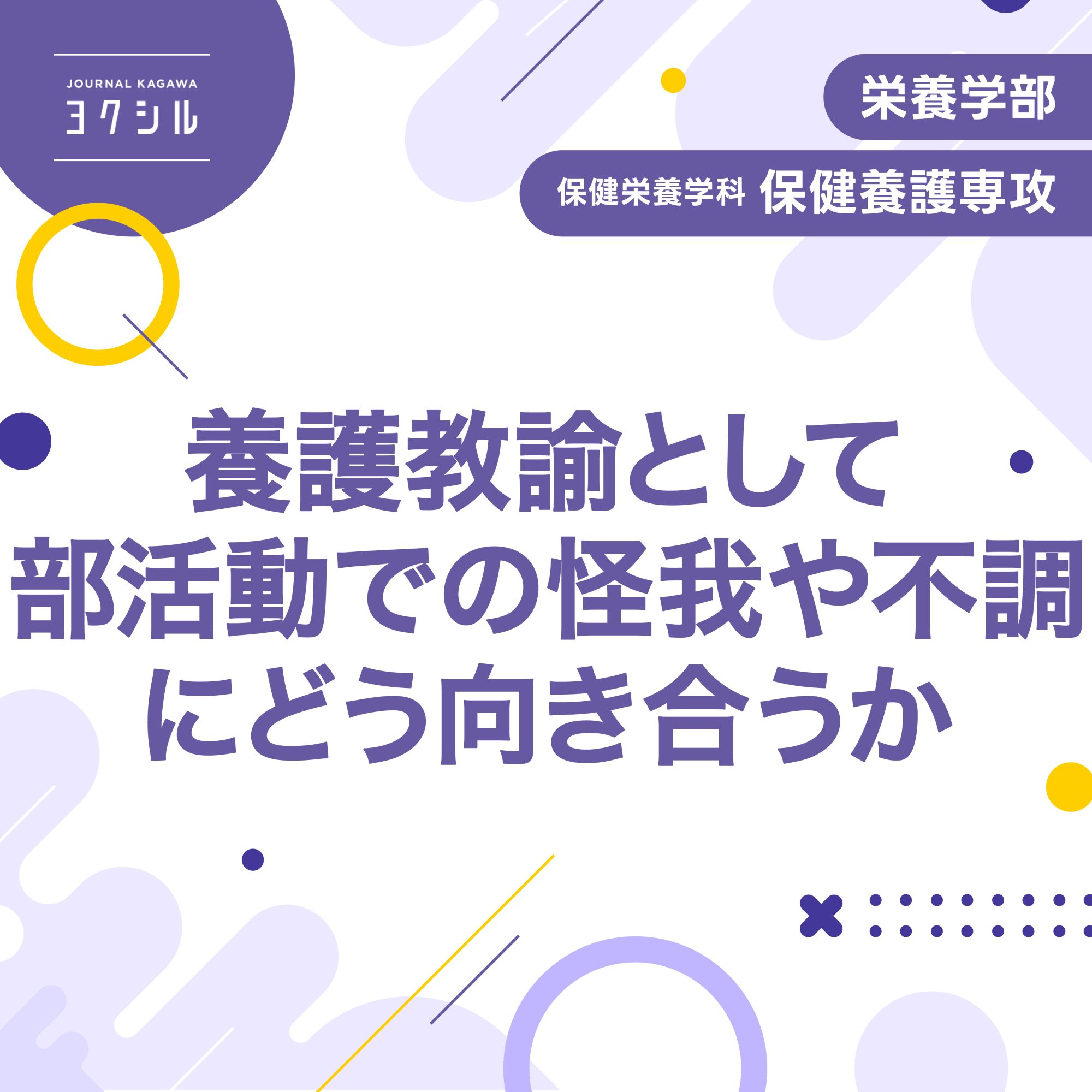日本栄養大学短期大学部のゼミは学生それぞれが興味のある研究室を選び、栄養士として社会の課題を見つけて、指導教員のもとで探求していきます。
短期大学部でゼミを選択する意義と実際のゼミの内容について、調理学研究室の児玉ひろみ先生に伺います。

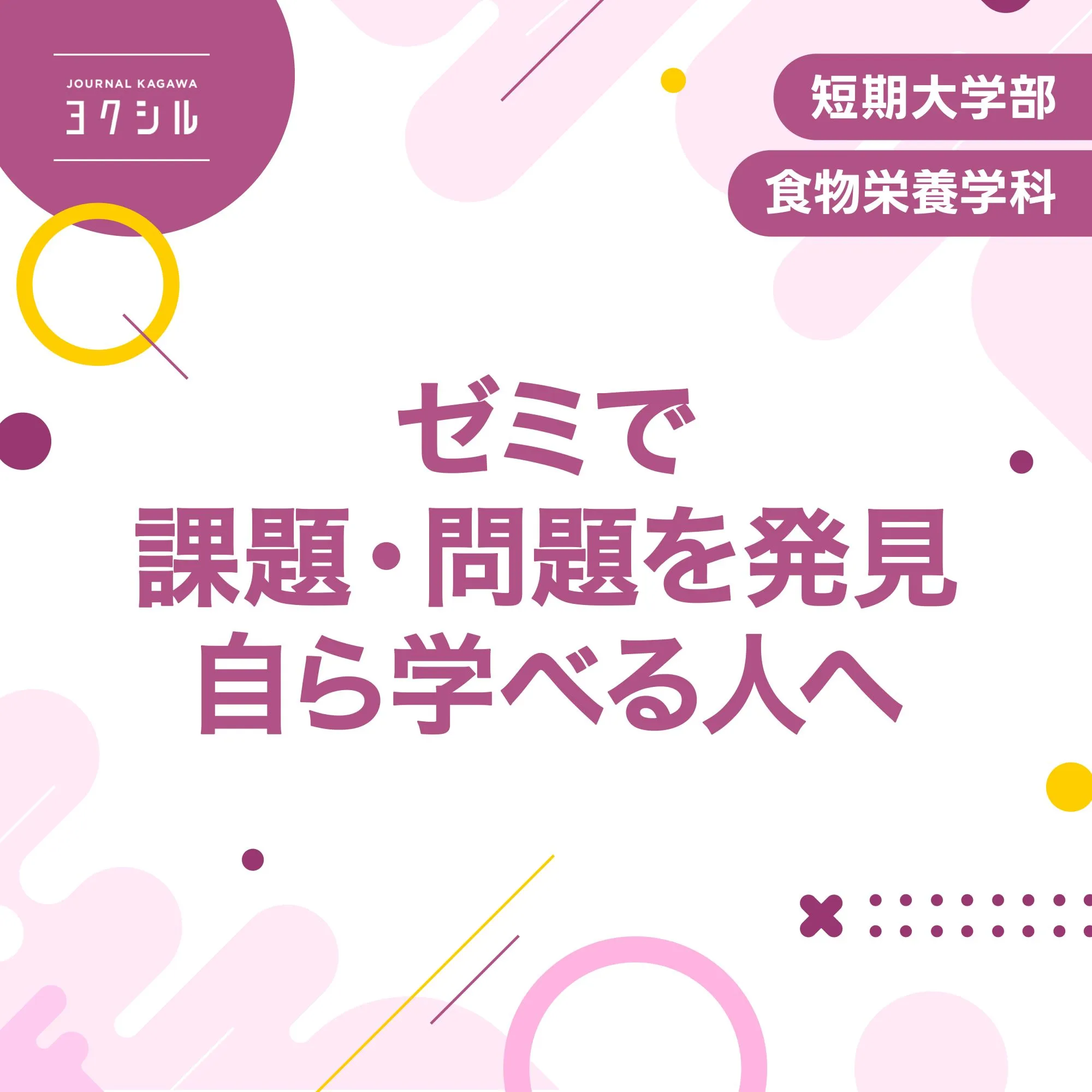
短期大学部
ゼミ/短期大学部/栄養士
ゼミで課題・問題を発見、自ら学べる人へ

日本栄養大学短期大学部の「ゼミ」ってなんだろう。
ゼミが持つ大きな役割は、「自ら学ぶ姿勢」を身につけることです。
短期大学部では2年という短い間に栄養士の資格をとり、社会に出ていかなければなりません。栄養士として社会に出たときに、社会で必要とされている課題に向き合い、自ら考え周囲と協力して答えを探求できるようにする。その基礎を身につけるのがゼミです。
本学では専任教員の人材が豊富で、幅広い分野のゼミを開講できるのが特徴です。食品を用いた実験などを行う食品衛生、食品化学、生理学、生化学や、栄養と健康に関する研究を主とする栄養学、臨床栄養、栄養指導。給食や調理の実習室を主な研究の場とする給食管理、調理学など、研究分野は多岐に渡ります。
ゼミは必ず選択しないといけないわけではありませんが、四大への編入や就職での強みにもなるので選択する人が多く、それぞれが興味あるテーマを選ぶスタイルです。
ゼミではどんな研究をしているのか
研究室ごとにいろいろな研究テーマがあります。例えば食品衛生のゼミでは、食品衛生上の問題について学生自身が調べてテーマを決め、実験しています。外部と連携するゼミもあり、地域の飲食店における健康メニューを考案しているゼミや、ある疾患を持つ子の親子に向けたレシピを考案して一緒に調理しているゼミもあります。
企業とお弁当などを共同開発しているゼミや、料理コンテストに参加しているゼミもあり、今年はキウィを使ったレシピコンテストで最優秀賞を受賞しました。
企業や地域などいろいろな連携先がありますが、目的やニーズを把握してレシピ開発をして、評価を受ける。こうしたことは普段の授業では得られない体験です。自分たちで調べたことをまとめ、人に伝えるプレゼンテーション力やコミュニケーション力も身につき、さまざまな探究を突き詰められるところがゼミの面白いところです。
どんなふうに研究を進めるのか
私が教えている調理学のゼミでは、栄養士として必要な献立作成のための調理力アップを主題としています。図書館での文献検索でレシピを調べ、使用されている食品の概量、調味料の分量から調味パーセントを算出、食品の調理特性を理解した上でおいしく調理できるレシピに改良し、実際に調理して気づいたことをレポートにまとめています。
その他のゼミでも研究室での主な研究テーマに沿って、個人やグループで調べ、教員の指導をふまえて研究計画を立て、実施したことを評価・考察して次に進めることを繰り返して、約1年間のゼミを行っています。
短大でゼミを選び、学ぶことの意義
短大のゼミの成果物は論文という形にはしていないのですが、毎年秋に開催している駒込祭では、研究の成果発表、来場者に向けたデモンストレーションや食事アドバイス、料理教室の開催などをしています。ゼミでの学びを生かした貴重な経験の機会になっています。
ゼミを通して身につく、自ら考え課題に気づき探求する姿勢は、四大に編入する場合にも卒業研究などで学ぶために欠かせないものであり、社会人となってからはさらに重要になります。
学びを深めたいと思うこと。これは一生役に立つことなので、ぜひ興味のある分野を選択して欲しいです。
お話を聞いた先生

▲児玉 ひろみ 先生