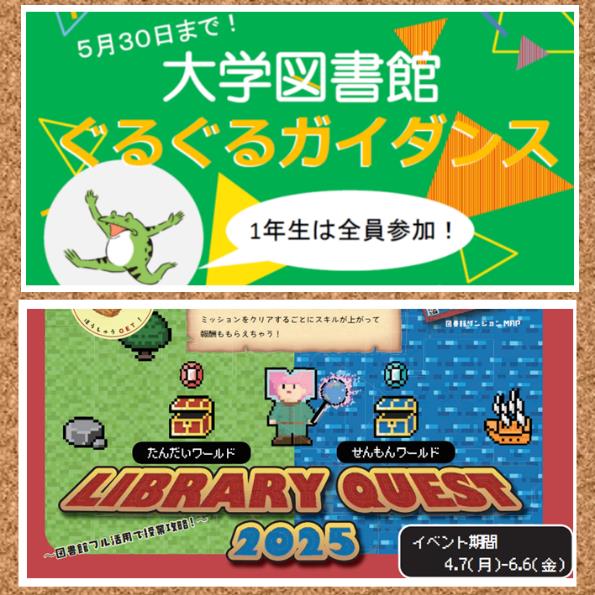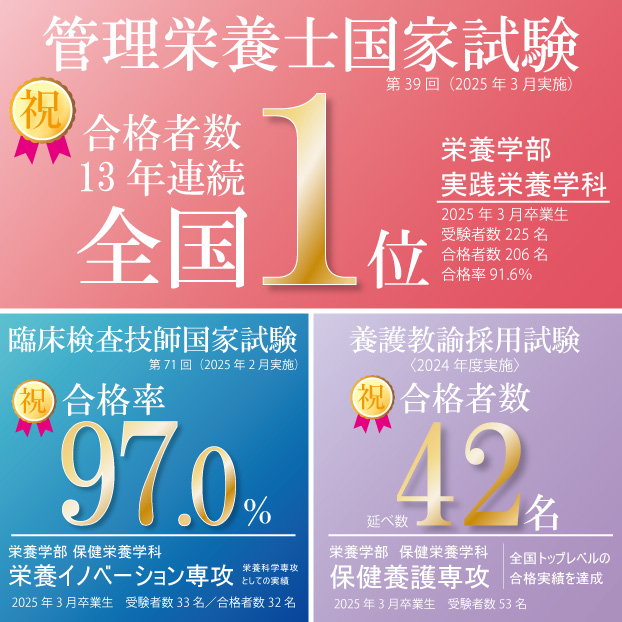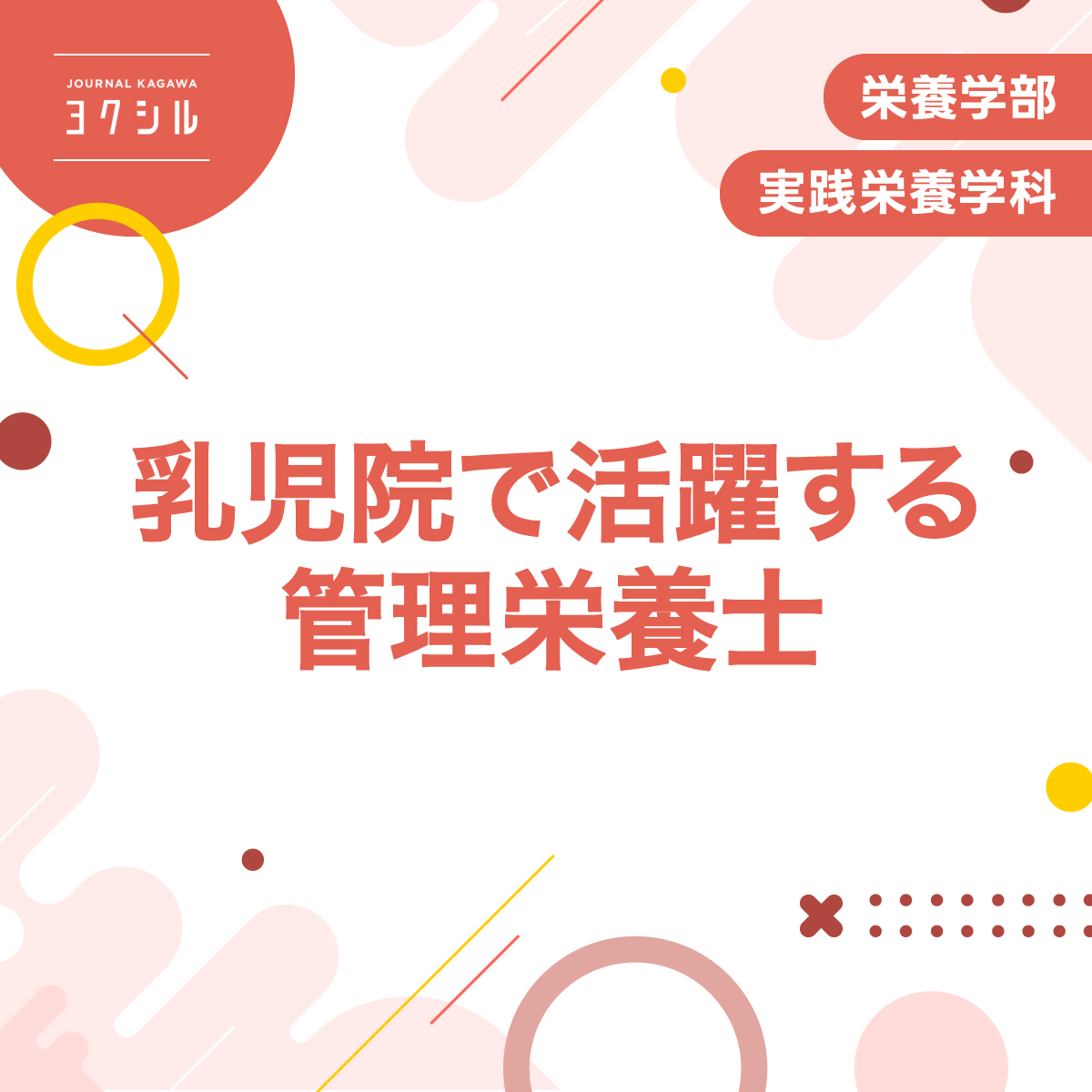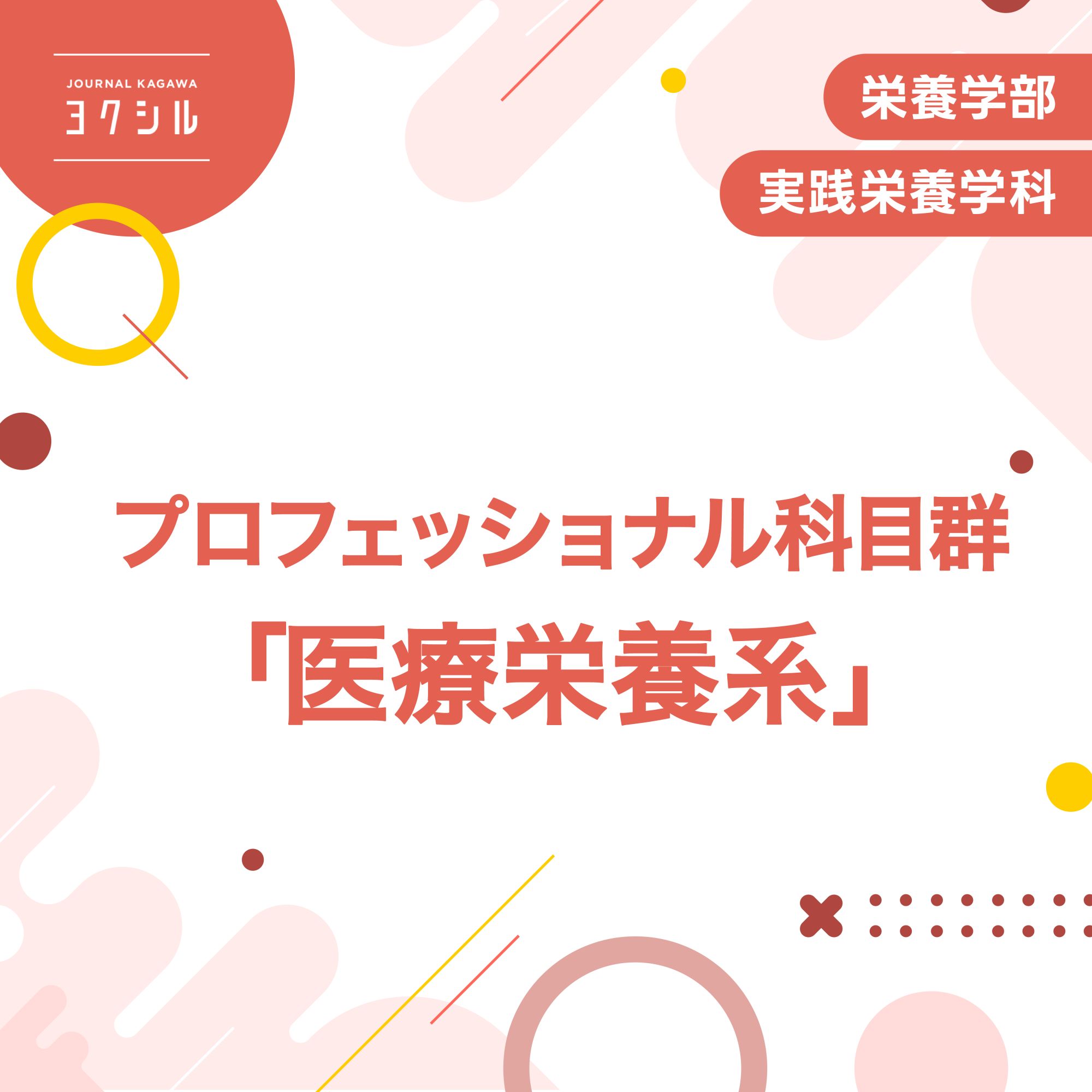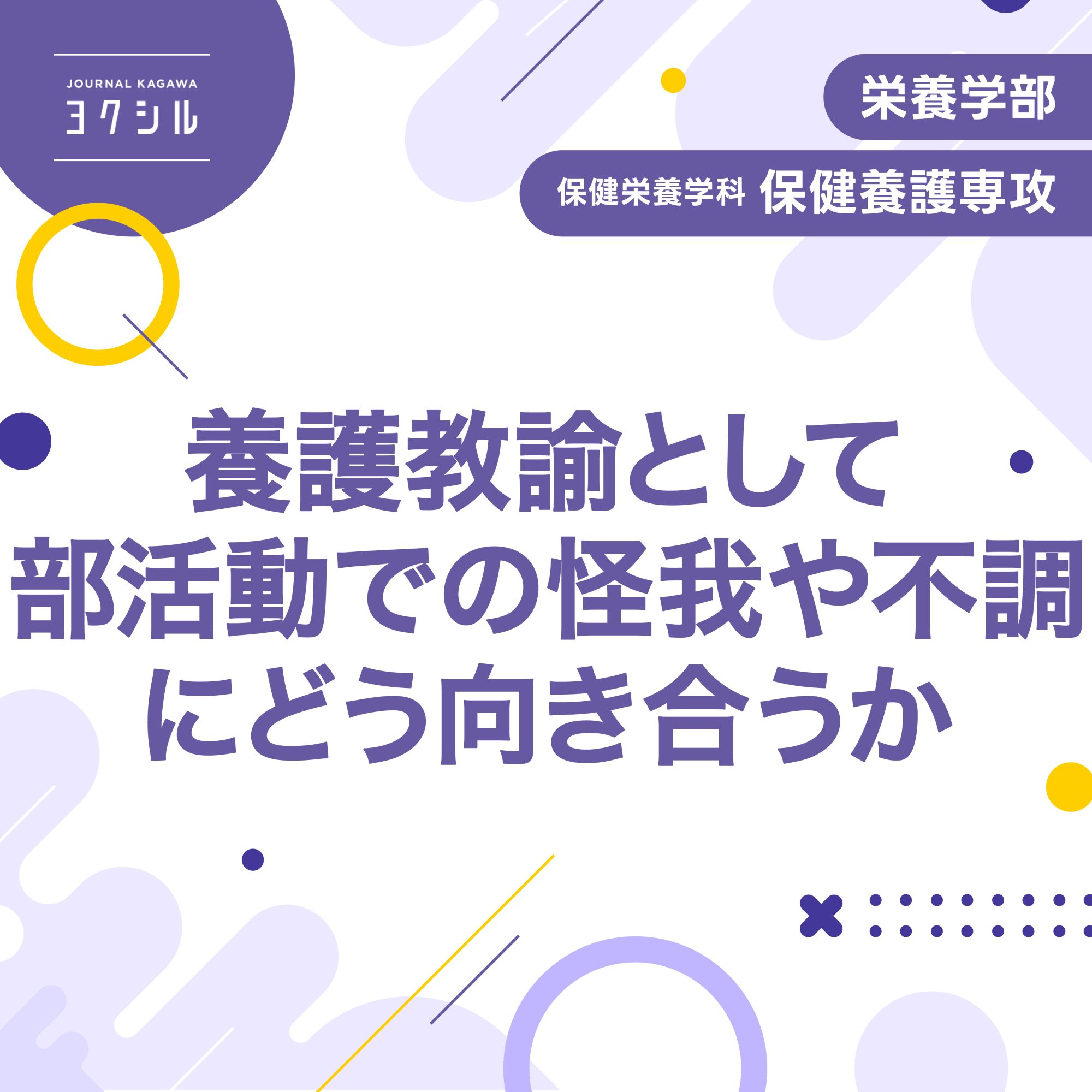食文化栄養学科は学生のクリエイティブ志向が強く、学んだ知識や習得した技術を活かし商品開発や、料理研究家の職に就く人や、学園内留学制度を利用して調理技術や製菓製パンを1年間集中して学んでプロを目指す人もいます。調理の実習時間が本学の学科の中でも一番多いことも特徴の一つです。

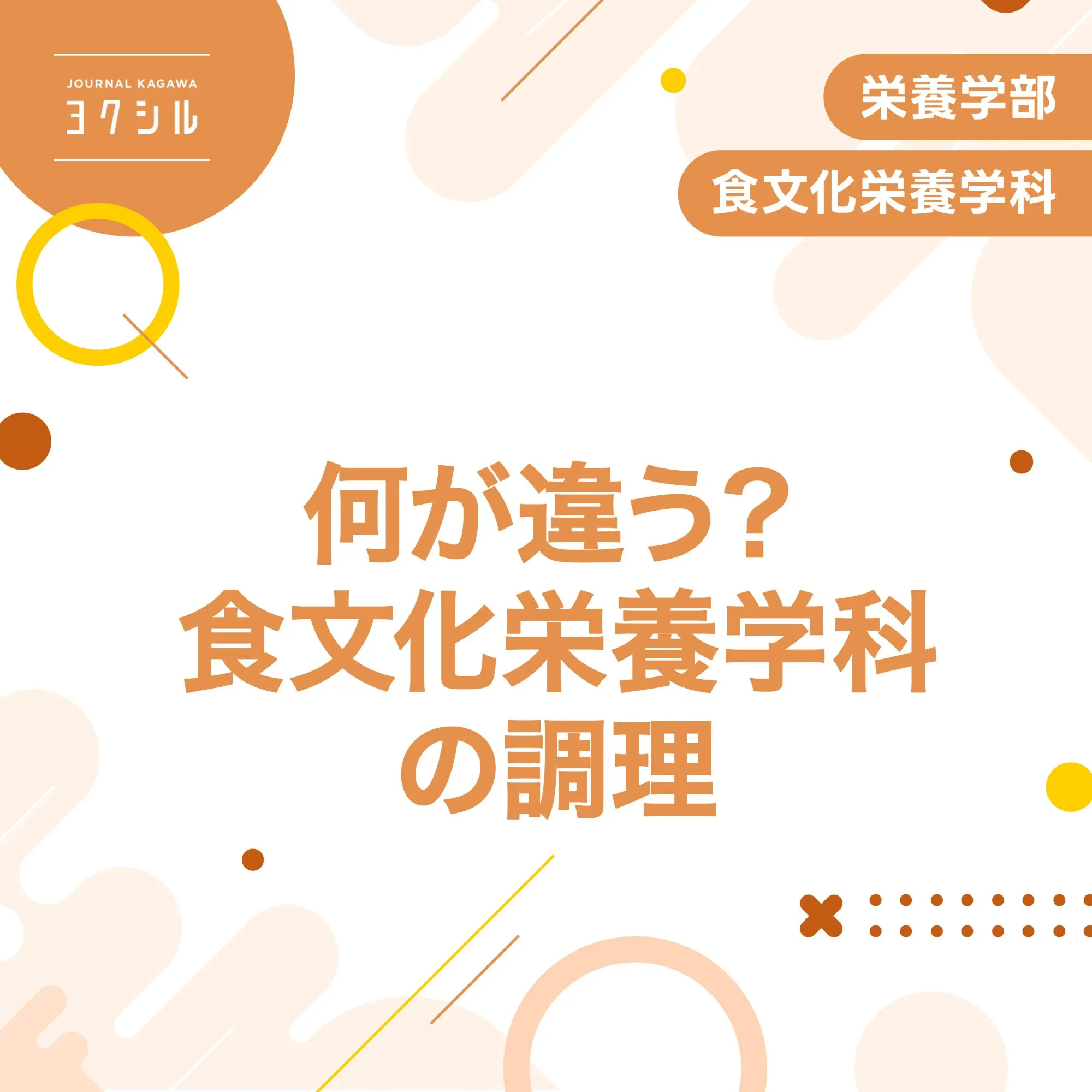
食文化栄養学科
調理技術/食材/旬
何が違う?食文化栄養学科の調理

調理技術はなぜ必要なのか
食文化栄養学科では料理そのものを表現するだけでなく、料理を通じてメッセージを伝えるなど、料理の先で人と人を繋ぐことを想定しています。
そのため、「自分が表現したいと思う料理を、まず自分で再現できる」ということを重視し、「基礎技術や調理理論の裏付けがあり信頼できる料理」を、自分で作ることができる技術を身につけます。
「おいしさ」には正解がない。だから「おいしさ」を自由自在に作り出す
根拠を学ぶ「調理」
料理のレシピは、1つの料理にもたくさんあって、どれが正解とは言い切れません。
食文化栄養学科の調理の授業では、基本的には一般的なレシピを伝えつつ、例えば「時短レシピ」や「高齢者向きのレシピ」、「子供向きのレシピ」のように、作る人や食べる人に合わせてレシピを改変する力を付ける事を重視しています。
例えば、ほうれん草は、根元の下処理をして切らずにお湯で茹でるのが基本ですが、調理する環境や調理技術によっては、切って茹でたり、電子レンジを使うこともあります。ゆで汁に栄養素が流出する、アクが残るなどのデメリットも理解した上で、それ以外のメリットがあるからした、というような根拠を、調理の時間に身につけていきます。
料理の背景を知る「食文化」
もう1つ重要なのが、その料理の背景を知っていることです。
例えば、プリンは、卵や牛乳を使った蒸し菓子ですが、ゼラチンなどのゲル化剤で固めてもプリンの名前がついています。料理は時代とともに変化するものですから間違いではありませんが、本来の意味や由来を知らずに展開していくと、表現や提案の根拠がなくなってしまいます。
文化的背景や根拠を知っていれば、ネーミングひとつでも説明ができるし、調理技術が説得力になる。こうしたプロの育成を目指しています。
食文化栄養学科の調理学と実習
食文化栄養学科の1年で学ぶ調理の科目は、調理学と基礎調理学実習、応用調理学実習、です。
調理学では、基本的な調理の理論に加えて「海外に材料を持って行ってだし汁をとったら、出来上がりがいつもと全然違う。これは水の硬度が影響しているから」というような事例を話します。
1年生の実習では、1年間かけて基本的な調理技術を身につけていき、自分でイメージしたものを作れるようにします。また、後期春には調理学とデザイン・企画の科目をコラボしたフードクリエイション実習という科目も有ります。この実習では、ある条件にあった菓子を企画して作り、その作品のプレゼンテーションを行います。
2年次は日本料理や西洋料理、アジア料理などの各国料理、4年次になると1日通してお菓子とパンを作る製菓製パンの集中授業が1週間あります。これらの実習で活躍する卒業生、例えば卒業後に料理や菓子の研究家として活動をしている方や、シュガークラフトのプロになっている方に講師をしてもらいました。いろいろな働き方や仕事の展開の仕方などの参考にもなるので面白いと思います。これは他学科にはない、この学科の特徴的なところです。
調理学系ゼミは他のゼミとのコラボもたくさんあって、地域振興に展開したり、子供の料理教室でプロジェクションマッピングをしたりしました。
調理技術は調理学系ゼミでしっかり見て、他のゼミでは表現してもらう。他学科にはない学びの横のつながりを意識できるし、技術があるからこその展開できる、ということを体験してもらえると思います。
ゼミの料理教室の意味と意義
料理教室をテーマにしたゼミでは、小学生を対象にした料理教室と40〜80歳の中高年男性を対象とした教室を運営しています。
人に教えることも、調理の根拠や技術を持った上での表現の一つです。普段料理をやらない層の人たちなので毎回工夫が必要ですが、学んだことを人に教える表現として落とし込む作業が、ここで活きています。
この子供向きの料理教室を受けて、数年後に学生として入学してきた人もいます。技術と知識、根拠と説得力の成果かもしれません。共学化したら、そのような男子学生の入学にも期待しています。
お話を聞いた先生

▲奥嶋 佐知子 先生
【キーワード】
調理教育、調理技術、調理方法の検討、初学者教育、教材開発