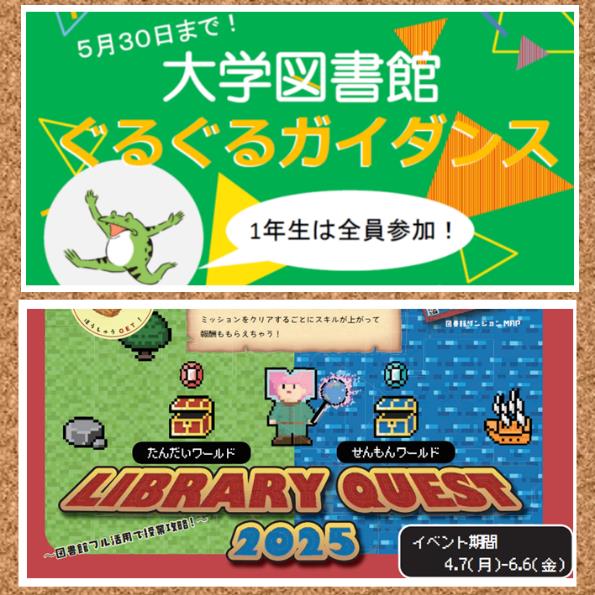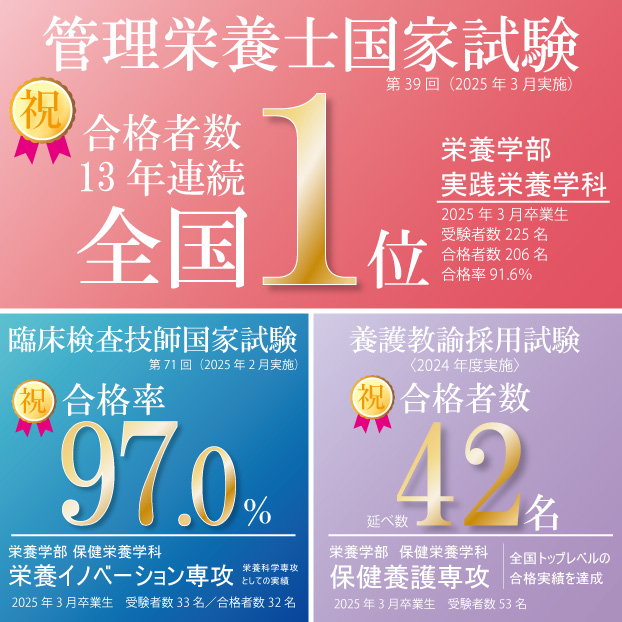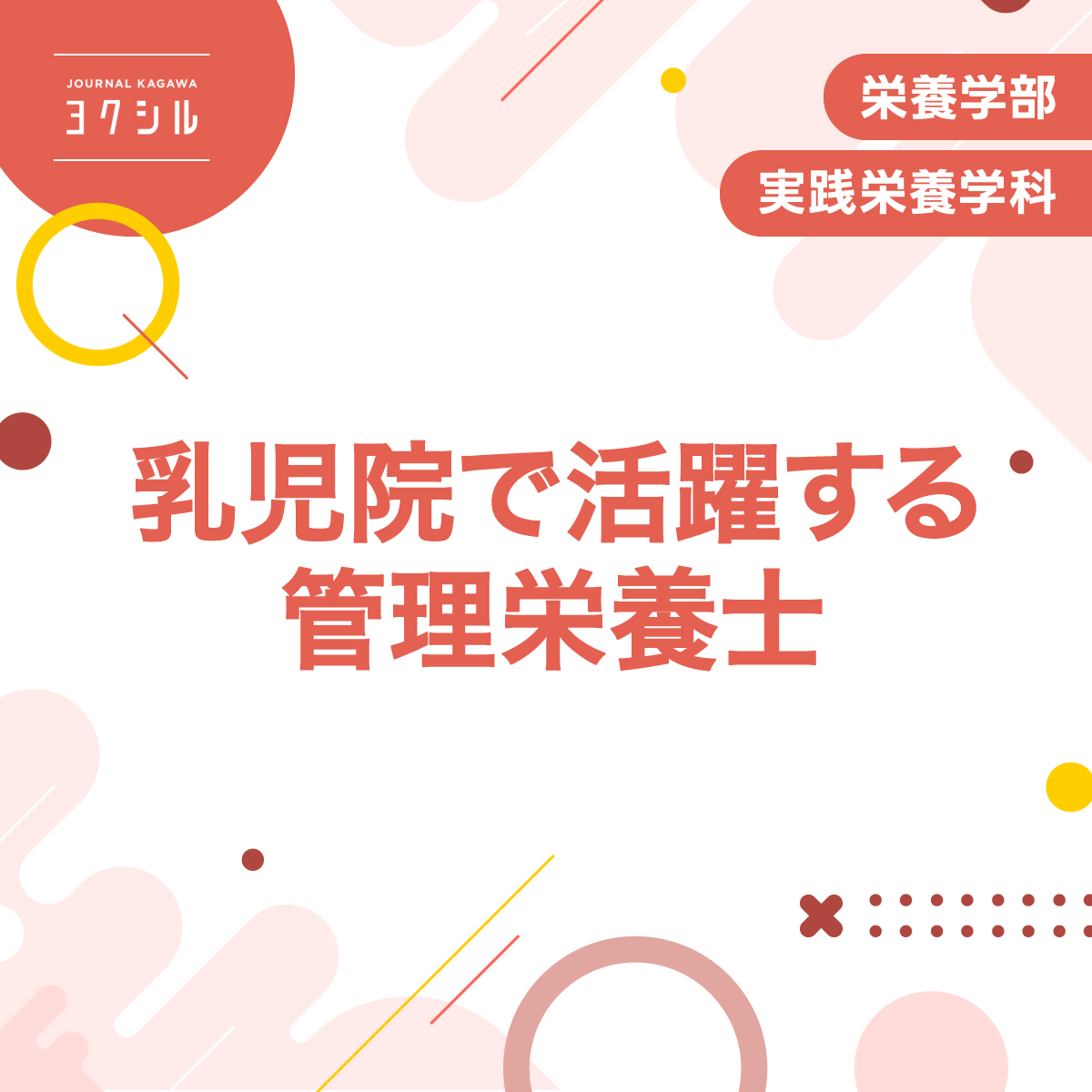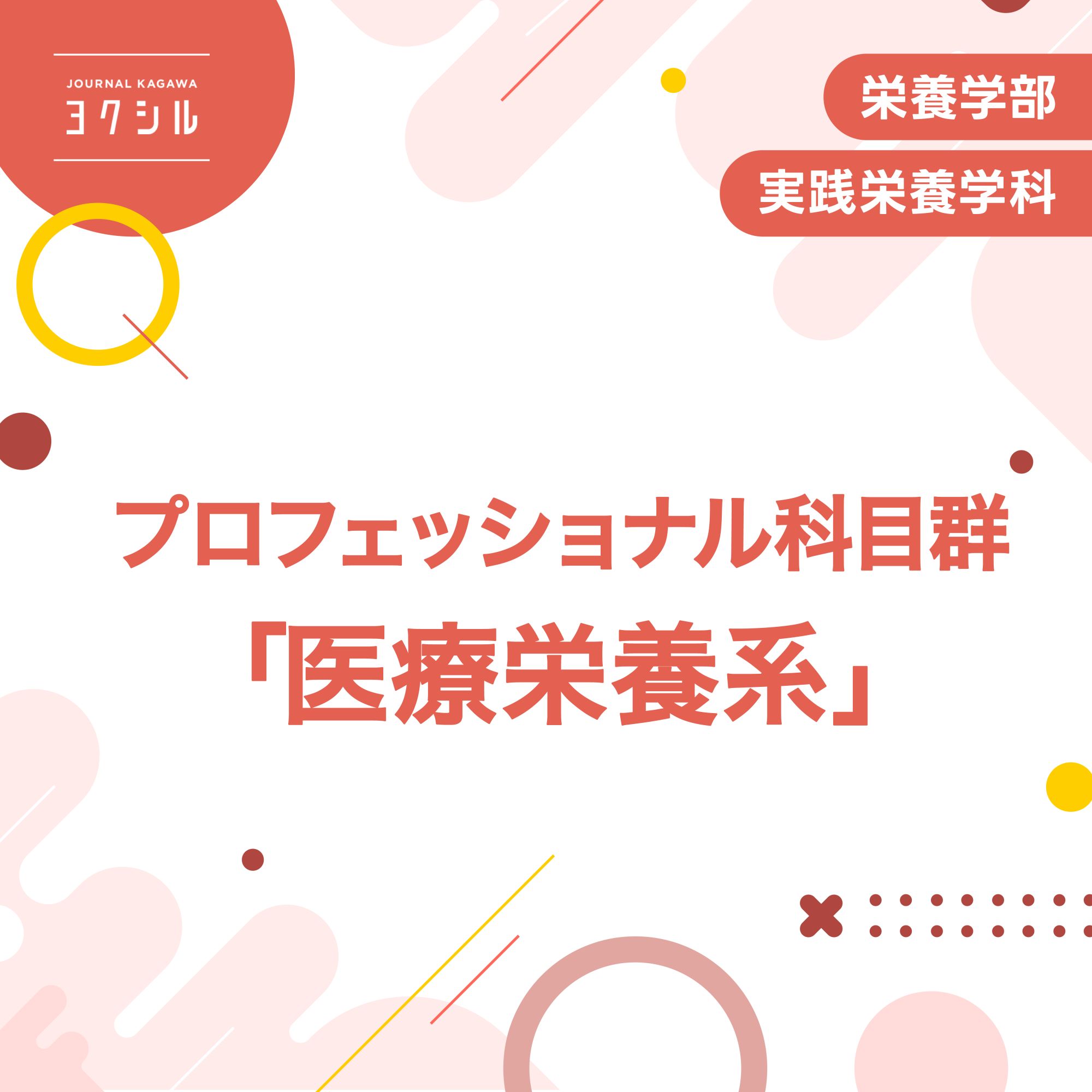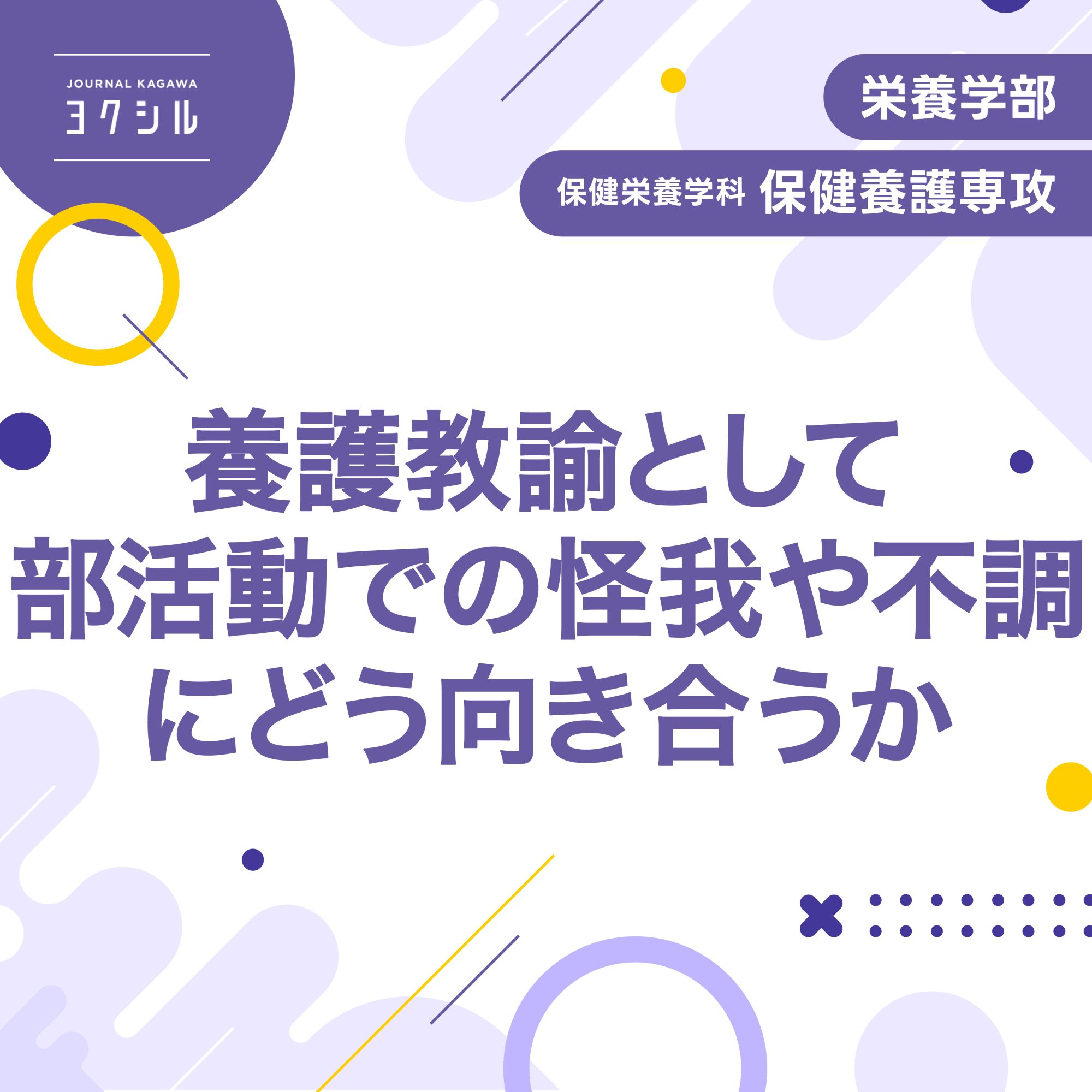食文化栄養学科は本学で唯一、栄養士など特定の資格取得を目的としない学科です。食が持つ文化的背景の知識や表現のスキルで、新しい食の価値や可能性を創造する力を養う学科として開設され、今に至るまでにさまざまな変遷がありました。
共学化を見据え、食文化栄養学科はこれからどう変わるのでしょうか。

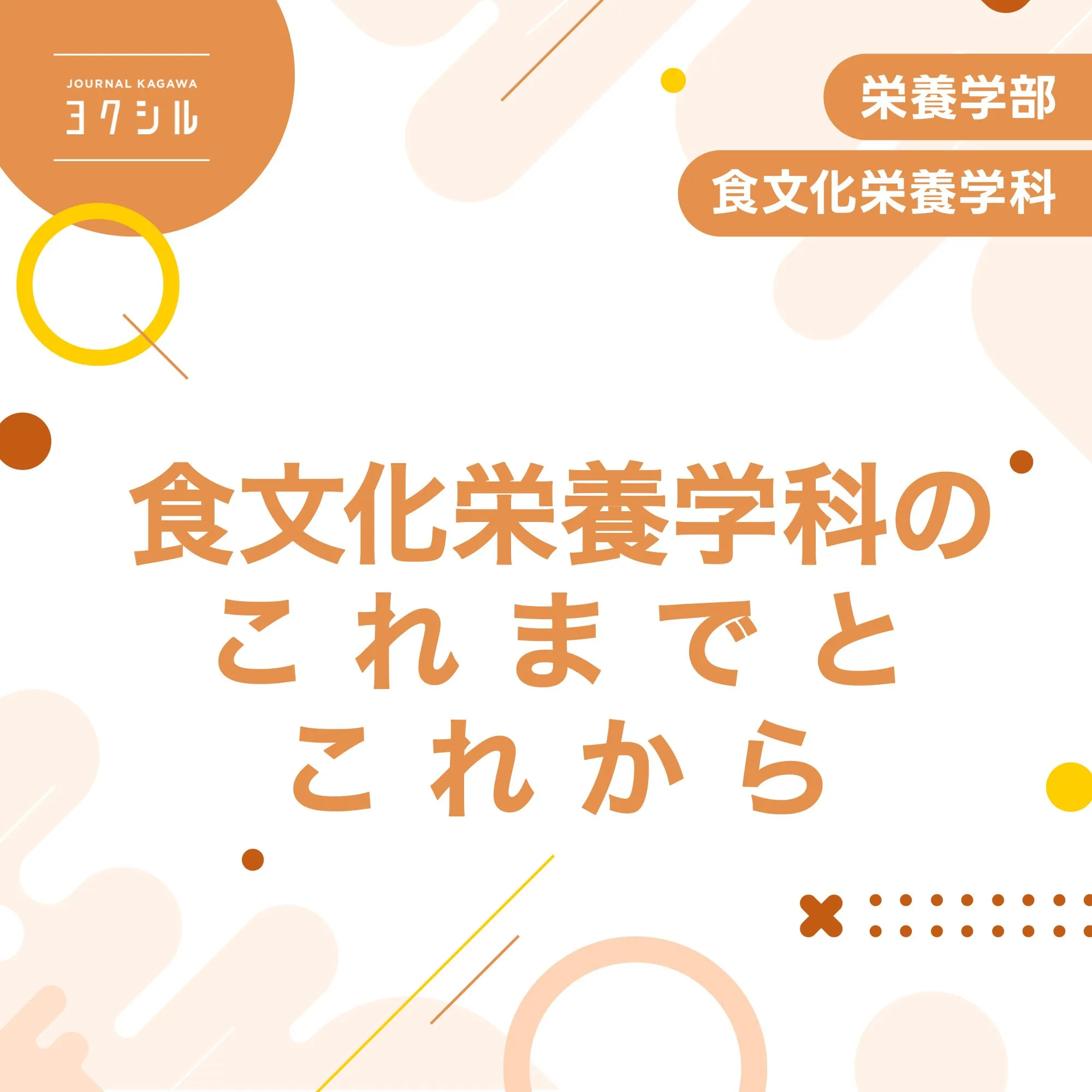
食文化栄養学科
食文化/歴史/新しい価値
食文化栄養学科のこれまでとこれから

開設の想い「私たちは、文化的要素で食べている」
本学の創立者である香川綾先生は、「私たちは栄養素を食べて生きているのではなく、食事や料理、地域や郷土料理などを全て取り入れた文化的な要素で私たちは食べて生きている」と唱え、栄養学、保健栄養学に「文化」を取り入れるためには、広い食の分野を自由に学び研究できるもう一つ学科が必要だと考えていました。
1993年4月、食文化栄養学科の前身である「文化栄養学科」は、実践栄養学科と保健栄養学科と並ぶ学科として、「文化としての食や食の文化性について、栄養との関わりで体系的に学び、その成果を多様な人間社会に、豊かな表現力をもって実践できる食文化表現の専門家を育てること」を目的に開設されました。
食文化栄養学科の変遷
第一世代(1993年〜)「文化栄養学科」時代
日本で唯一の「文化栄養学科」として開設されました。初代学科長の足立己幸先生をはじめ、初期の頃は学生にも教員にもユニークな人が集まりました。文化学、動物人間学、食情報学等の重鎮の教授陣や、後に小説家として有名になった助手の方やユーモアあふれる助手の方々が学科運営に加わり、学生も他大学を卒業してから入学する人や栄養士として働いていた社会人が編入学してくるなどさまざまでした。
カリキュラムは、栄養学を広く深い「学問の森」になぞらえて、「文化栄養学」の木々を育て、森全体を多様で豊かにするために、人間科学分野、食物科学分野、食生態学分野、文化論分野、栄養科学分野、国際文化表現論分野、情報論分野、総合講座・実習などで構成されました。
第二世代(2006年頃〜)学ぶフィールドをより明確に「食文化栄養学科」へ
学科名称を「食文化栄養学科」に変更し、「食のスペシャリスト」を育成するということを明確にしました。
料理表現や調理技術により重点を置いたカリキュラムになり、栄養学をはじめ、日本や世界各地の食文化、食コーディネート、食ビジネス、映像表現法などについて幅広く自由に学ぶとともに、情報発信のノウハウやスキル、具体的な課題についての企画力・表現力など、実社会で役立つ知識と技術が修得できる構成となりました。
食を技術で表現できることに力を入れ、1年間の学園内留学制度で製菓科や調理師科で学べるようにしたのもこの頃です。身につけるスキルも具体的になり、所定の科目を履修・単位修得することでフードコーディネーター3級を取得できるようになり、必修科目・選択科目も変化しました。
学問的・実践的な学びの構造をより明確化し、自身の専門性を深められるように、3年次からコース制が導入されました。「食の社会文化」、「食のビジネス」、「食の表現」、「食の国際」、「調理・製菓プロフェッショナル」の5つのコースとコースコア科目を作り、いずれか一つのコースに所属しますが、ある程度の自由度を残しながらも筋道のある選択ができて、かつ体系的に学べるようにしていきました。
学内発表のプレゼンテーションがパワーポイントでの「口頭発表」になり、段ボールパネルを使用した「展示前発表」など、見せ方が洗練され、学生による要旨集装丁のデザイン性も増し、発表会の進行も工夫を凝らしたものなっていきました。
第三世代(2024年〜)|新しいテクノロジーも取り入れ、アナログな体験的な学びを
女子栄養大学は2026年に「日本栄養大学」として共学化へと生まれ変わります。それに伴い、カリキュラムも新しい内容を策定中です。
パソコンやタブレットが当たり前になり、全ての人がクリエーターであり発信者になれる時代。スマホの普及で個人が動画を作ったりSNSにあげたりするのも日常的なことになりました。
幅広く自由に学べる食文化栄養学科は新しいテクノロジーを取り入れやすい環境です。
ARやAIを使った卒業研究もあり、デジタル技術を用いた食の体験をデザインし社会的課題に挑戦するなど、学生が希望すればさまざまなことにチャレンジできるので、どんどん新しいものを手にして欲しいです。
これからの食文化栄養学科で学べることとは
学科創設時より、4年間の学びの集大成の必修科目として「食文化栄養学実習(卒業研究)」は学科の卒業必修コア科目です。3年次後期から4年次の1年半をかけて、各自のテーマに沿って、じっくり取り組めます。
アナログな「食べること」の根本は変わりませんが、デジタル技術や最新のツールを合わせた新しいコトに期待しています。世の中は日々刻々と変化していきますが、変わるものと、変わらないものをしっかりと見極め、食文化栄養学科で培う創造性で新しい表現を模索していきましょう。
お話を聞いた先生

▲藤倉 純子 先生
【キーワード】
ICT活用の食育、プログラミング、データベース、情報処理