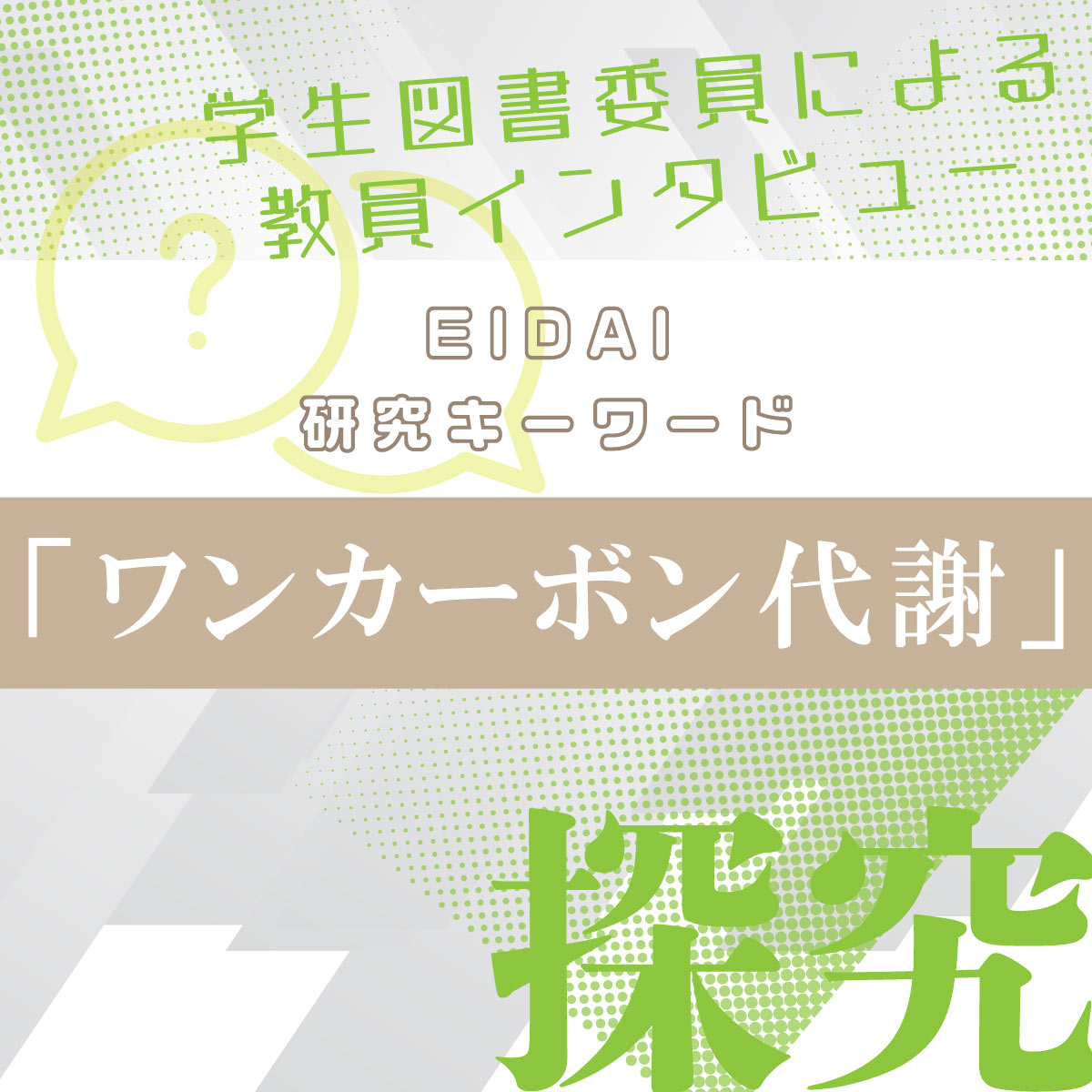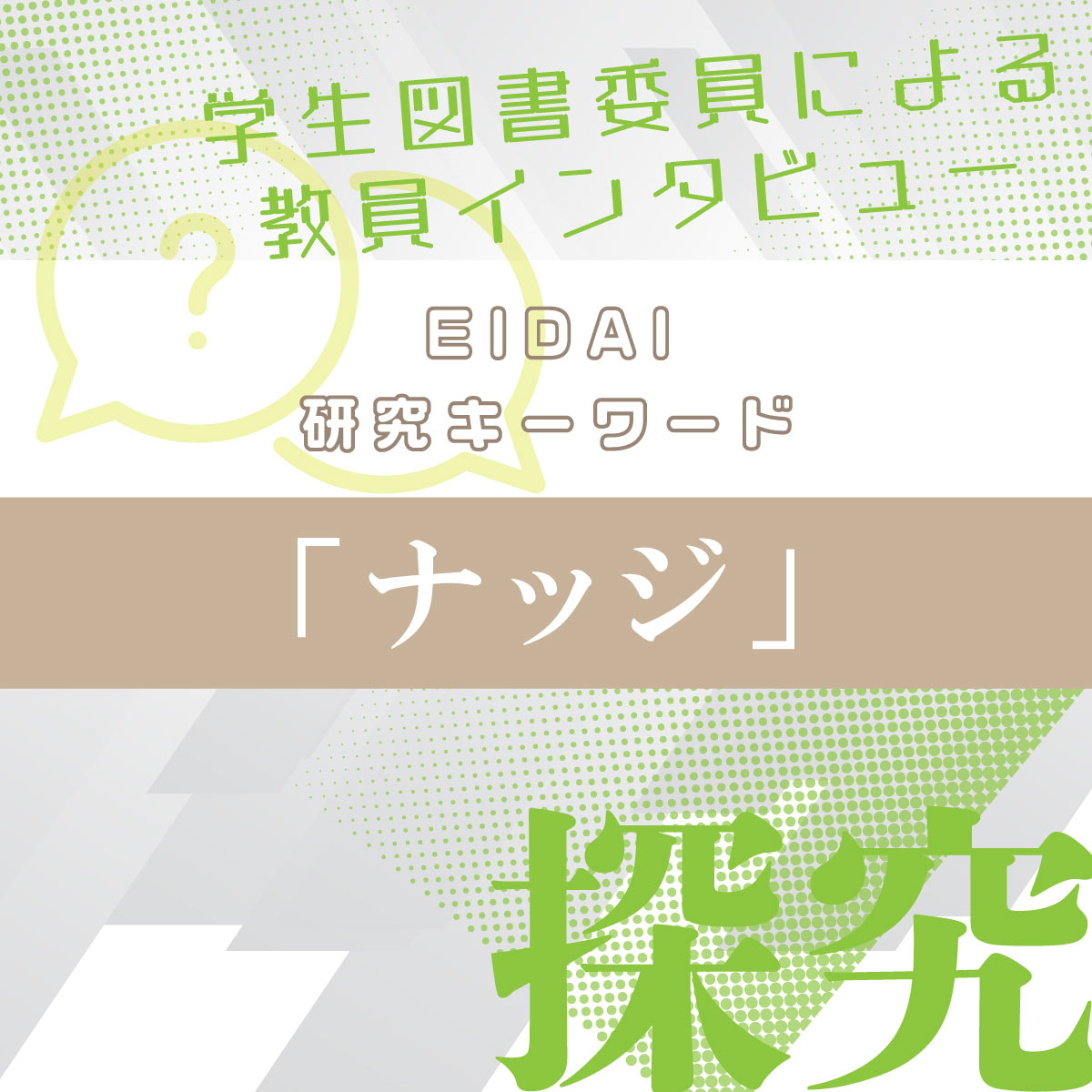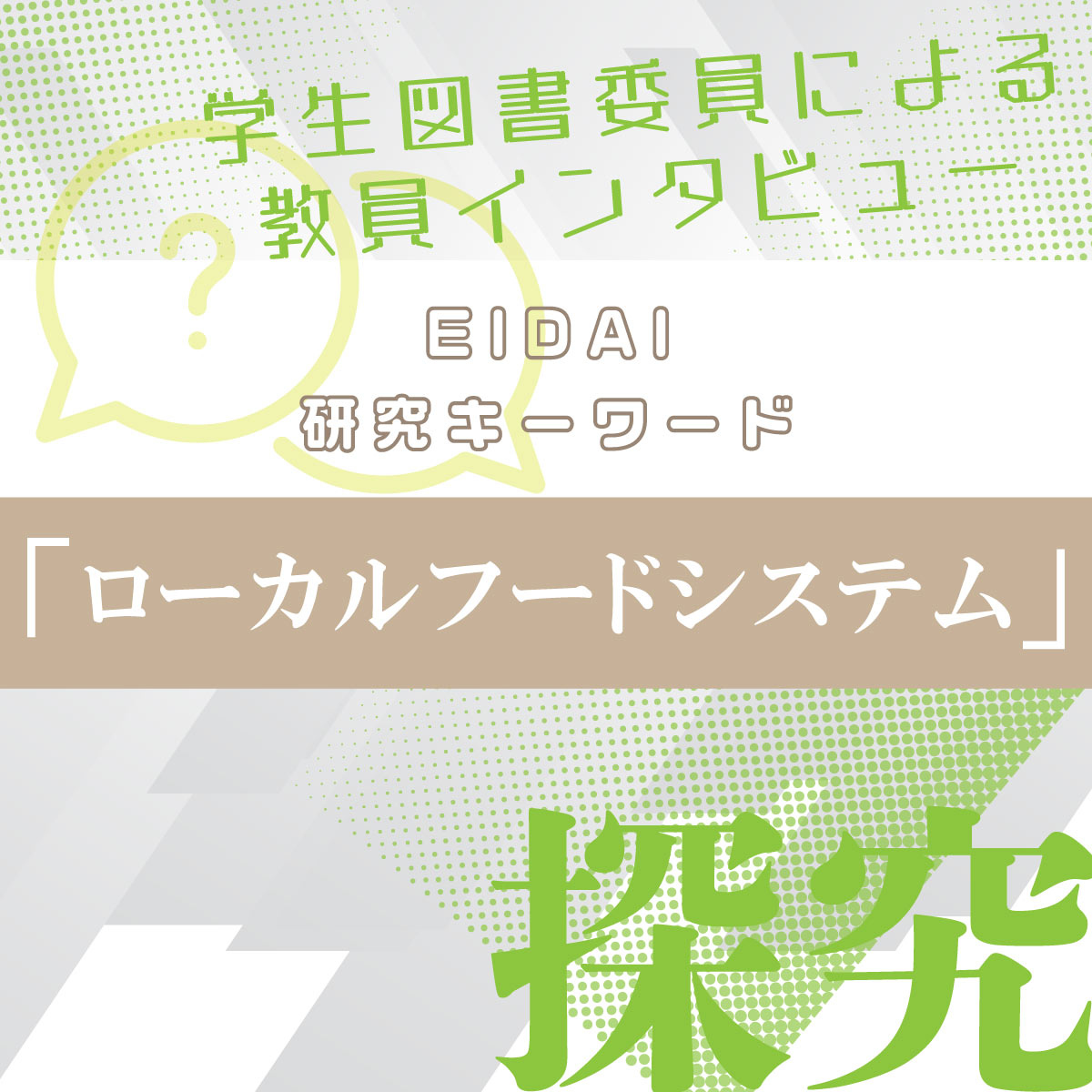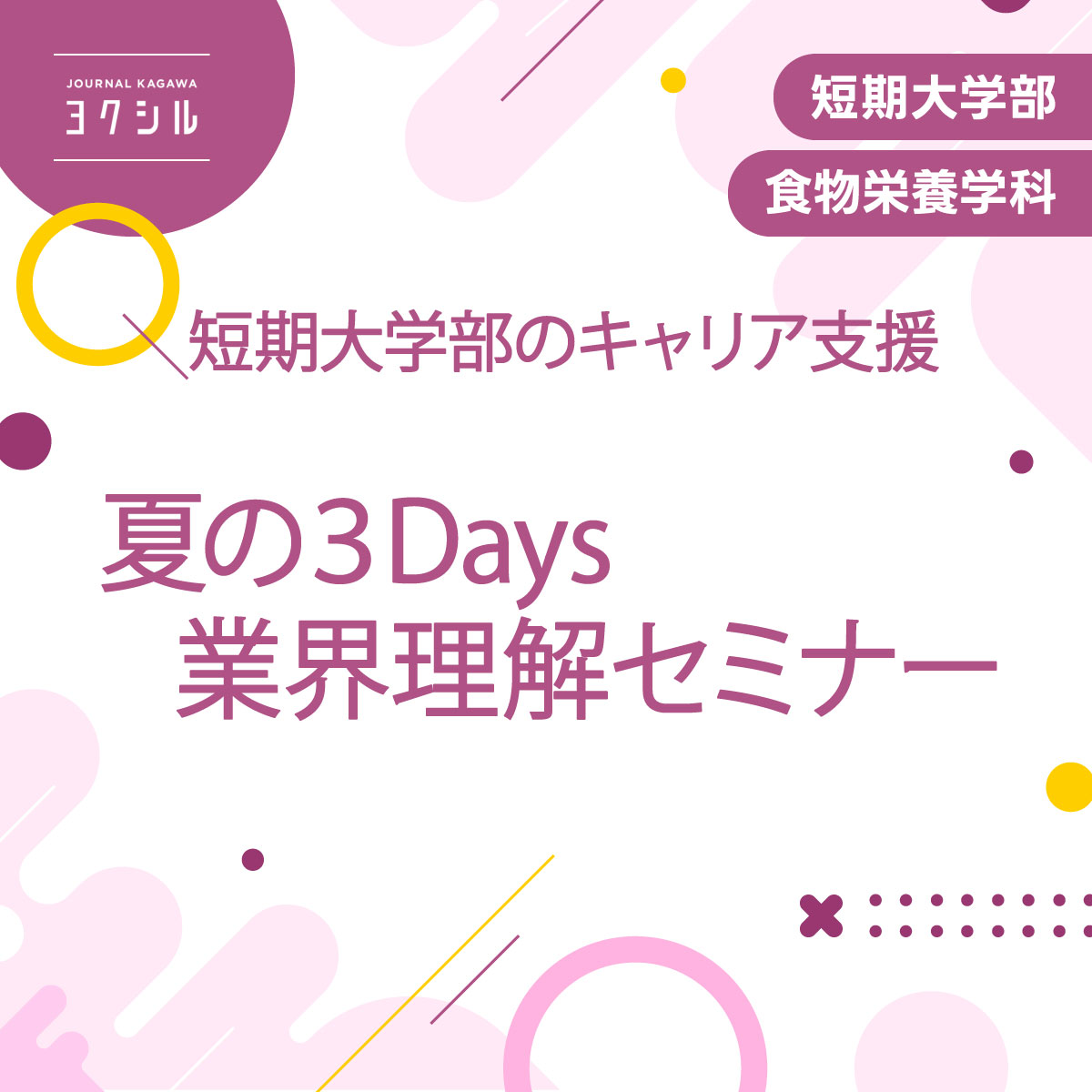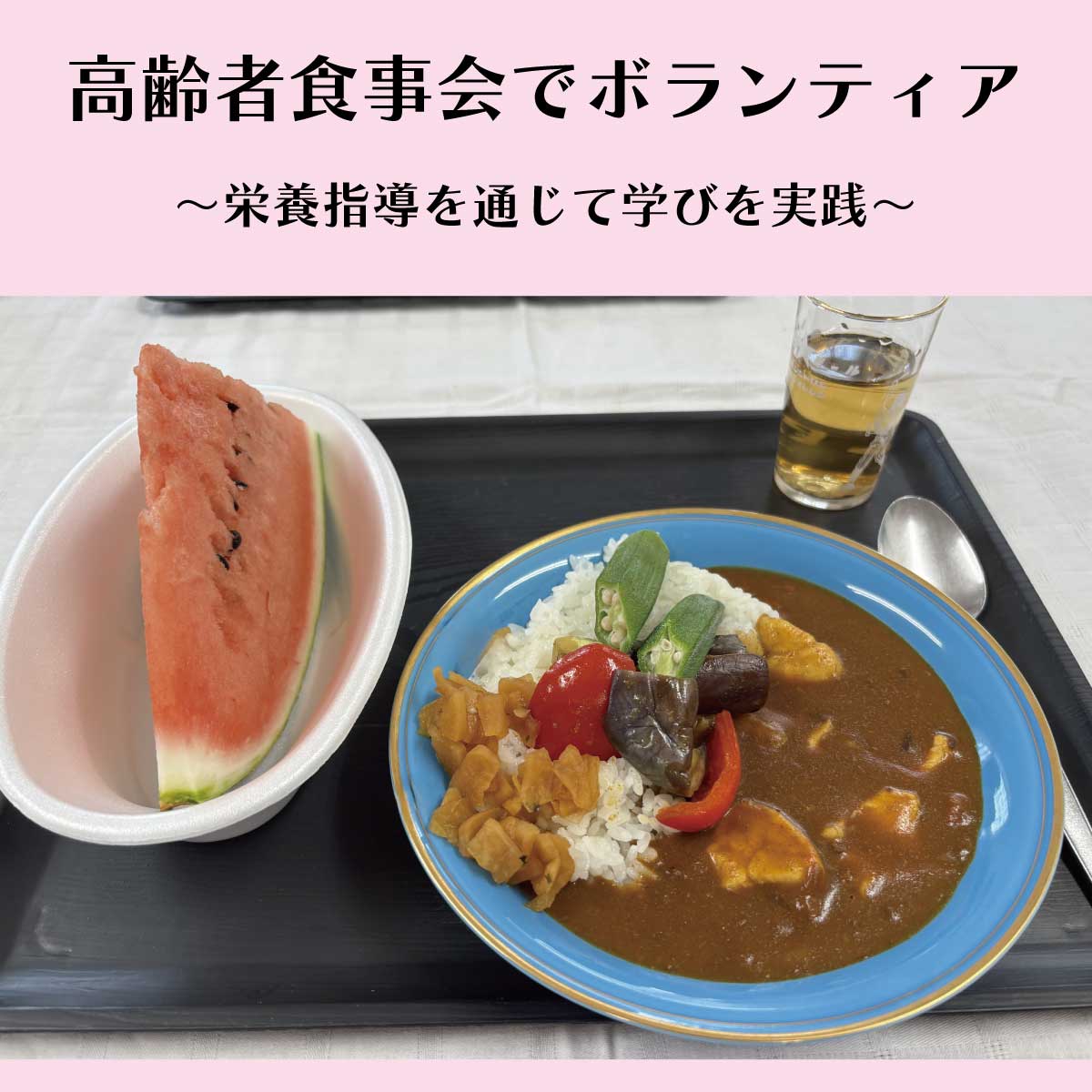学校の部活動に起因する怪我や体調不良には、部活動の顧問だけではなく養護教諭も連携して対応します。保健養護専攻では、解剖生理学などの人体に関する基礎知識から、応急手当や初期対応等に関する専門科目、卒業研究を学び、子どもたちの心と体を守るための知識と実践力を深めます。

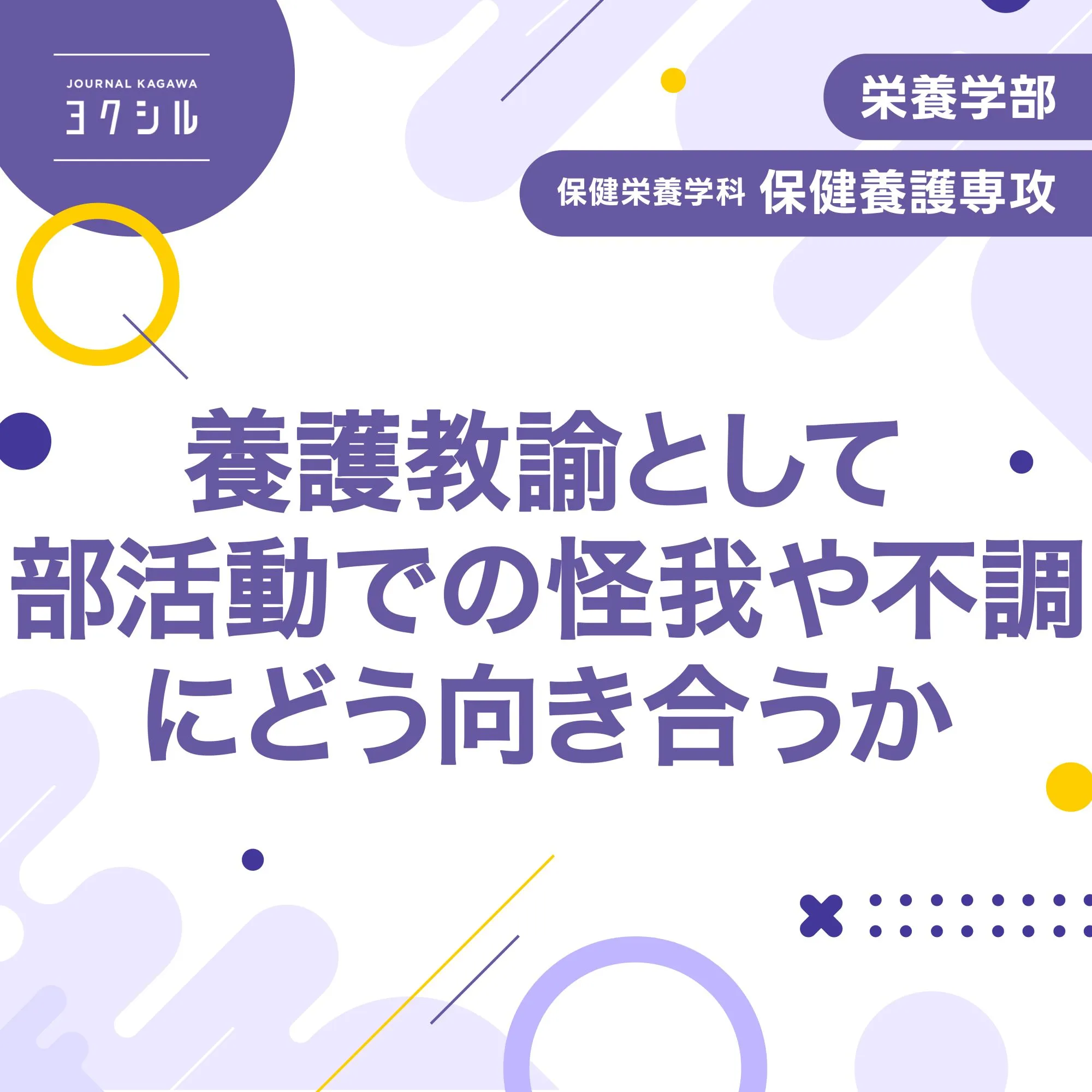
保健養護専攻
部活動/養護教諭/怪我予防/三主徴
養護教諭として、部活動での怪我や不調にどう向き合うか

部活動でおきる怪我と体の不調
部活動でおきる怪我や不調は、練習や競技途中の外傷、練習のし過ぎなどによるスポーツ障害、貧血などがあります。また近年は夏の熱中症の対策も必要ですし、女性にみられる三主徴(エネルギー不足、無月経、骨粗鬆症)は、将来に関わる問題です。
こうした部活動に関わる体への影響を未然に防ぐための保健指導、起きてしまった時の初期対応や、必要に応じて回復期の相談にのり、ケアをするのも養護教諭の役割です。
学校の部活動は生徒が自発的に参加する、教育課程外の活動ですが、多くは教員が顧問として指導にあたっています。ただ、運動部であっても体育を専門とする教諭が顧問になるとは限りません。子どもたちの安全な活動に向けて、養護教諭が学校全体の中心となって健康教育を進めていくことが望まれます。
養護教諭に必要な知識と経験で、実践力をつける
保健養護専攻では、1年次と3年次に健康スポーツ科学演習(生涯スポーツ演習)で「体を動かしながら心身の健康を維持すること」や「健康教育の指導」について学びます。「健康教育の指導」では、「怪我を防ぐ」「安全に活動を行う」「回復するために必要なこと」など学校現場でのスポーツ活動時における具体的かつ実践的に役立つ知識と指導方法などを身につけていきます。
4年次の卒業研究では、テーマを決めて高校の運動部や地域のスポーツ団体を対象に調査と研究を行い、スポーツ安全に関する実態や、効果的な指導についてまとめます。近年はスポーツ障害、熱中症、三主徴などをテーマにした卒業研究があり調査研究を行うだけでなく、子どもたちへの指導教材も作成し、実際の指導にも活用できるようにしています。
保健養護専攻 には、自分が高校生の時に部活動で怪我や体調を崩した経験から、養護教諭になって子どもたちに健康な体でスポーツ活動を行うための指導をしたいといった志をもっている学生もいます。
養護教諭になった時には、一人ひとりに合わせて支援する大変さもありますが、目標に向かって自分を高めていく生徒たちに寄り添いながら卒業を見届け、またその後の成長を楽しみにできるのも、仕事の大きな喜びのひとつでしょう。
食と栄養を強みに、学校全体の健康を守る
日本栄養大学の養護教諭の強みは、4年間の講義や実習で、食と栄養についての専門知識を学ぶことです。
例えば、熱中症や貧血、三主徴の予防と対策には、正しい食生活を送ることが重要です。スポーツ活動時の適切な水分補給、怪我や体調不良の回復に役立つ食事、運動量に応じた食事摂取の必要性など、食と栄養は大きく関わってきます。
学校現場では、これらを保健体育科教員と協力しながらチームティーチングで保健科の授業を行ったり、必要に応じて保健指導を行ったりしながら生徒に伝えます。本学で学ぶ強みを活かし、学校全体の健康を支えられる養護教諭を目指しましょう。
お話を聞いた先生

▲鞠子 佳香 先生
【キーワード】
学習評価法、からだづくり運動