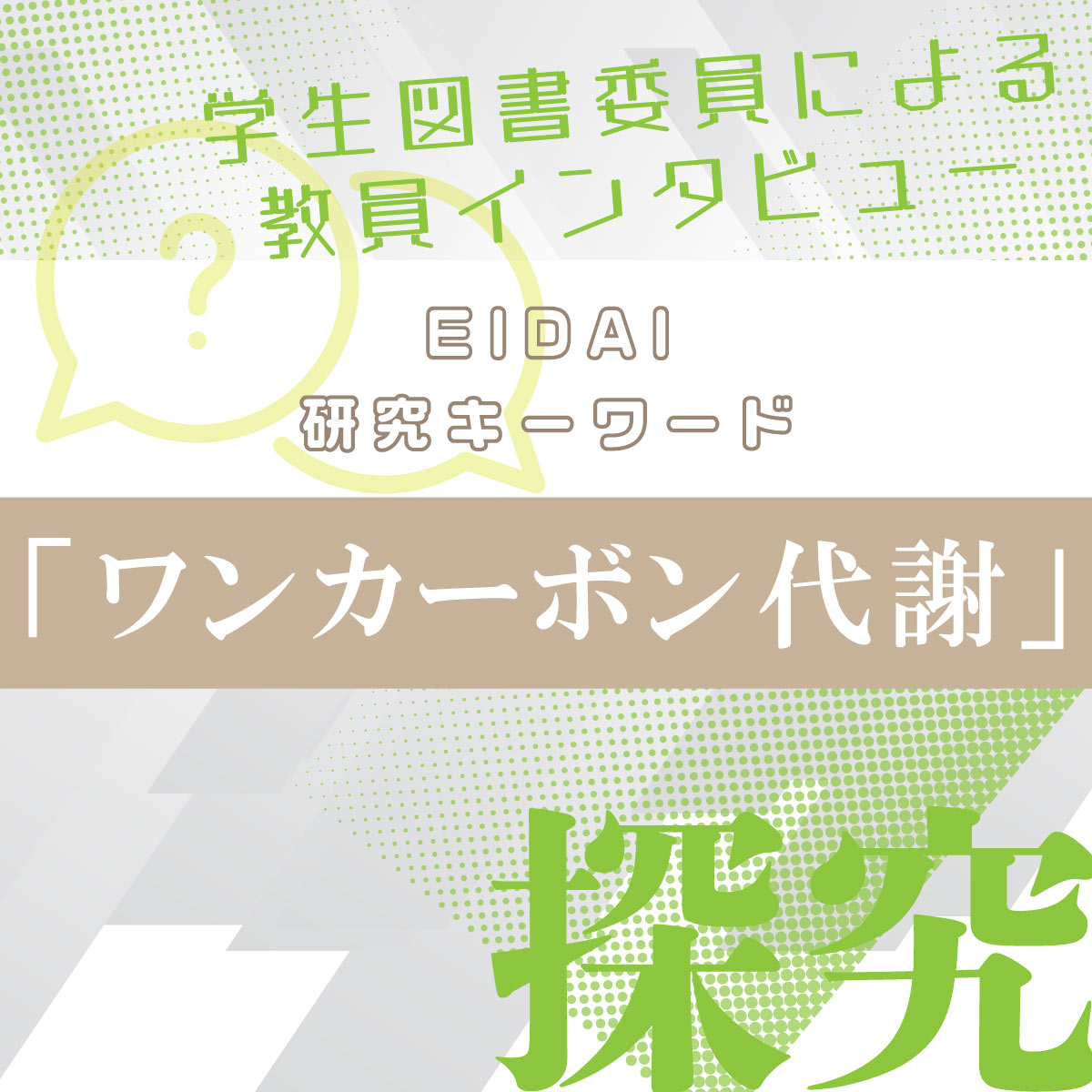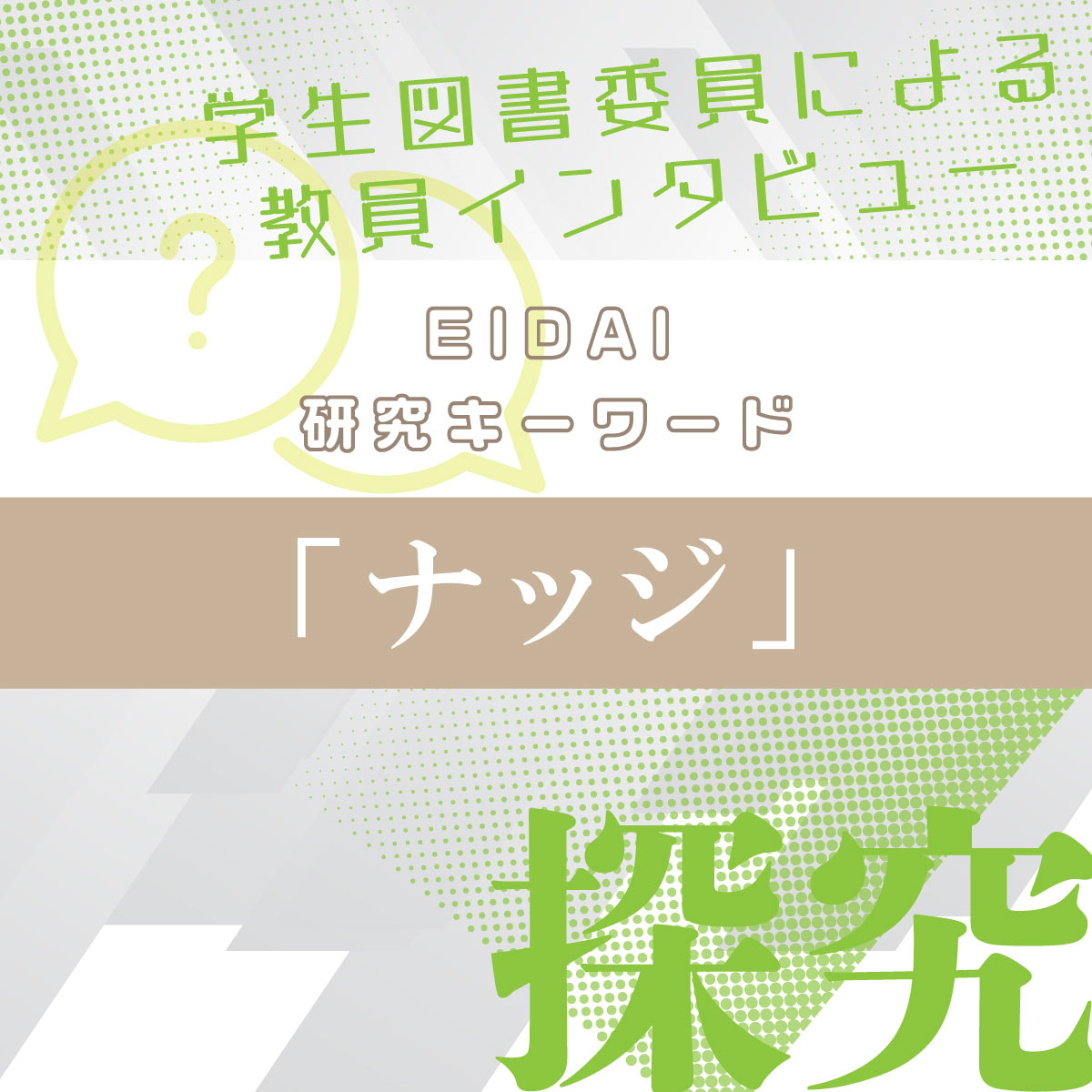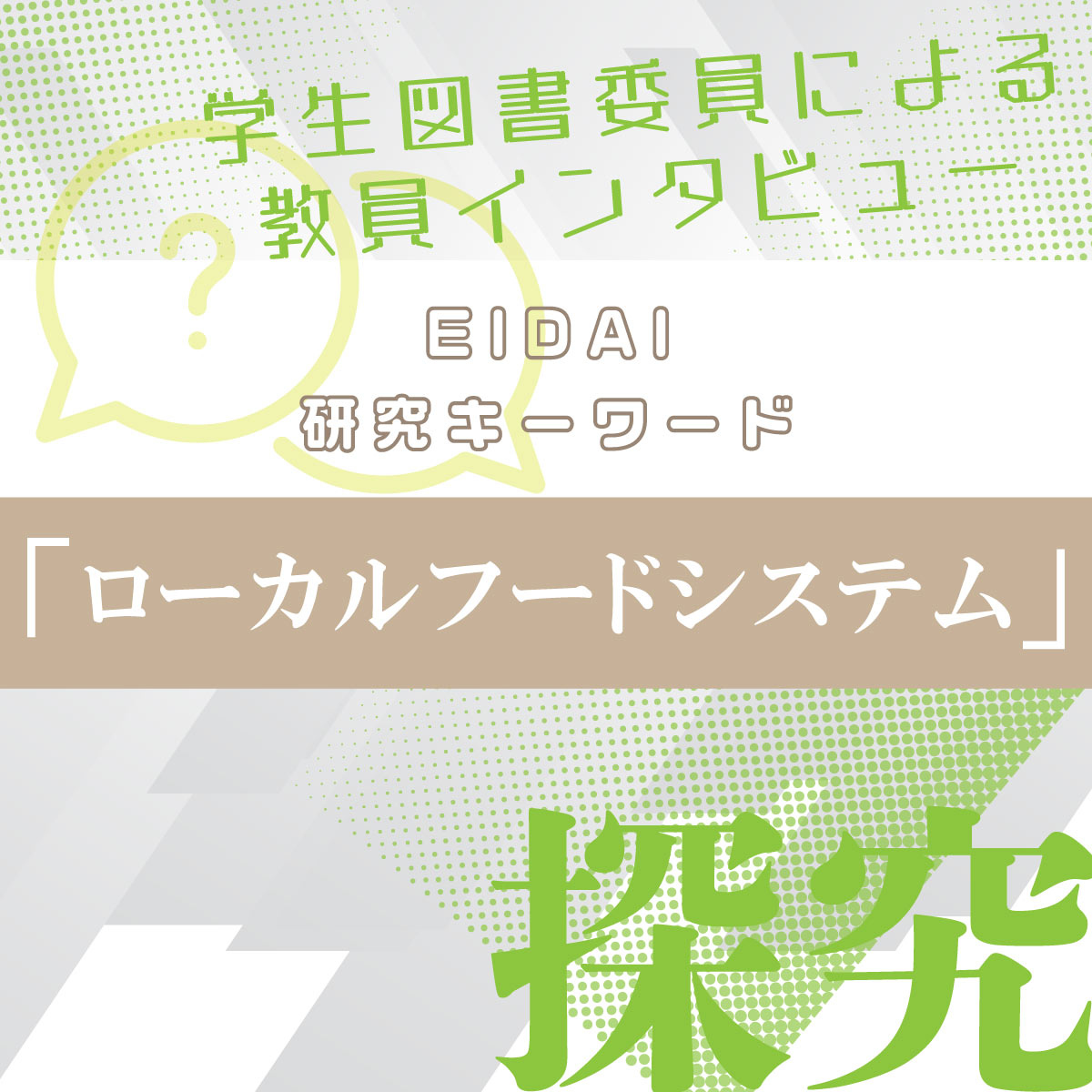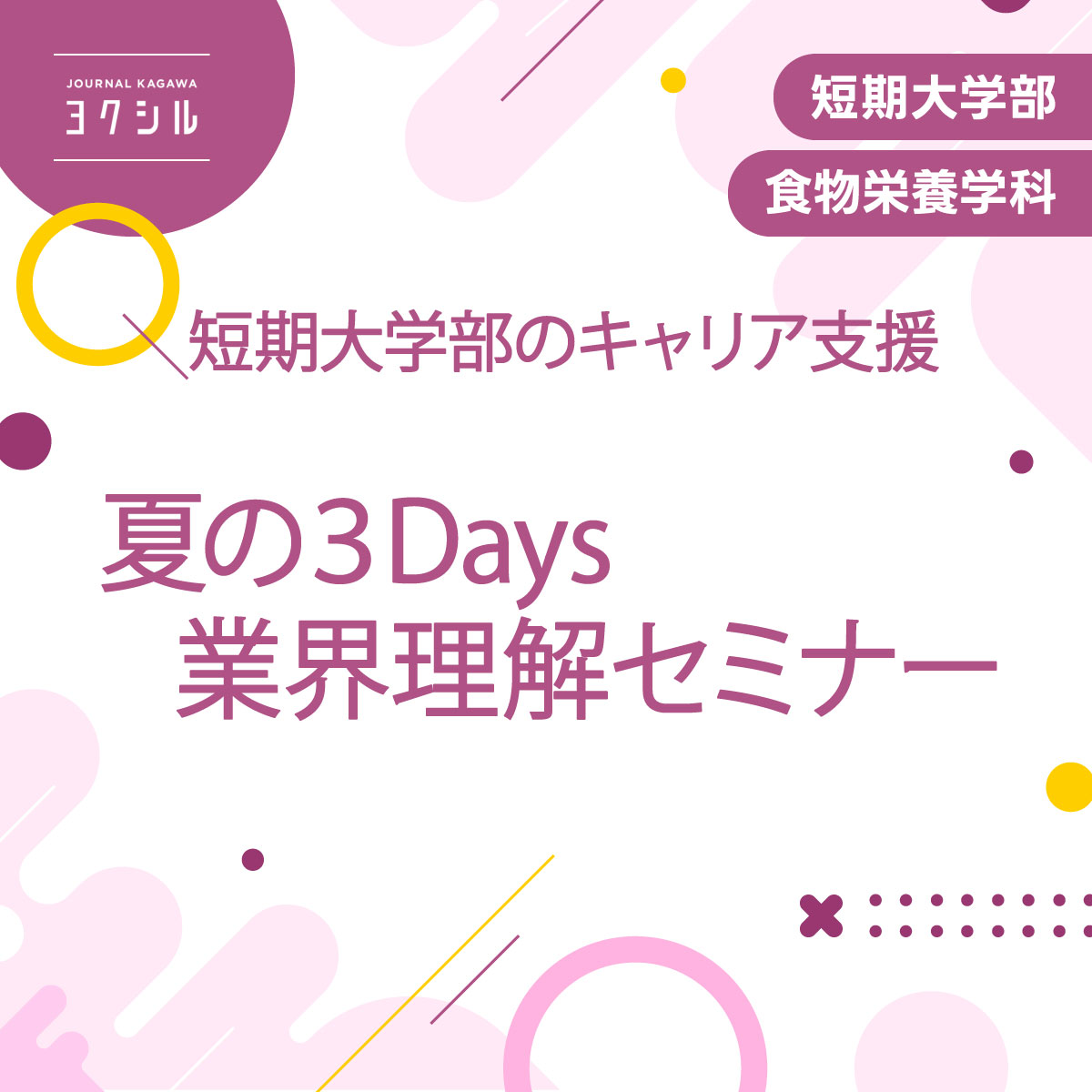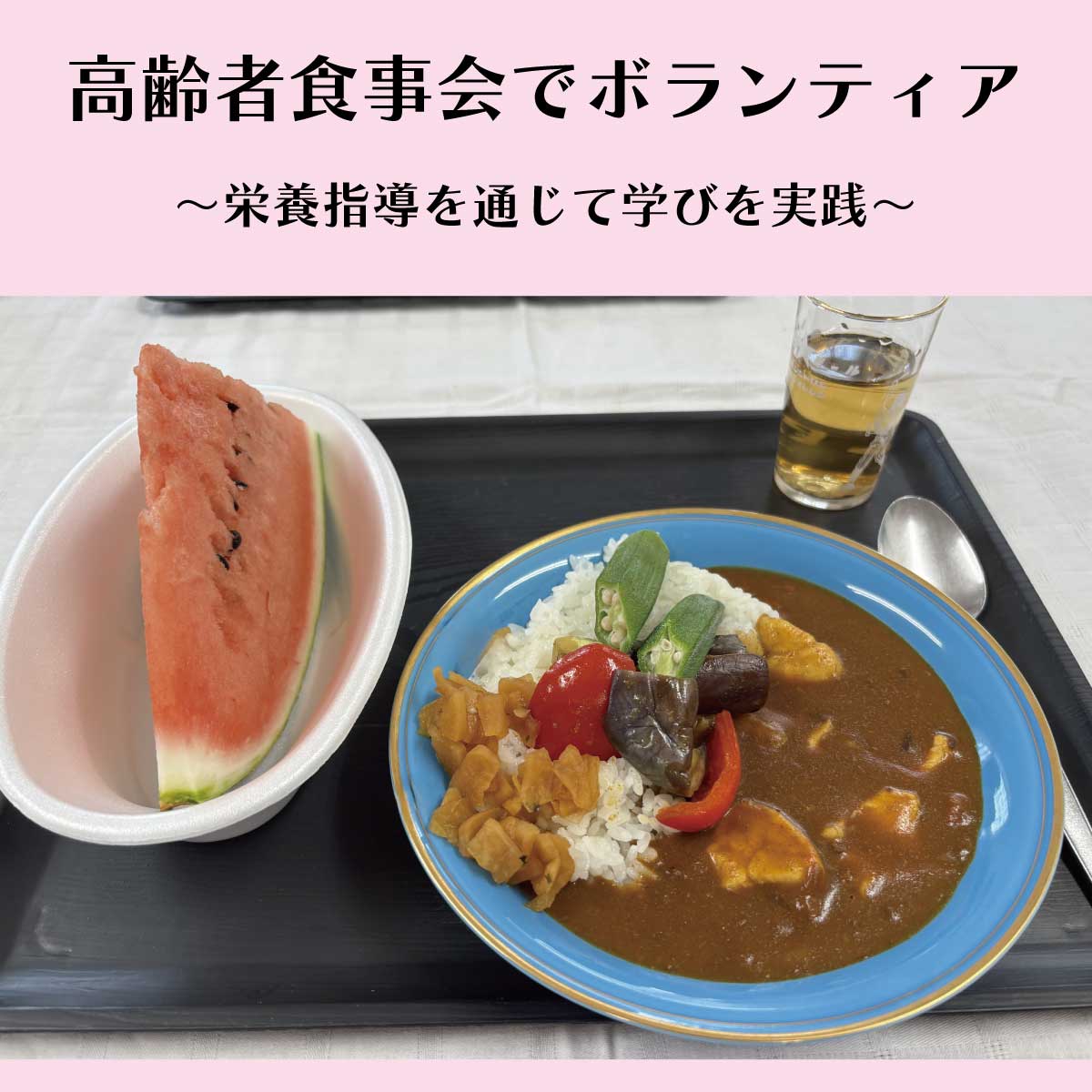保健養護専攻では、微生物学・免疫学を学びます。どちらも難しい分野ですが、微生物学の理解が感染症の予防や対策に、免疫学はアレルギーのメカニズムを学ぶことで、いざという時の迅速な対応に繋がります。
養護教諭として子どもたちの健康を守るために避けては通れない、学校内の環境整備、衛生指導の根拠になる科目です。

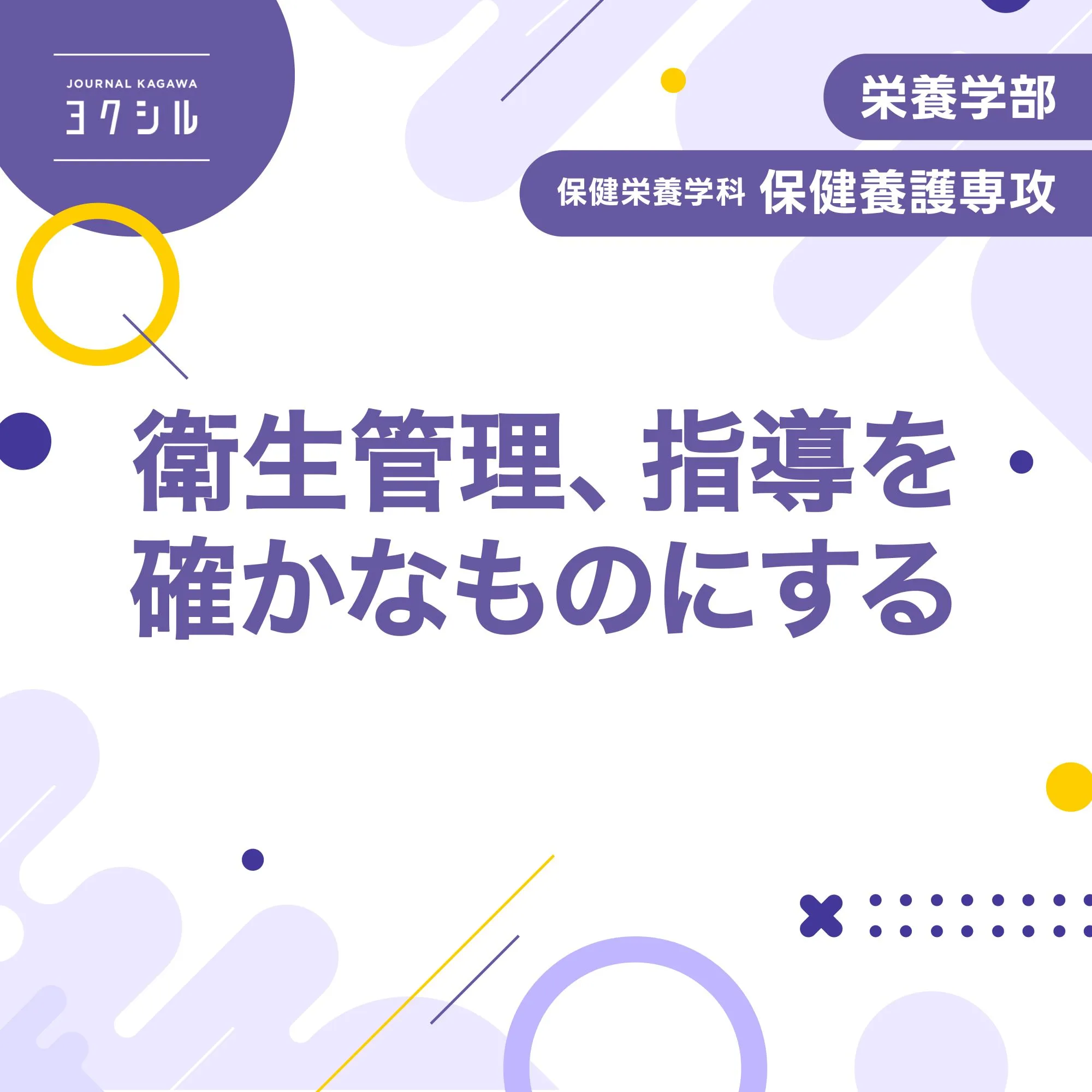
保健養護専攻
保健室/学校衛生管理/感染症対策
衛生管理、指導を確かなものにする学び

微生物学や免疫学は、日常に役立つ専門知識
1年次では微生物学で感染症について学び、2年次には感染制御学・免疫学を学びます。
例えば、ノロウィルスとコロナウィルスでは使用する消毒薬が違います。コロナウィルスにはアルコール消毒が有効ですが、ノロウィルスにはアルコール消毒は効果がありません。この違いは、ウィルス粒子の周りにある脂質の有無によるもので、ノロウィルスのように外側を覆う脂質がない場合は、アルコールではない消毒薬を使用します。
実際に学校で感染が起きた時や新しい感染症が発生した時にどのような対処をすればいいか、的確な判断ができるように、根本にある知識を学んでいきましょう。
専門知識と実体験で、指導に説得力が生まれる
実習では、手洗い方法の違いで消毒の効果を比較したり、自分の口腔内の菌を採取して培養し、糖の分解を比較して、虫歯(う蝕)と糖分解の関係を確かめる、というようなことをします。
虫歯の原因になるミュータンス菌にスクロース(ショ糖)を与えると歯を溶かす酸が産生され、逆にキシロースを与えると酸は産生されません、これらを実際にやってみる、という感じです。
歯磨きやキシロースが虫歯予防の効果があるのはわかっていても、実際に口の中でどう作用しているのかを知っている人は少ないと思います。実験を通して、「いかに感染を抑えるか」や「菌の増殖と抑制」を体験すると、例えば、学校内の感染予防や子どもたちの歯磨き指導などにも説得力が出ます。これは専門知識を持つことの強みです。
学校内の感染症は、新型コロナ、インフルエンザ、手足口病、プール熱などたくさんあり、それぞれに対策を変え、新しい感染症にも素早く対応するためには専門知識が必要です。食物アレルギーは、発症前と発症後の両方に対応しますが、これらも養護教諭の重要な役割なので、しっかりと身につけていきましょう。
一つひとつ学んで学校全体の健康を守る養護教諭へ
微生物学、感染制御学、免疫学は専門的な項目一つ一つ学びます。それらの理解が疾患の理解、予防、対応につながります。他大学では選択制になっていることもある分野なので、養護教諭として学ぶにはやや難しい印象があるかもしれません。しかし、根本を知っているからこそできる判断や結果もあります。児童・生徒の健康を守る、養護教諭の業務をより確かなものにするための学びです。
お話を聞いた先生

▲石橋 健一 先生
食と免疫,感染防御学,腸内免疫・腸内細菌,有用微生物