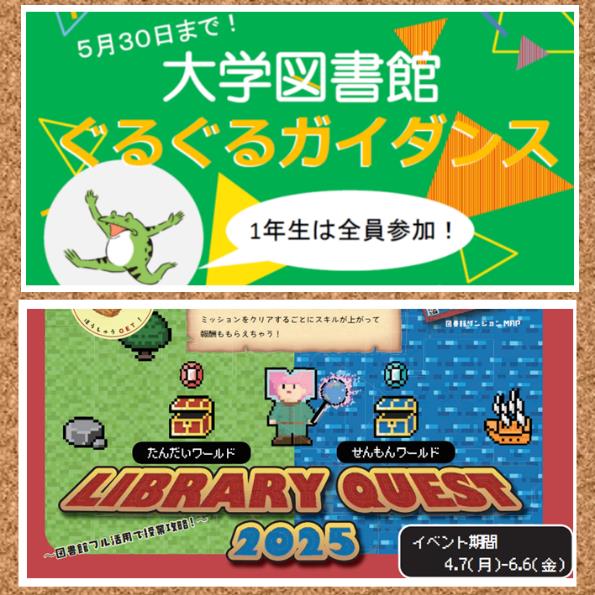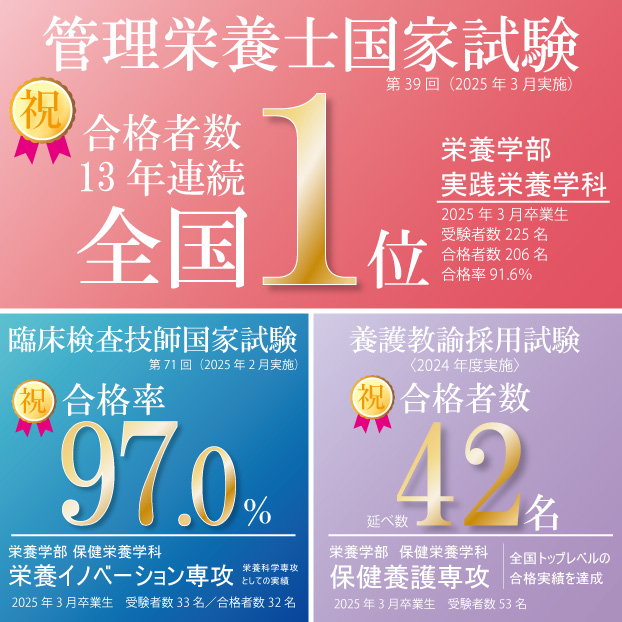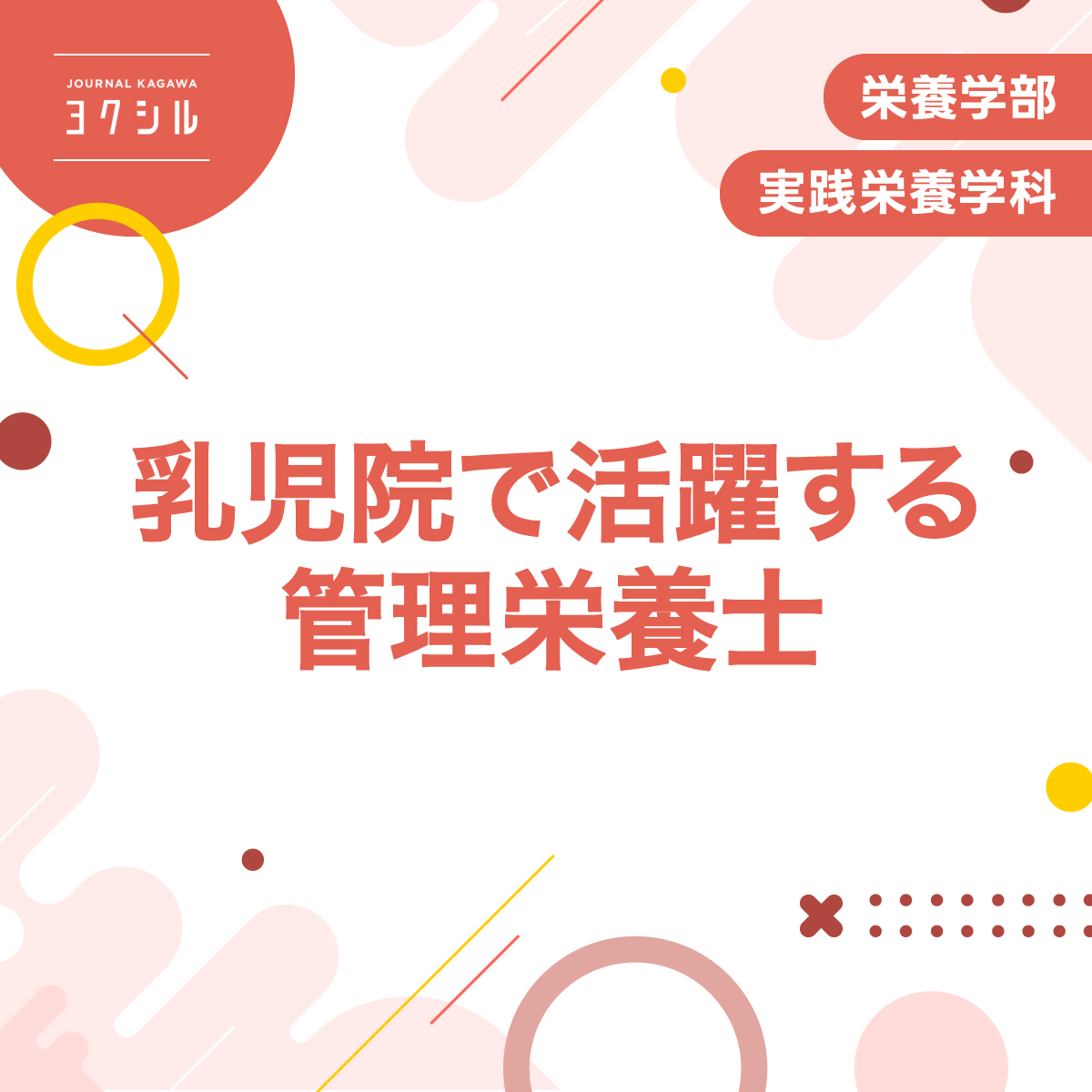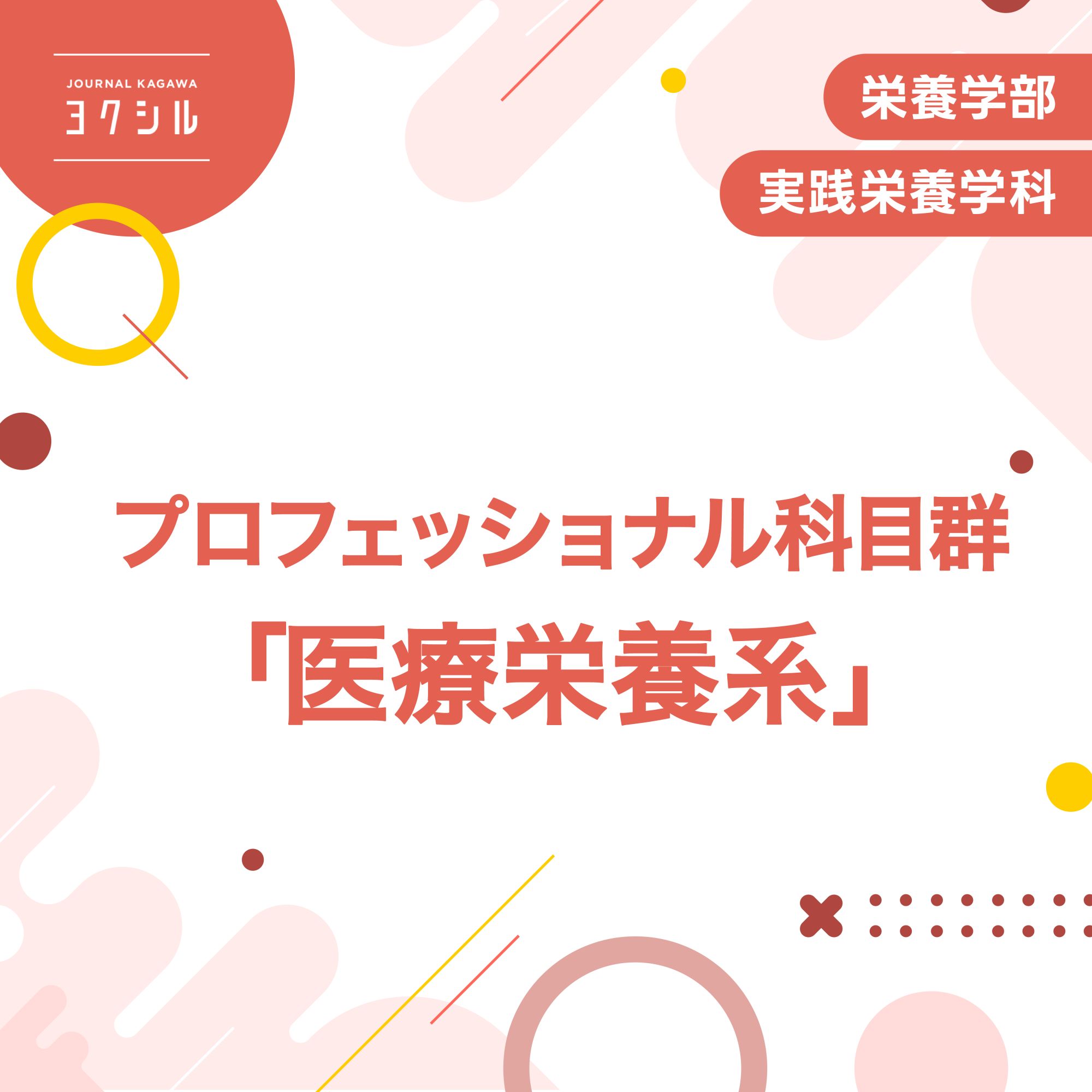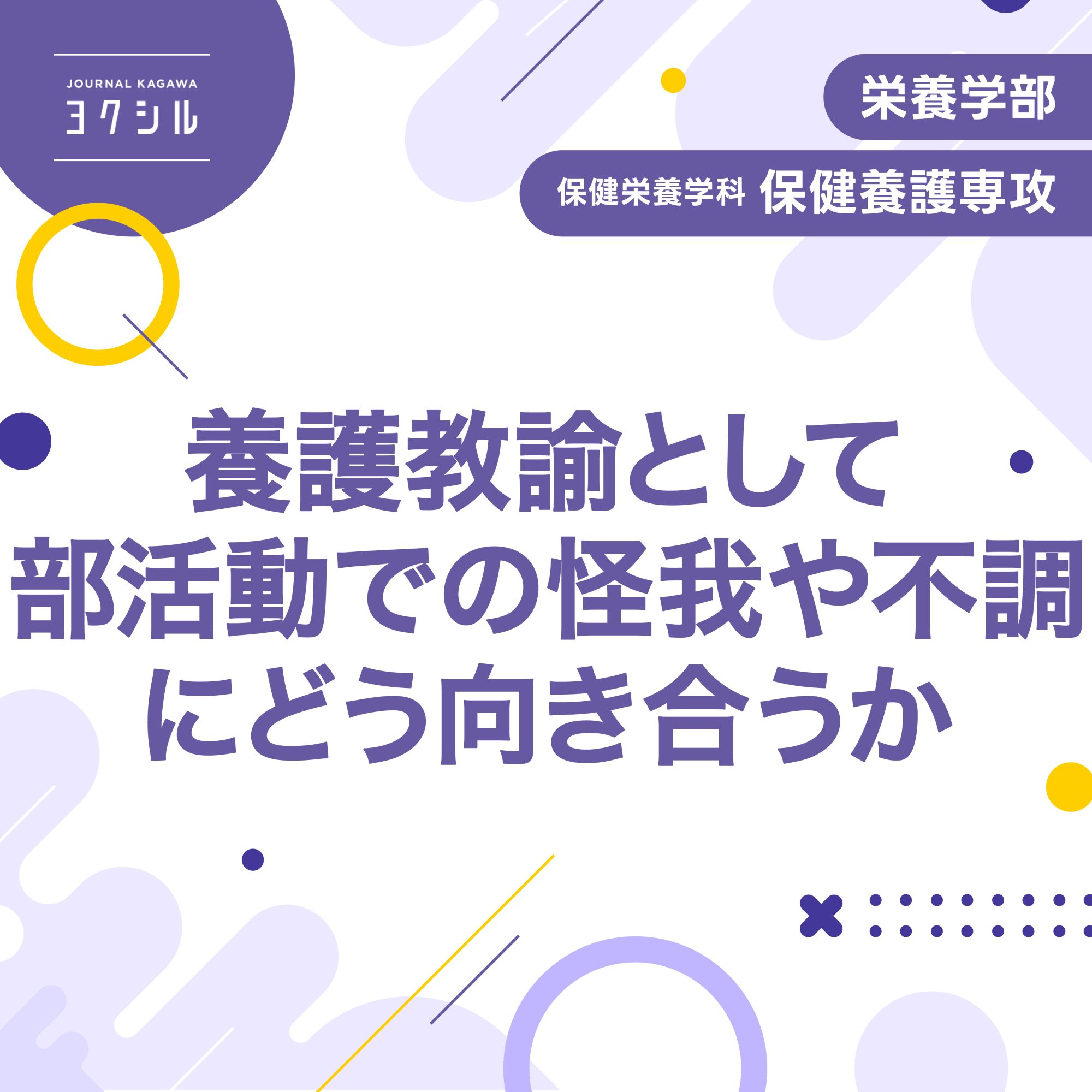実践栄養学科は、管理栄養士になるための科目のほかに、プロフェッショナル科目群という管理栄養士資格をさらに発展・充実させるため、5つの系統に分けた科目をそれぞれ3科目ずつ展開しています。
「公衆栄養・国際栄養系」では、国や地域の健康問題を解決するための公衆衛生や栄養、健康づくり、疾病予防などの観点で栄養のマネジメントを学びます。
そこに暮らす住民の方や多くの関係者と連携し、時間をかけて広範囲に働きかけるダイナミックな視点を養うだけでなく、災害時の栄養・食生活支援や平時の備えなどの災害栄養について深く学べることもこの科目の特徴の一つです。

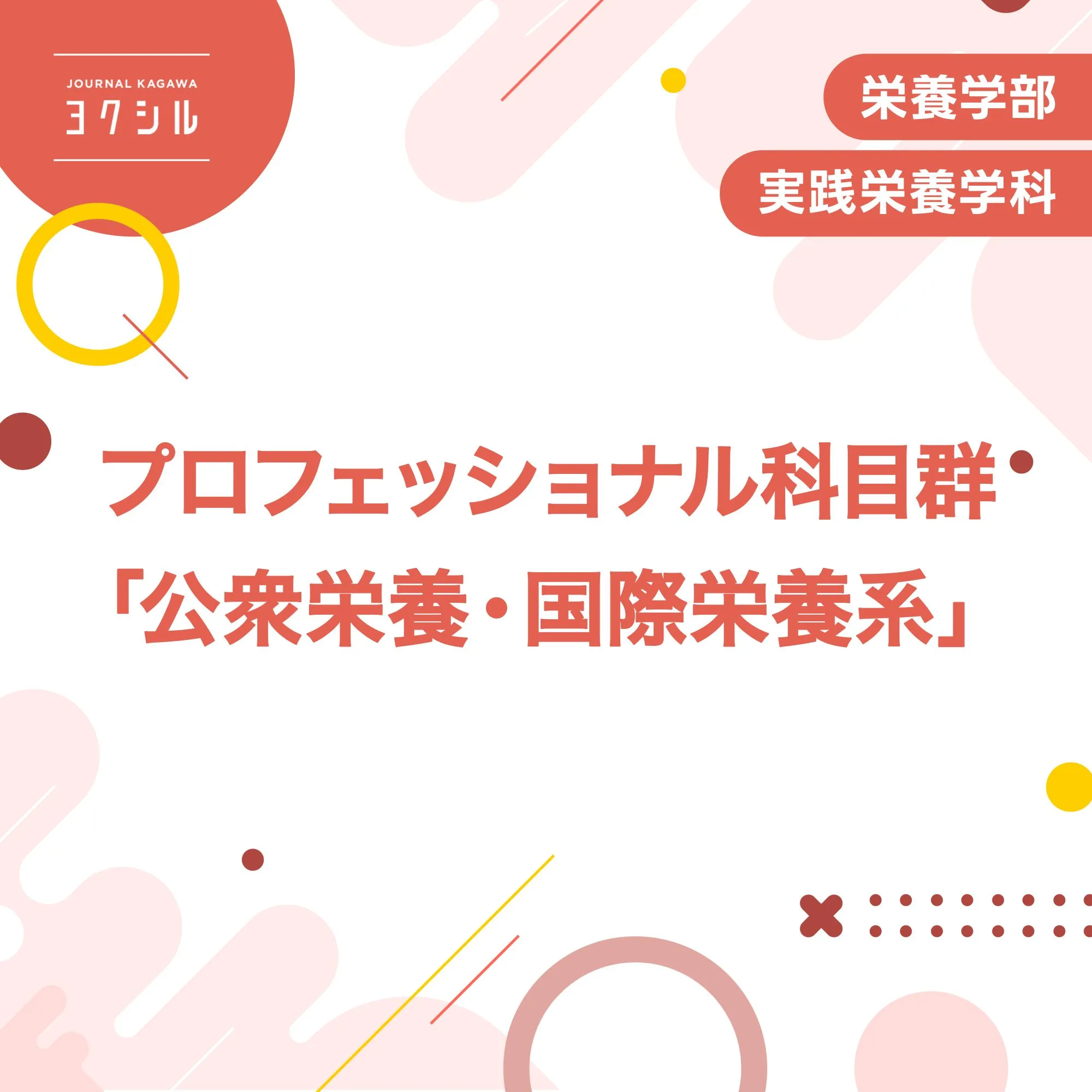
実践栄養学科
実践栄養学科/プロ科目/災害食/管理栄養士
栄養・衛生の力で国や地域の健康問題を解決

栄養・食生活の視点から「個人の力」と「組織の力」で、より多くの人を健康で幸せにする
公衆栄養・国際栄養系は、地域の栄養施策と諸外国を取り巻く栄養課題について学ぶ「地域栄養・国際栄養概論」と、災害時の栄養・食生活支援を通した被災者の健康維持、食の自立支援について学ぶ「災害栄養活動論」、地域の継続可能な栄養・食施策について学ぶ「地域マネジメント実習」の3つの軸で構成されています。
行政の公衆衛生活動は、管理栄養士が行う栄養指導のような業務だけでなく、衛生や保健の分野にも関わります。常に多職種と連携しながら働くのが前提なので、他職種の専門性などへの理解もとても重要です。
3年次の臨地実習では、自治体の保健所や保健センターで2週間研修を行い、地域住民の健康増進や普及啓発、栄養指導などを体験します。4年次の地域マネジメント実習では、学内または学外の実習で、災害栄養や子どもの貧困、特定健康診査・特定保健指導の実際について現場に出向いた体験を行います。
国際栄養では実際に国際機関に関わっている講師の方々を招き、諸外国でどんな栄養に関する問題がおきているかなどを知り、それらに対するアプローチ方法などを学んでいきます。
災害時の栄養・食生活支援、世界の栄養の二重負荷の解決方法を考える
日本全国の管理栄養士養成課程の中でも、特に災害栄養について一番学べるのは本学だと思います。
災害の多い日本では、「被災した時に、どうやってできるだけ早く個々に最適な栄養を届け、健康を維持するか」や、「非常時の現場での対応方法や知識をどうやって広げるか」など、被災時の課題は多くあります。被災を体験することは難しく、また、体験したくないものです。災害栄養活動論では過去の災害をもとに作成したオリジナルのカードを使って、ワークショップで詳細にシミュレーションをしながらこうした課題について議論します。
そのほか、身近なところでは非常食を販売するメーカーと一緒に、より美味しく栄養がとれる新しい非常食の開発もしています。
世界に目を向けると、「栄養過多」と「栄養不足」の2つの栄養負荷は大きな問題です。これらは地域の食習慣なども大きく関わり、目の前の人にただ栄養を届けるだけでは解決できません。地域の食や生活習慣などを知り、栄養の知識を根付かせ、食習慣を改善するために行政や関連機関との連携が必要になってくるので、「課題解決のために何を動かし、どう対策を広げていくか」など、時間をかけて大きく動かすことについて学びます。
Think Globally, Act Locally.
管理栄養士のスキルが、身近な地域の行政からグローバルなキャアリアに繋がる分野でもあります。卒業後は自治体の保健所や保健センターの管理栄養士、厚生労働省や消費者庁の栄養技官のほか、WHOやユニセフ、JICAなどの国際機関で働く人もいます。
一人でも多くの人に健康を届けるために、地域や自治体、時には国を跨いで何をどう動かすか。さまざまな角度から考え、幅広い視野を身につける科目です。
お話を聞いた先生

▲久保 彰子 先生
【キーワード】
災害栄養、ヘルスプロモーション、食環境整備、ラオス栄養改善、行政管理栄養士育成