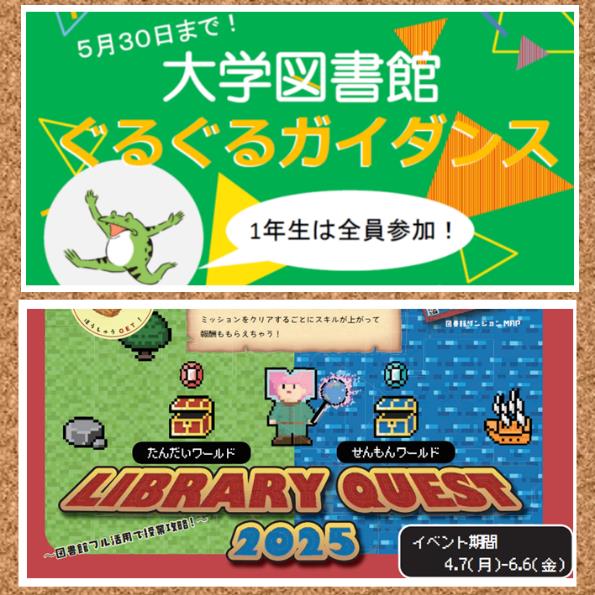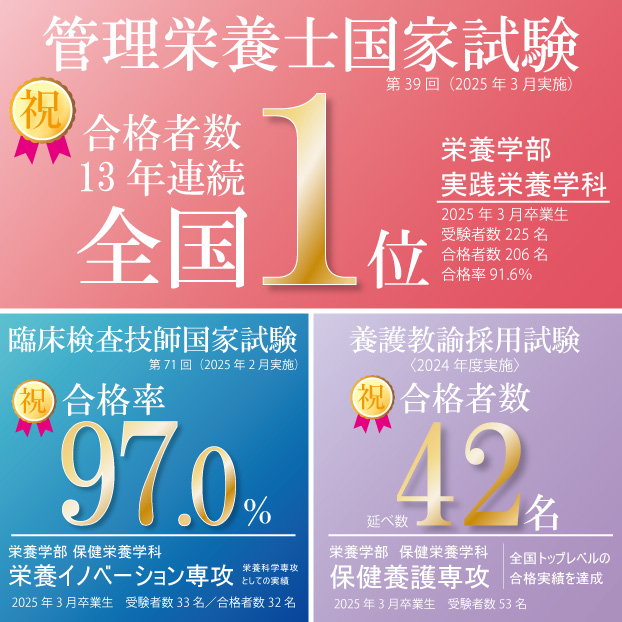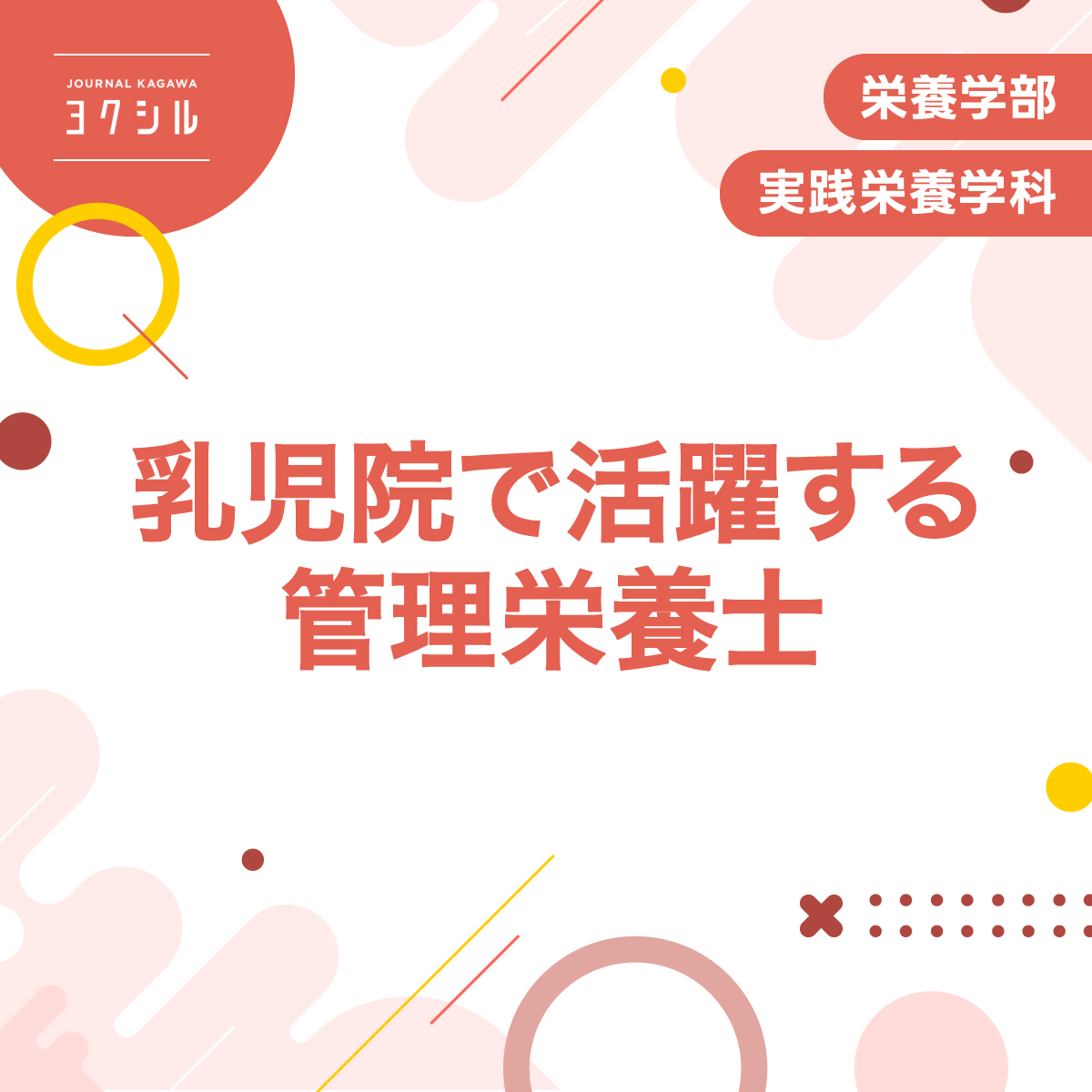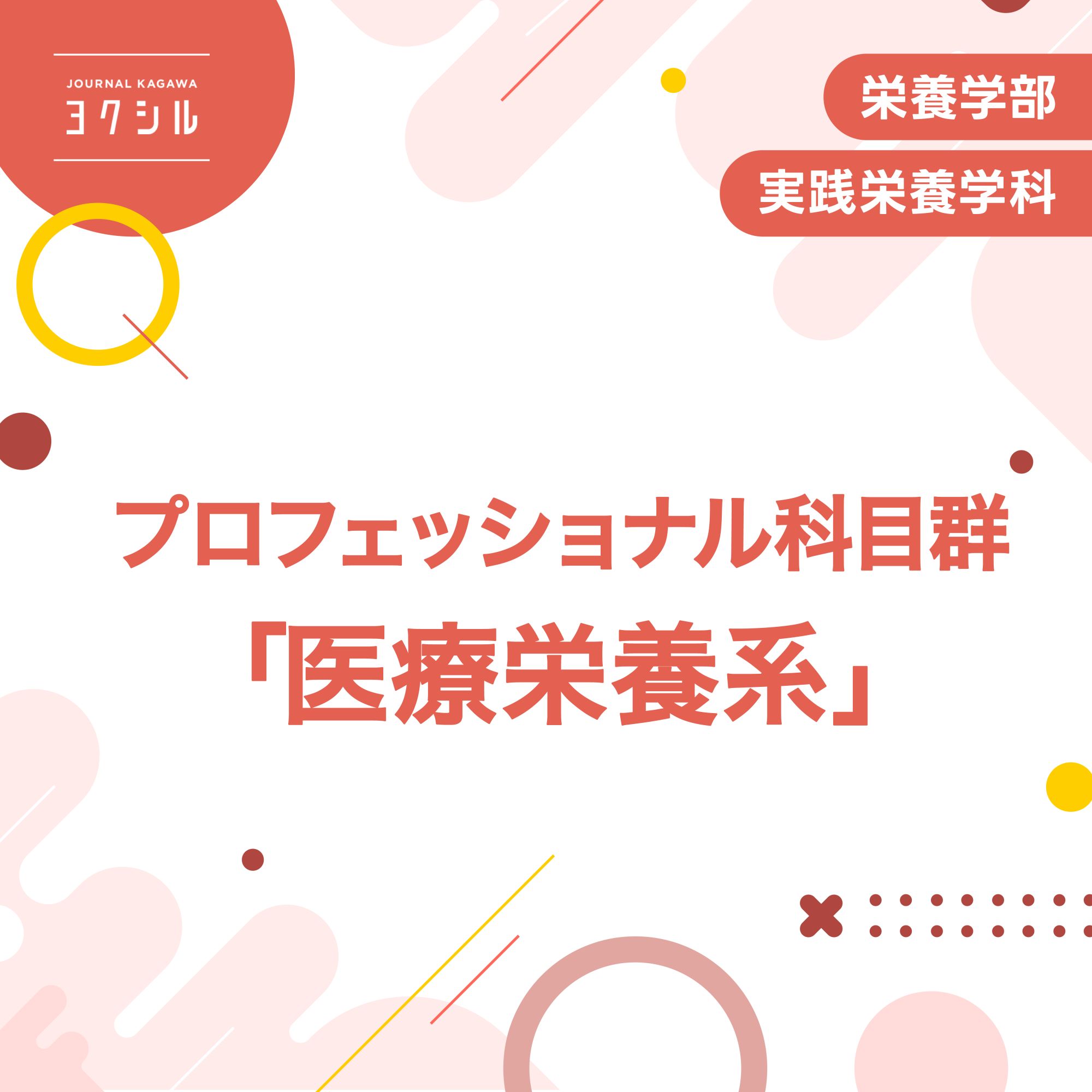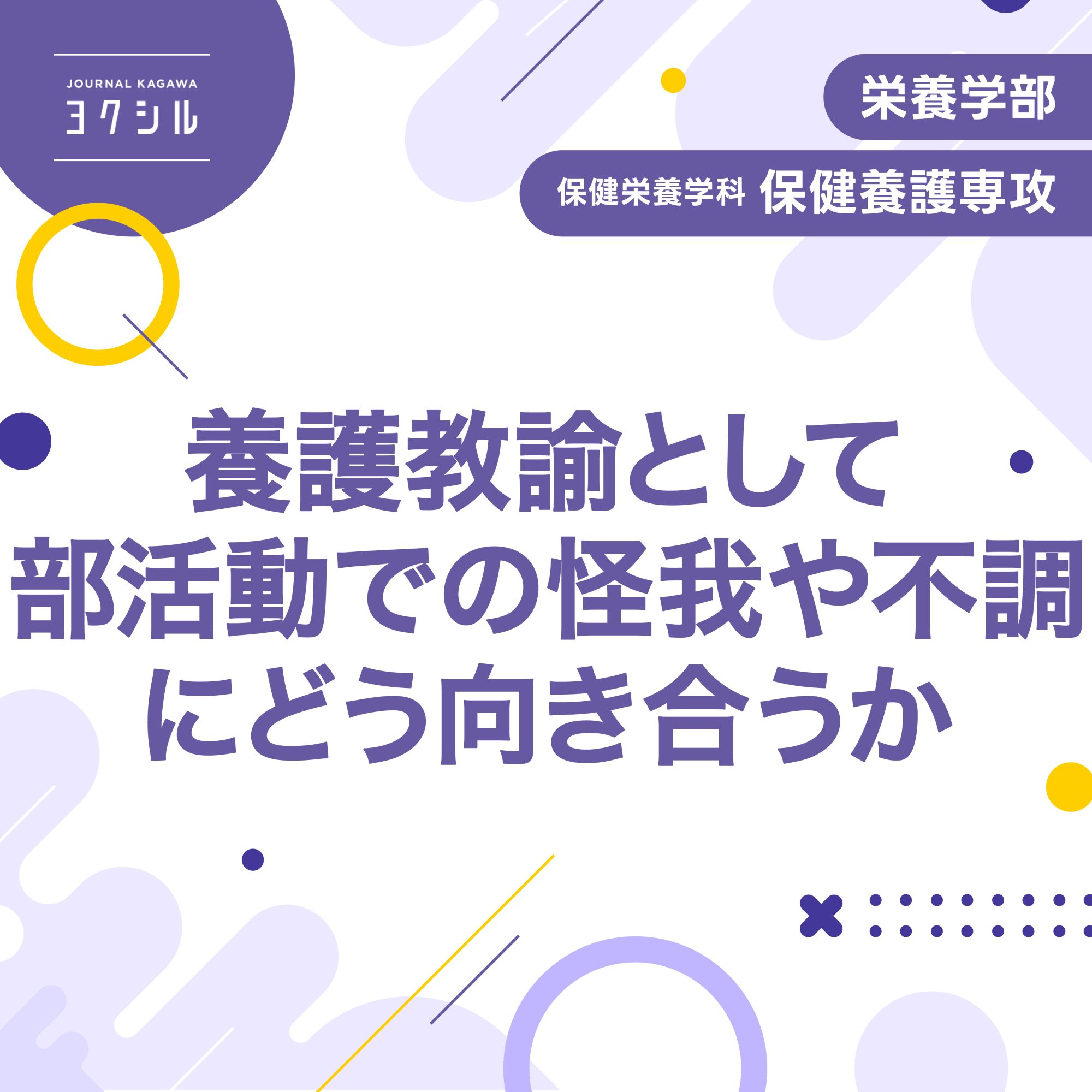実践栄養学科は、管理栄養士になるための科目のほかに、プロフェッショナル科目群という管理栄養士資格をさらに発展・充実させるため、5つの系統に分けた科目をそれぞれ3科目ずつ展開しています。
「スポーツ栄養系」では、スポーツに必要な管理栄養士の知識と経験、運動生理学、調理方法などのほか、対象者の精神面を支えるためのコミュニケーションなども学びます。
スポーツ栄養は、アスリートや運動をする人に限定した栄養学だと思われがちですが、実は対象の幅が広く、育ち盛りの子どもや働き盛りの成人、高齢者の健康維持にも有効です。公認スポーツ栄養士を目指すだけでなく、専門知識がさまざまな分野で活かせます。

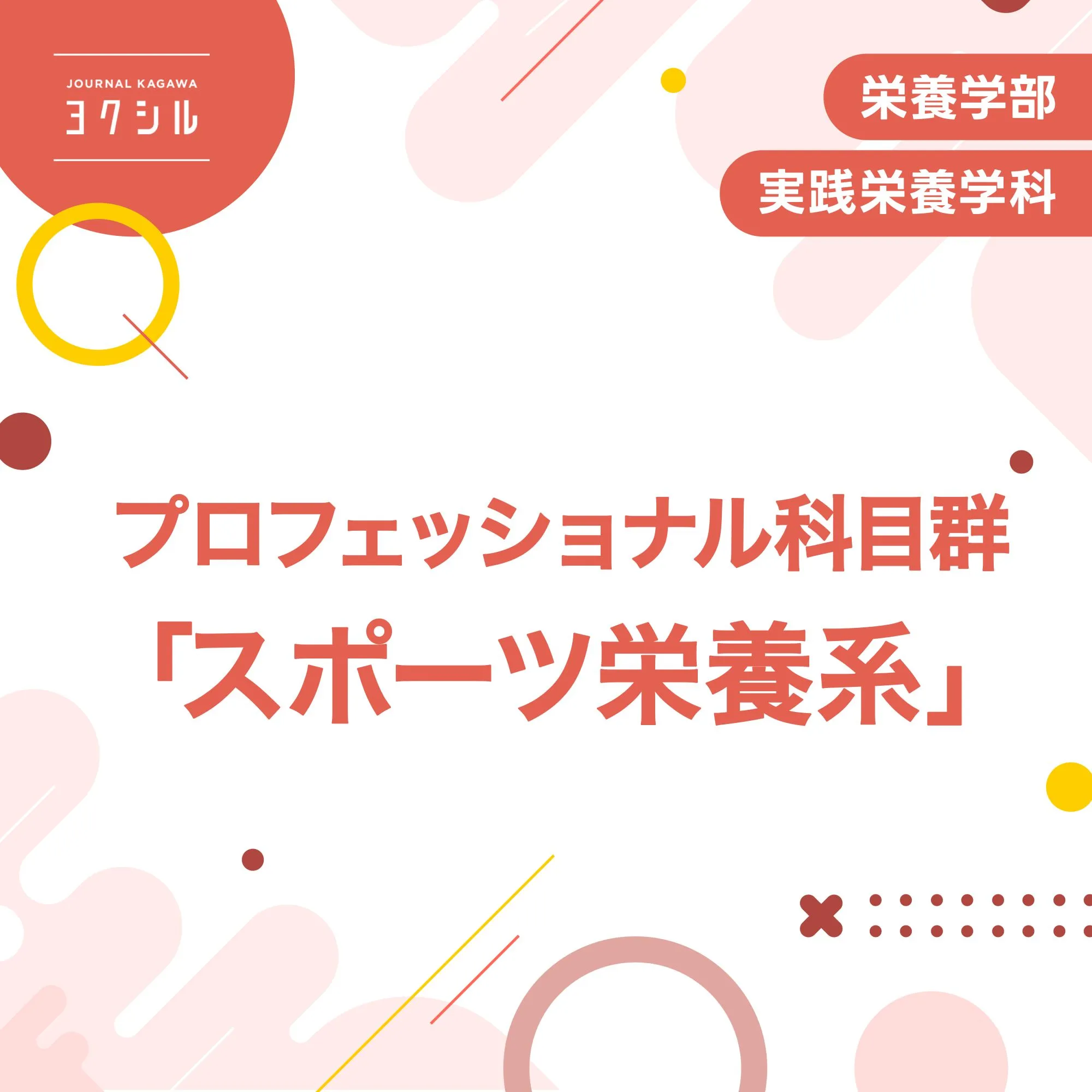
実践栄養学科
栄養生理学研究室
上西 一弘 教授
運動する人の栄養を学ぶ「スポーツ栄養系」

スポーツ栄養系で学ぶ「スポーツ」「身体」「栄養」「コミュニケーション」
スポーツ栄養系では、1・2年次に学んだ栄養学や解剖生理、生化学、調理、給食などの知識を基礎に、3年次はスポーツ概論、スポーツ栄養学へと学びを深め、4年次には実際に他大学のスポーツ選手達に食事を提供するところまで行います。
栄養の知識だけでなく、過酷なトレーニングや競技に必要な栄養を考えて献立にして美味しく食べてもらうことや、対象者との信頼関係を築くためのコミュニケーションも必要です。そうしたことを体験的に学べるよう、講義科目のほか実習や実験、演習などの体験的な授業もあります。
実際のカリキュラム
例えば、「栄養ドリンク・エナジードリンク・スポーツドリンク・経口補水液はどう違うか」というテーマの演習では、実際にたくさんの種類のドリンク類を並べて成分を比較し、「どう違うのか」「どんな時に飲むと良いのか」などを学びながら飲み比べをしました。普段なんとなく手にしているドリンクが詳しくわかり、学生たちの関心も高い演習です。
4年生最後の実習では、ゼミでサポートしている他大学の選手のために、レバーなどの栄養豊富な食材を使った献立を考え、選手たちに実食をしてもらいます。学校に到着してから教室に招き、それぞれのグループで考えた複数の料理を並べて、どれを選んでくれたか、どれが一番好評だったか、などを調査します。今までに学んだスポーツ栄養の知識を駆使した献立も、美味しく食べてもらわないと意味がないので、相手の競技種目や年齢、好みなどに合わせてどう接して提供するか。4年間の学びの集大成とも言える、緊張感のある実習です。
スポーツ栄養の可能性
オリンピックの開催や日本のアスリートの活躍で、近年は「スポーツ栄養」という言葉をよく耳にするようになりました。この科目は、「自分が運動をやっていたから」「スポーツをやっている家族を応援したい」という理由で選択する人が多くいます。しかし、育ち盛りの子どもや働き盛りの成人、高齢者への栄養提供のほか、体を使う全ての人に活かせる専門知識です。コミュニケーションも含めて様々な角度で相手のことを考え、さまざまな環境や状態の対象者に栄養を届けられるよう、一緒に学んでいきましょう。
お話を聞いた先生

▲上西 一弘 先生
【キーワード】
ミネラル代謝,骨代謝,身体組成,スポーツ栄養