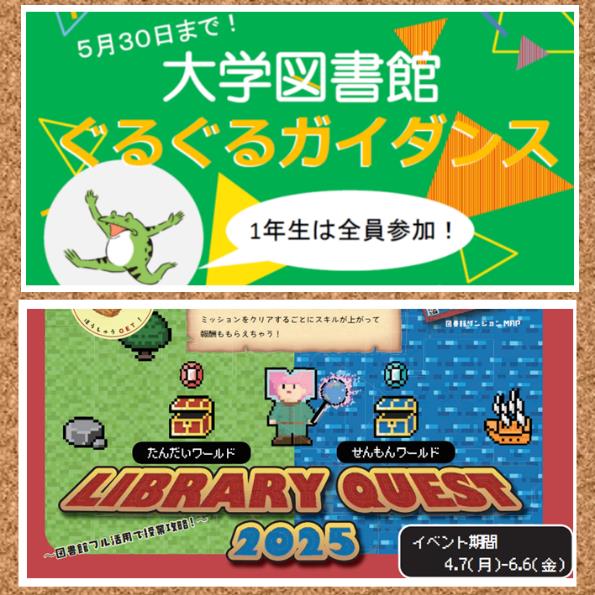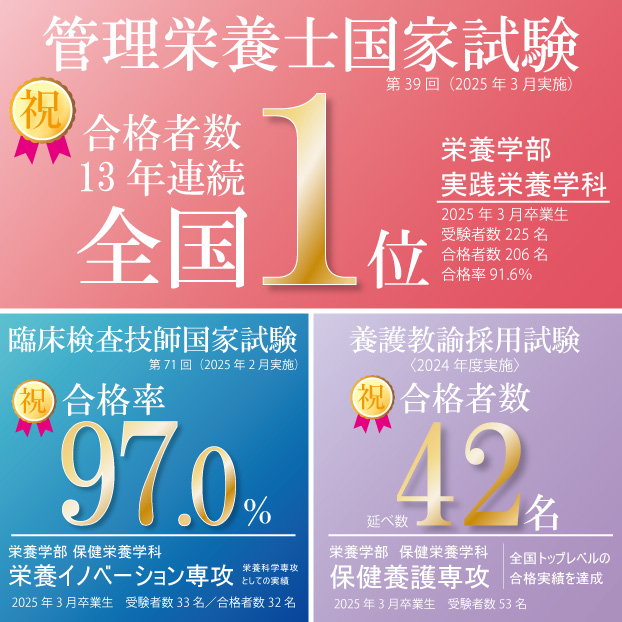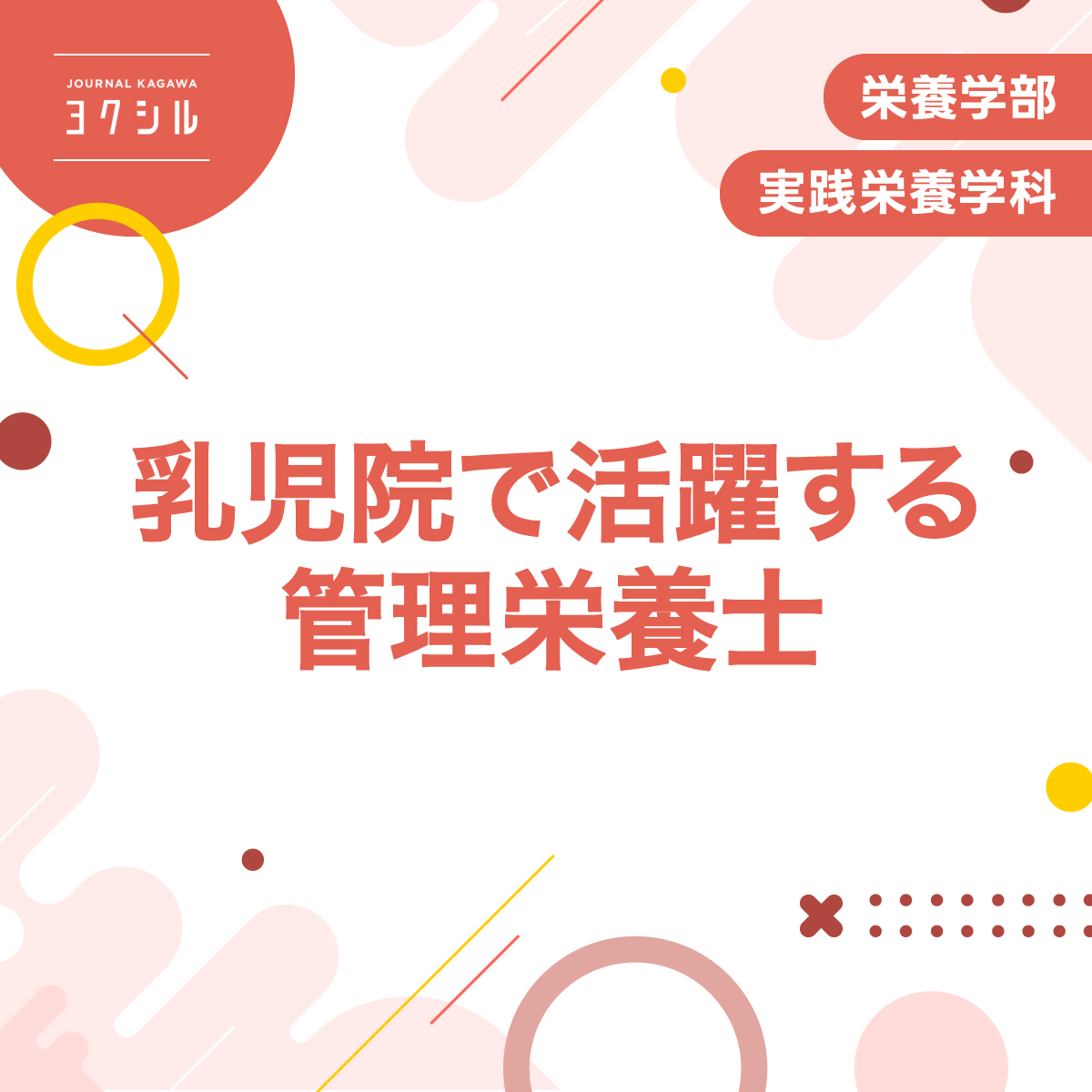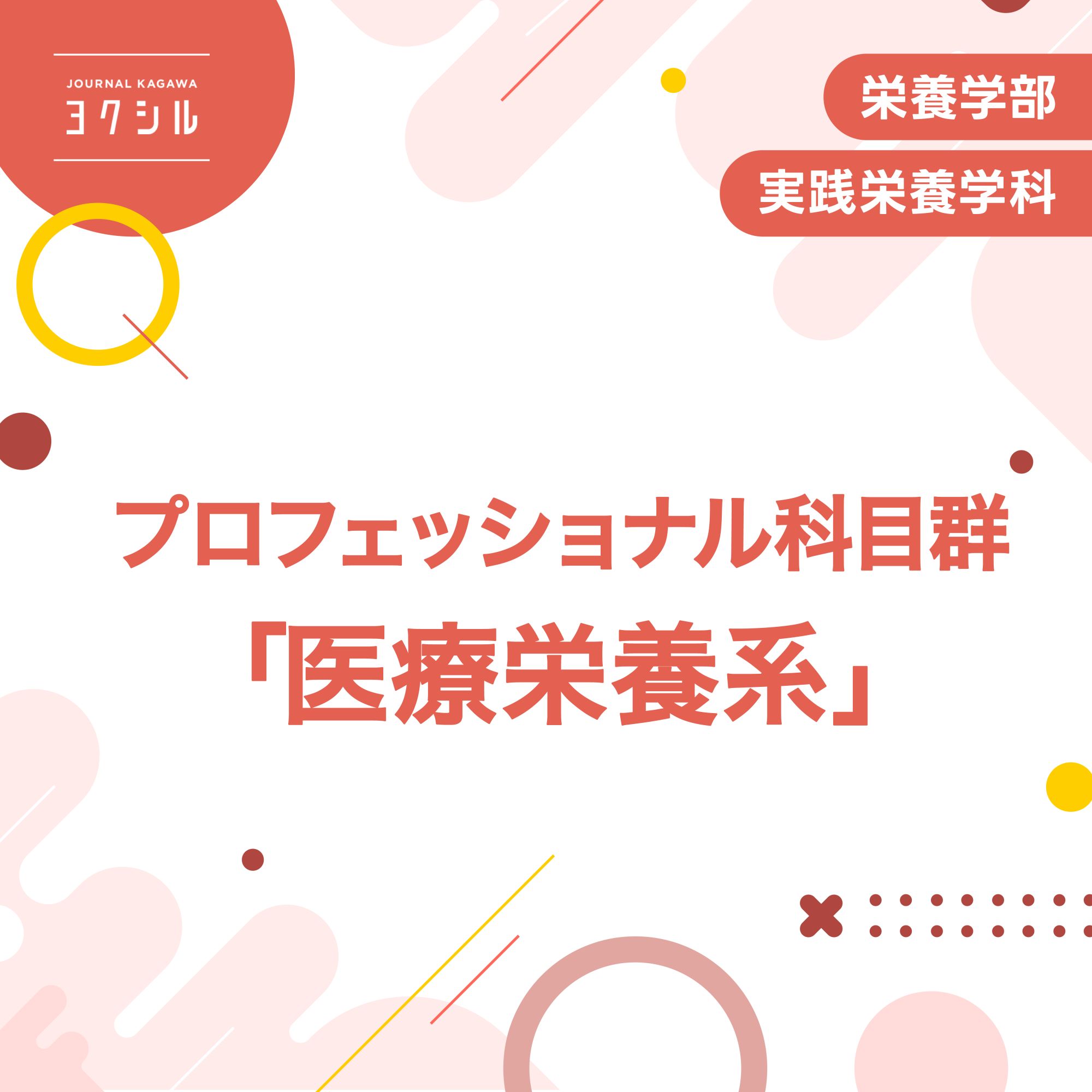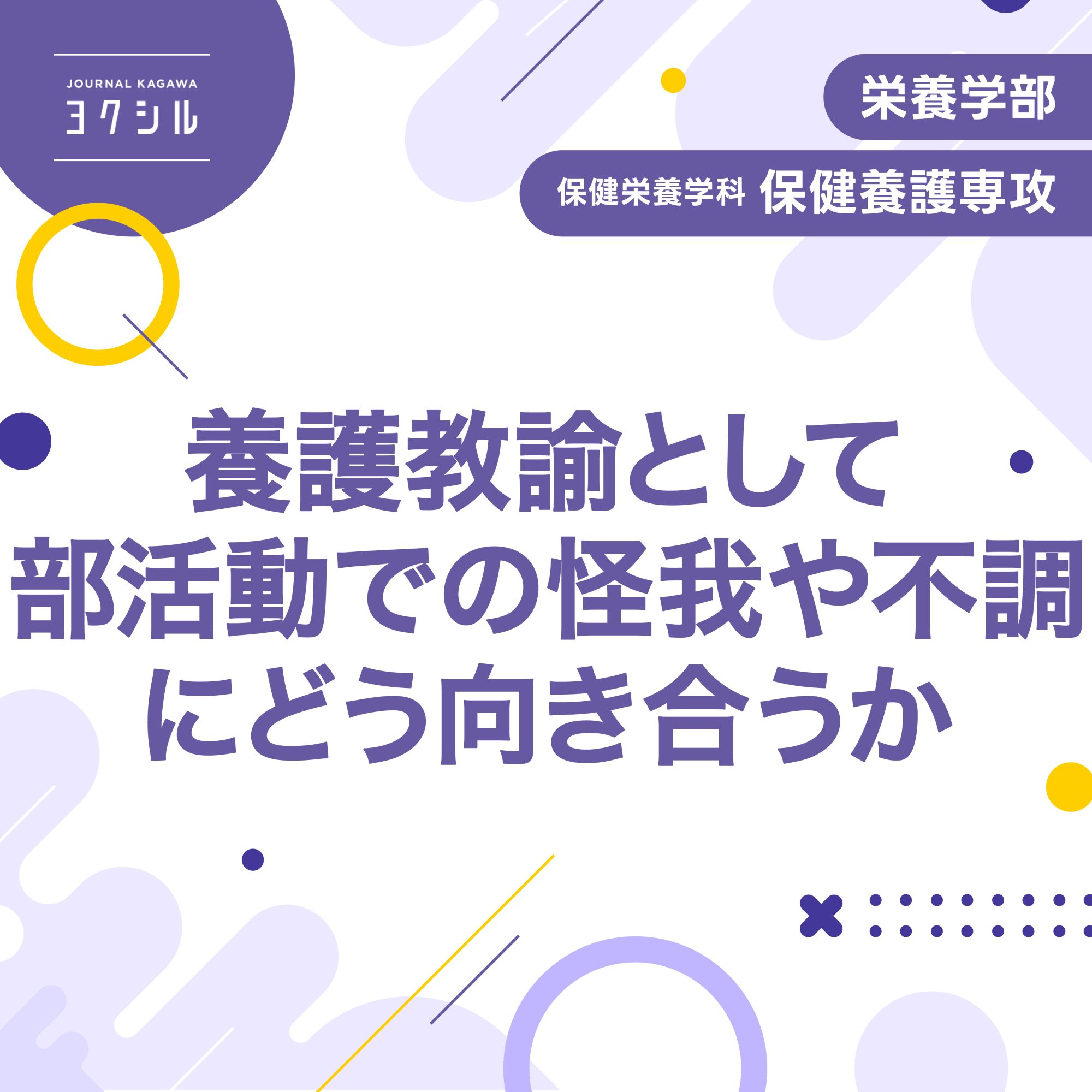本学の養護教育の特徴は、「食と栄養の知識、養護教諭の現場に必要な知識」と、「たくさんの人と関わりながら子どもたちの心と体の健やかな成長を第一とする学び」です。
子ども達の健康を支え、専門知識と知見に基づいた的確な判断をし、担任や校長、保護者をはじめたくさんの人と関わることもある養護教諭の仕事に、本学の幅広いカリキュラムで身につけた知識が強みになります。

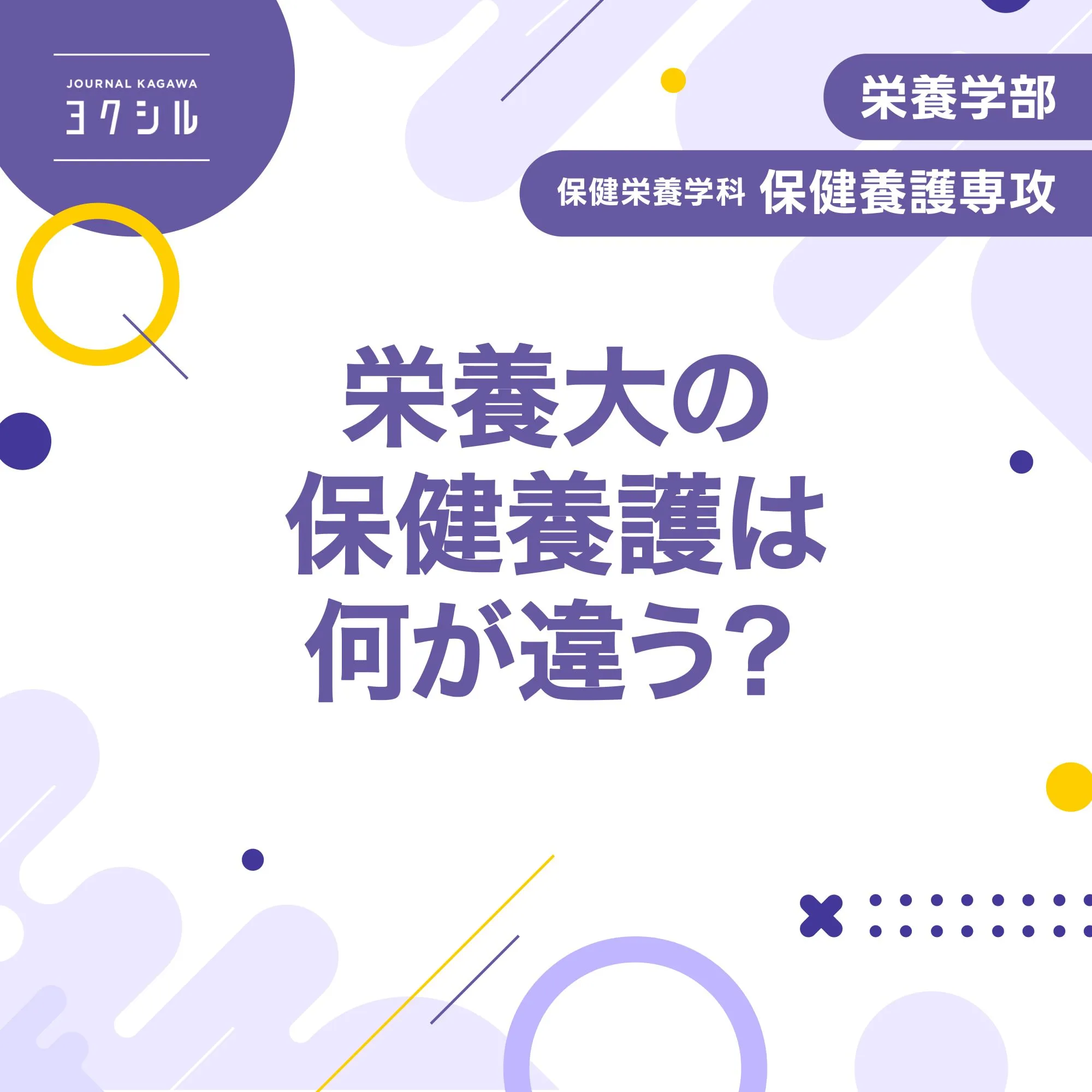
保健養護専攻
養護教諭/食育/保健室
栄養大学の保健養護は何が違う?

食行動から、子供たちの家庭や健康が見えることもある
学校での食育も含めた健康教育は子供たちの食習慣形成の基礎になり、生涯を健康に過ごすためのとなります。食行動や食習慣は大人になってから改善するのは難しいので、学齢期の早いうちから健全な食生活を身に付け、国民全体で健康を維持、増進していくことも目指しています。
実際に養護教諭として小中学校で働くと、食に関する課題や問題を抱えている子供が思いのほか多く、食物アレルギーなどの体質的な問題のほかに、食行動から別の問題が見えてくるがあります。極端な偏食の原因が家庭での食生活にあったり、偏食だと思っていたら思わぬ傷病が潜んでいたりすることもあります。毎日子供たちを観察してちょっとした違和感に気づき、学校の担任や外部機関とやりとりをして、何かあった時に迅速に具体的に対応を考案するのも養護教諭の仕事です。食と栄養の知識・技能を礎にしている本学の養護教諭だからこそ、それらを的確に担える強みがあります。
様々な組織・立場の人々との円滑な連携・協働もできるプロフェッショナルな養護教諭へ
養護教諭はほとんどの学校で一人職です。数百人の子供たちの健康課題を一人で解決するのは難しいので、全体を見ながら担任や保護者、管理職、そのほか内外の人とうまく連携・協働できるように調整していく役割も担っています。目の前の事実に対処するだけでなく、広い視野で分析する知識と経験も多彩な実習や演習を通して身に付きます。
学ぶ事がたくさんあるので大変ですが、本学の強みである食と栄養の教育が、養護教諭として働く上での自信と信頼、そして子供たちの心と体の健康を作つくりその将来にもつながっています。ぜひ一緒に学んでいきましょう。
「食と栄養の知識・技能を強みに」栄養学部で学ぶ保健養護とは
保健養護では、1年次は栄養学や解剖生理、養護概説などといった養護教諭に必要な基礎知識を、2年次は長期学校体験実習や看護学臨床実習を通して学校という場、教員、養護教諭という職の具体的な役割を学びます。3年次には講義や演習を通して養護教諭としての専門性を高め、4年次には養護実習や教育実習で実践力を身につけ、学びの集大成として卒業研究や教職実践演習で自分なりの課題を見つけて掘り下げ、グループワークで仲間と一緒に連携・協働しながら解決することを学びます。
実際の学校現場では、子供たちの他にも学校内の担任の先生や校長、副校長、教頭、保護者、学校外の医療機関、教育委員会、児童相談所、警察など、様々な組織・立場の人々と連携・協働します。
本専攻では、グループワークなど協働的な学びに重点をおいており、学んだことや多彩な実習での経験をしっかりまとめ、多くの人たちに向けて発信する経験を積み重ねていきます。ですので、養護教諭になった時に周りの人と連携・協働して、自らの考えを伝え、仲間と連携・協働して問題を解決していく力が身に付くのです。
お話を聞いた先生

▲久保田 美穂 先生
【キーワード】
防災教育,保健教育,養護診断,保健管理