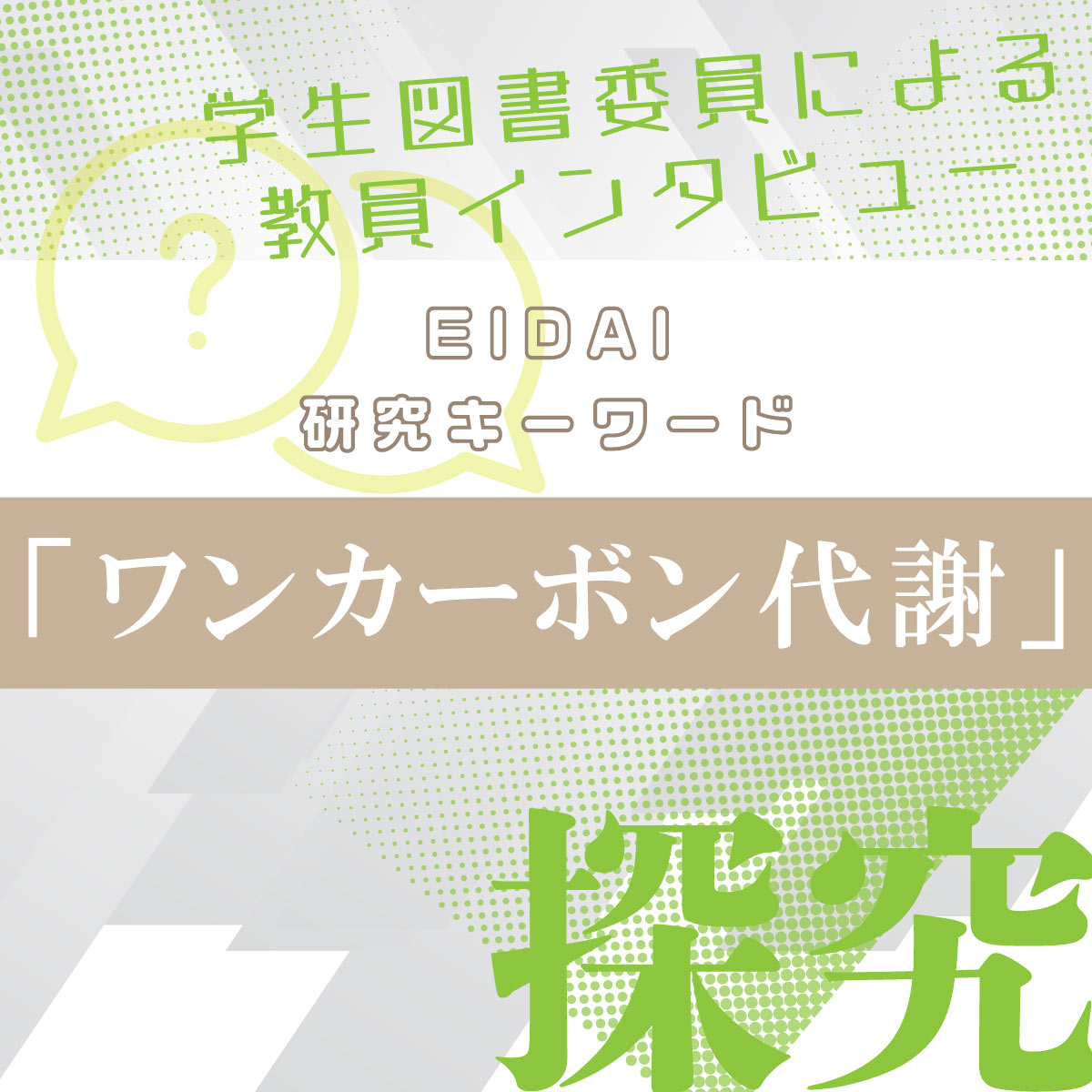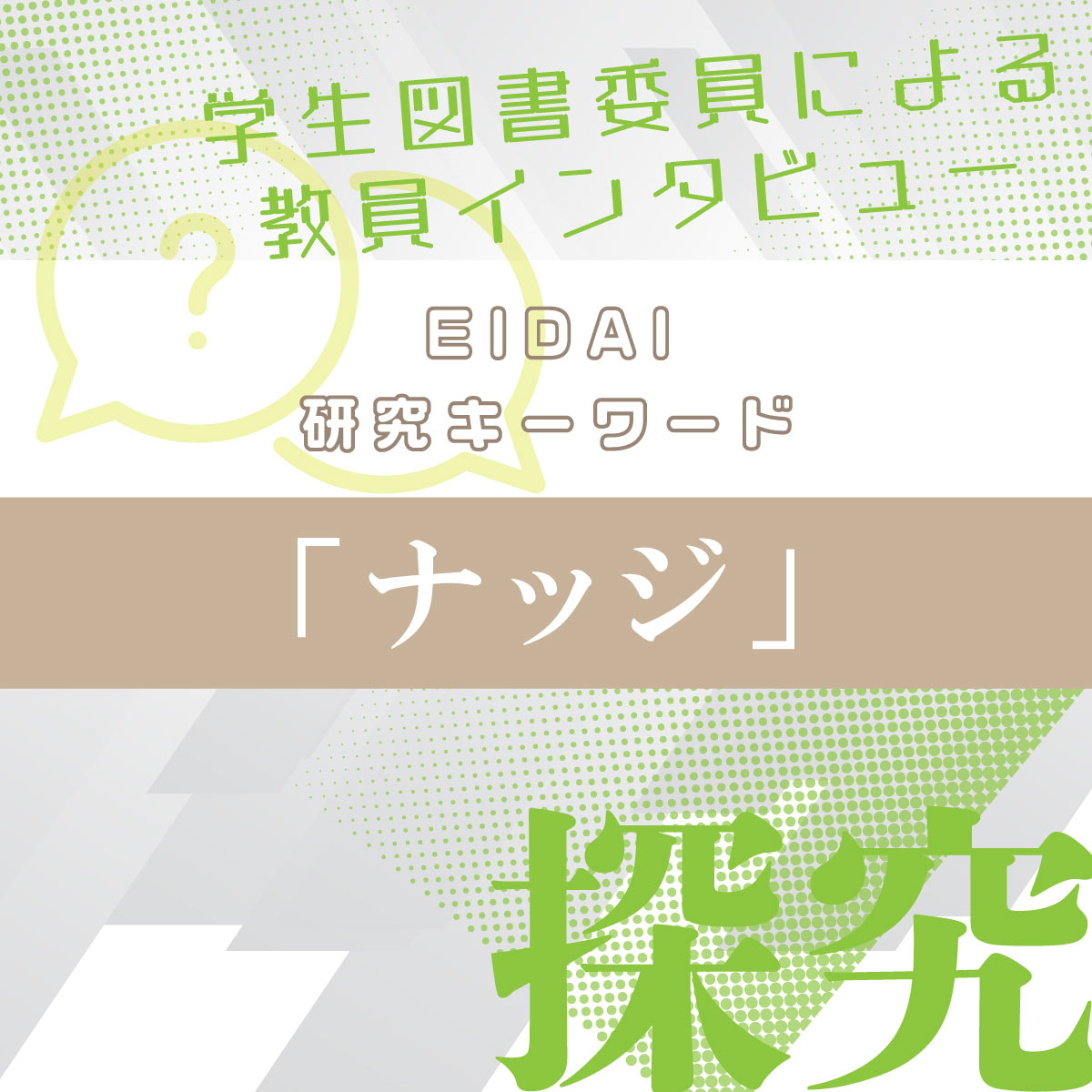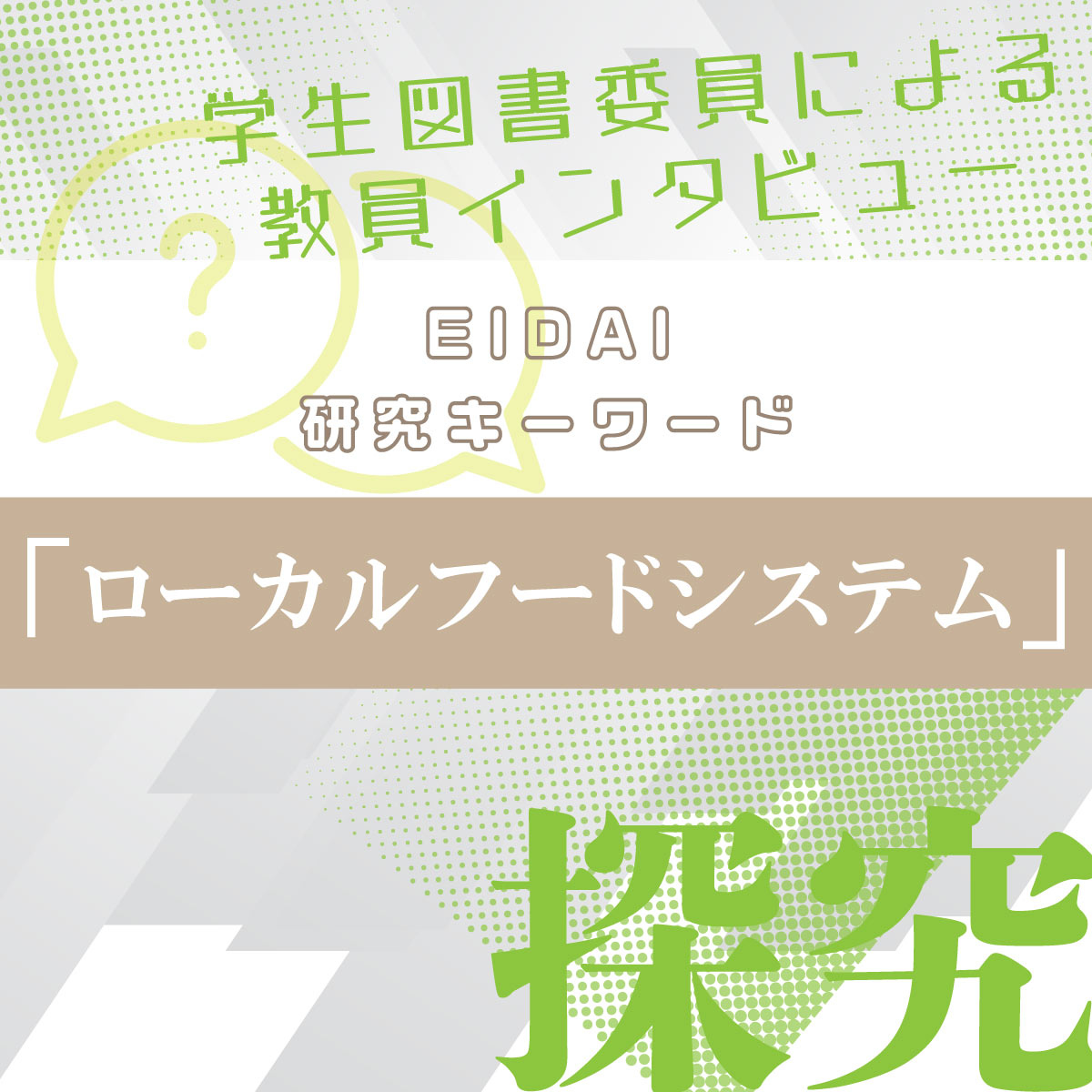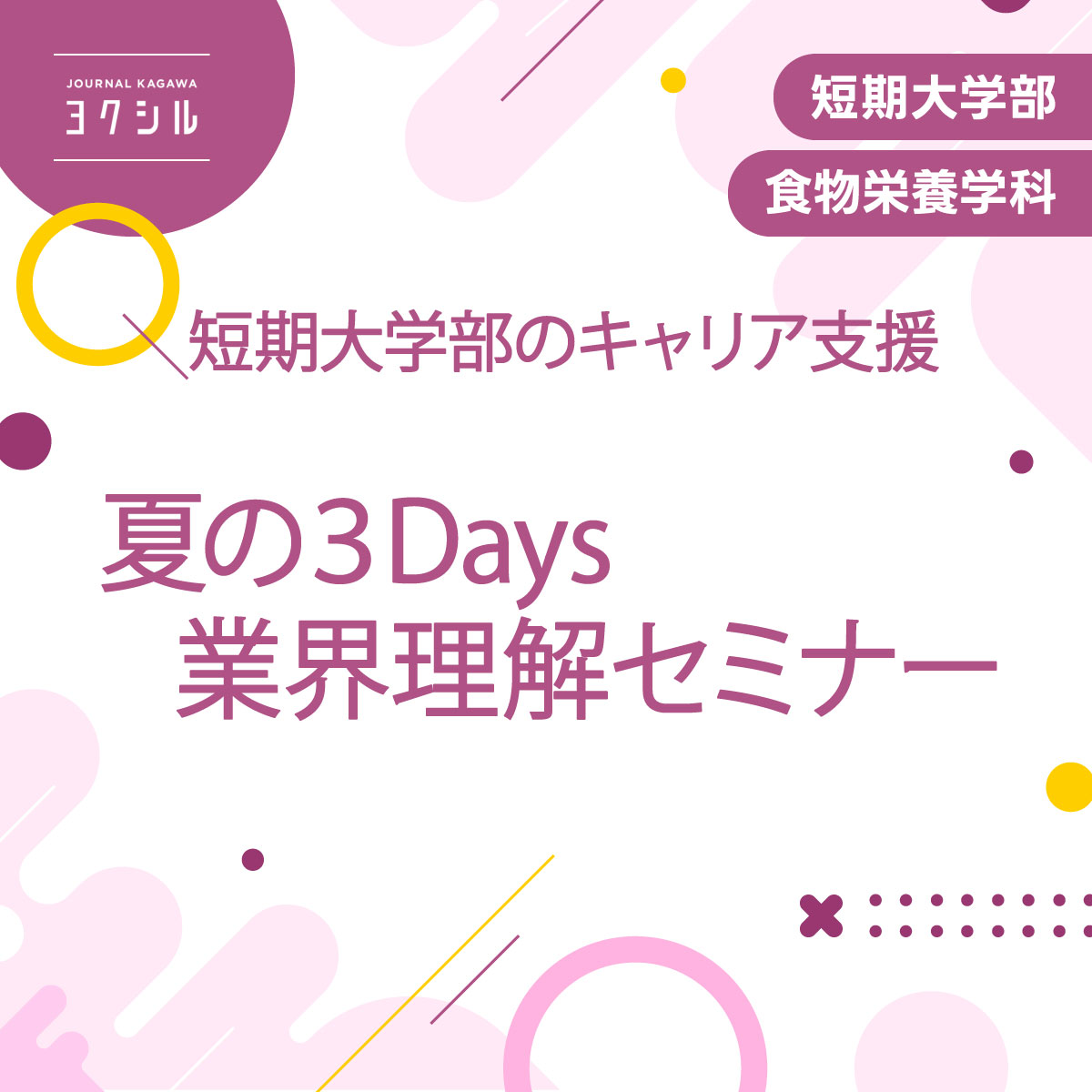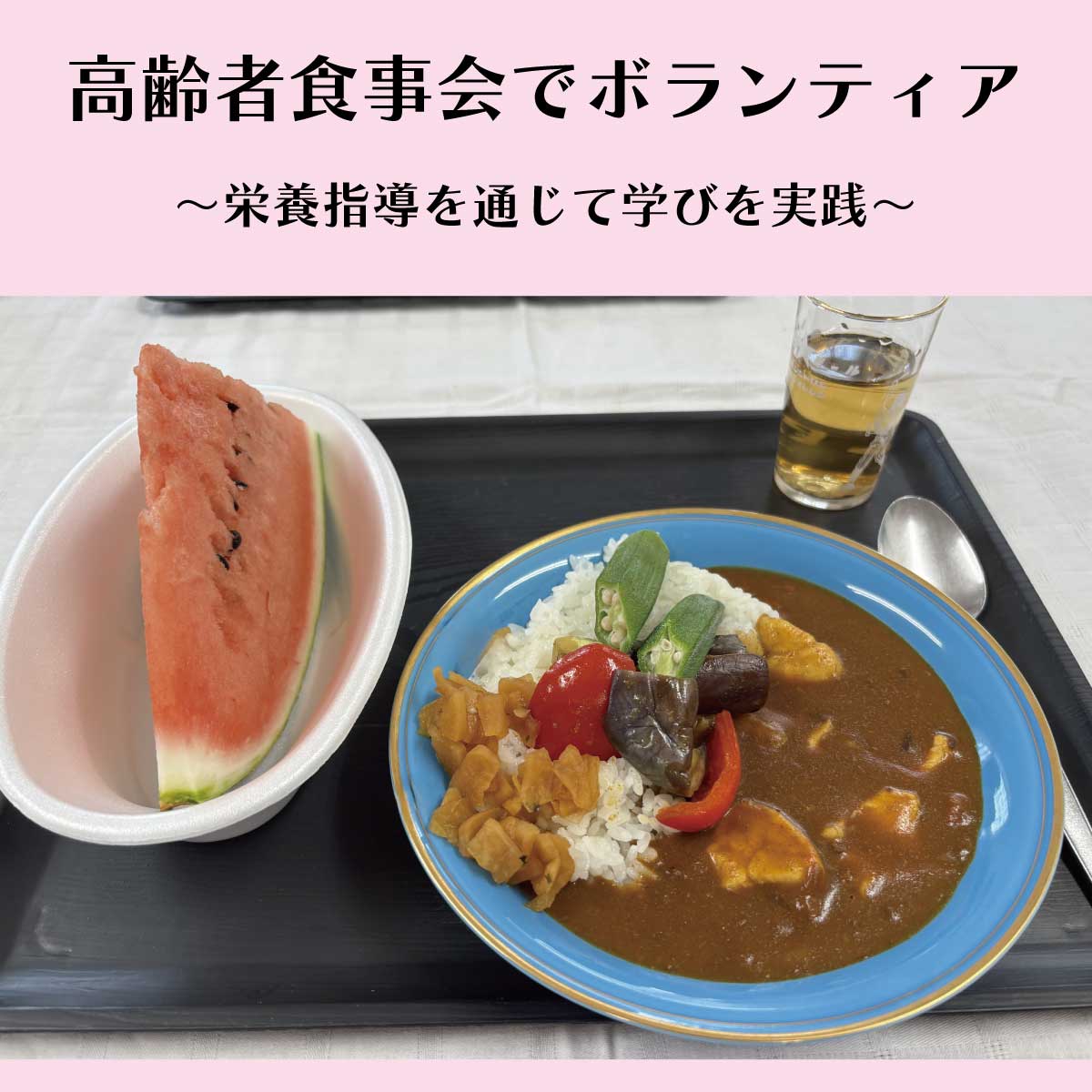私たちは日本に暮らし、日本人の価値観、日本の食文化の中で生活していますが、「日本の中だけではなく、海外の食の多様性についても知り、目を向けてほしい」と考え、食文化栄養学科では、1年次に国際理解論、3年次に国際栄養学の2科目を学科の必修科目として位置付けています。
さらに、3年次からスタートする5つのコースの1つ「食の国際コース」では、食文化等を英語で理解する力と英語で伝える力を身につけることを目指した授業を行っています。

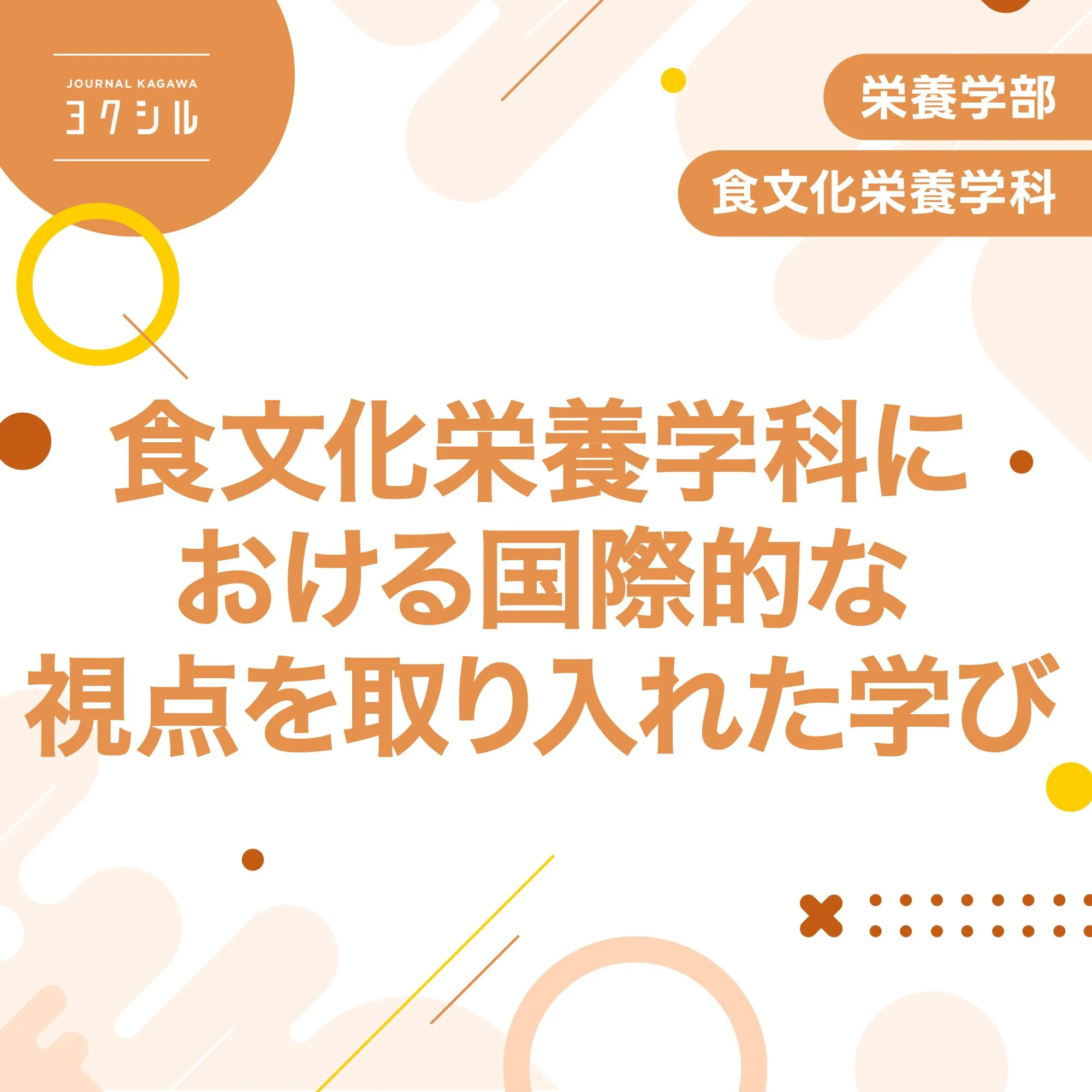
食文化栄養学科
食文化栄養学科における国際的な視点を取り入れた学び

日本の外に目を向け、世界の栄養・食に関する問題の実際を知る
1年次の国際理解論は、日本の外に目を向けてもらうための導入の授業です。海外の家庭の1週間分の食料の写真を見て、想像力を張り巡らせながら、どこの国かをグループで考えてもらうワークをします。またプラスチックごみ、フードロス、水の問題、子どもの貧困や教育問題など、世界で起きている様々な問題をSDGsと関連づけて学びます。学校に行かずに、家族のために1日かけて歩いて水汲みに行く子どもがいるなど、自分にとって当たり前と思っていたことが、世界ではそうとは限らない、という事実に衝撃を受ける学生もいます。
その後、栄養学や食文化について他科目で学んだ後、3年次に国際栄養学を学びます。この科目では、まず世界の栄養や健康に関する現状、栄養・食に関連する国連機関の役割など国際的な動向を学んだ上で、アメリカ、オーストラリア、アフリカ等の各地域や国における栄養・食に関する問題の現状と課題解決のための活動実践例を学びます。事例は、PDCA(計画・実施・評価・改善)サイクルに基づき講義をしており、PDCAサイクルの考え方を学ぶ機会にもなっています。
最初は海外に興味がなかった学生も、徐々に世界で起きている様々な現状を理解し、授業が終わる頃には、「世界には自分が知らないことがあることを知った」「もっと海外にも目を向けたいと思った」と感想を言ってくれる学生も多くいます。
食文化等について英語で学び、英語で発信する
食の国際コースには5つのコース科目あり、食文化等を英語で理解する力をつける3科目、それらを英語で伝える力をつける2科目があります。後者の科目の1つ国際食活動フィールドワーク実習では、現地実習として約一週間ベトナムを訪れます。現地ではベトナム語が使われていますが、現地大学生との交流の際には英語を使って日本の食文化を伝えます。またレストラン等でも英語を使う機会があり、この実習を経験し、もっと英語が上手になりたい、英語を使って海外の人とコミュニケーションを図りたいという気持ちになる学生が多くいます。
4年次の国際栄養教育実習では、日本在住の海外留学生に英語でインタビューを行い、日本の食生活で困っていることや日本の食文化で知りたいことを尋ね、その内容に基づき英語で食育の内容を考え、留学生を対象にその食育を実際に実施します。他科目で身につけた英語力をアウトプットする機会になり、留学生から直接フィードバックをもらうことができるため、学生たちにとっても達成感を感じられる授業となっています。
国際コースの学びから卒業研究へ
食の国際コース科目の1つでもある、3年前期の海外英語語学研修では、休学せずに語学留学ができます。過去には海外英語語学研修で、本学が提携しているアイルランドのダブリンシティ大学の語学学校に留学した学生が帰国後、私のゼミで食文化栄養学実習(卒業研究)を行いました。留学中の実体験をもとに、海外の方の和食のイメージについて調査し、ラーメンや寿司をイメージする人が多いことがわかったため、日本の一汁三菜についてInstagramを使い英語で発信しました。
このように、国際コースの学びと食文化栄養学実習(卒業研究)をつなげる学生もいます。私のゼミを希望する学生のテーマは様々で、国際に関するテーマ以外にも、食育や持続可能な食など様々です。基本的には対象者の課題を見つけ、解決する方法を考えるなど、PDCAサイクルに基づき進めます。また社会の中の誰かの役に立つことを意識してテーマを考え、表現の方法は様々ですが、人々とのコミュニケーションを通じて他者に伝える取り組みを行っています。
食文化栄養学科+国際コースの学びを将来の強みに
食は世界中で通用するテーマであり、食を通したコミュニケーションは万国共通です。また、現在は日本に住んでいても訪日外国人観光客など、海外の方と接する機会があります。栄養学や調理、食文化に関する知識を身につけ、さらに食文化等を英語で理解できるようになったり、英語で発信する経験をしたりすることは、社会に出た際にも大きな強みになると思います。
食文化や栄養学に興味がある、でも英語や海外も好きで進路に迷っている方、食の国際コースがある食文化栄養学科で一緒に学びましょう。
お話を聞いた先生

▲衞藤 久美 先生
【キーワード】
食を通したコミュニケーション、共食、子どもの食生活、ヘルスプロモーション、食育、国際栄養