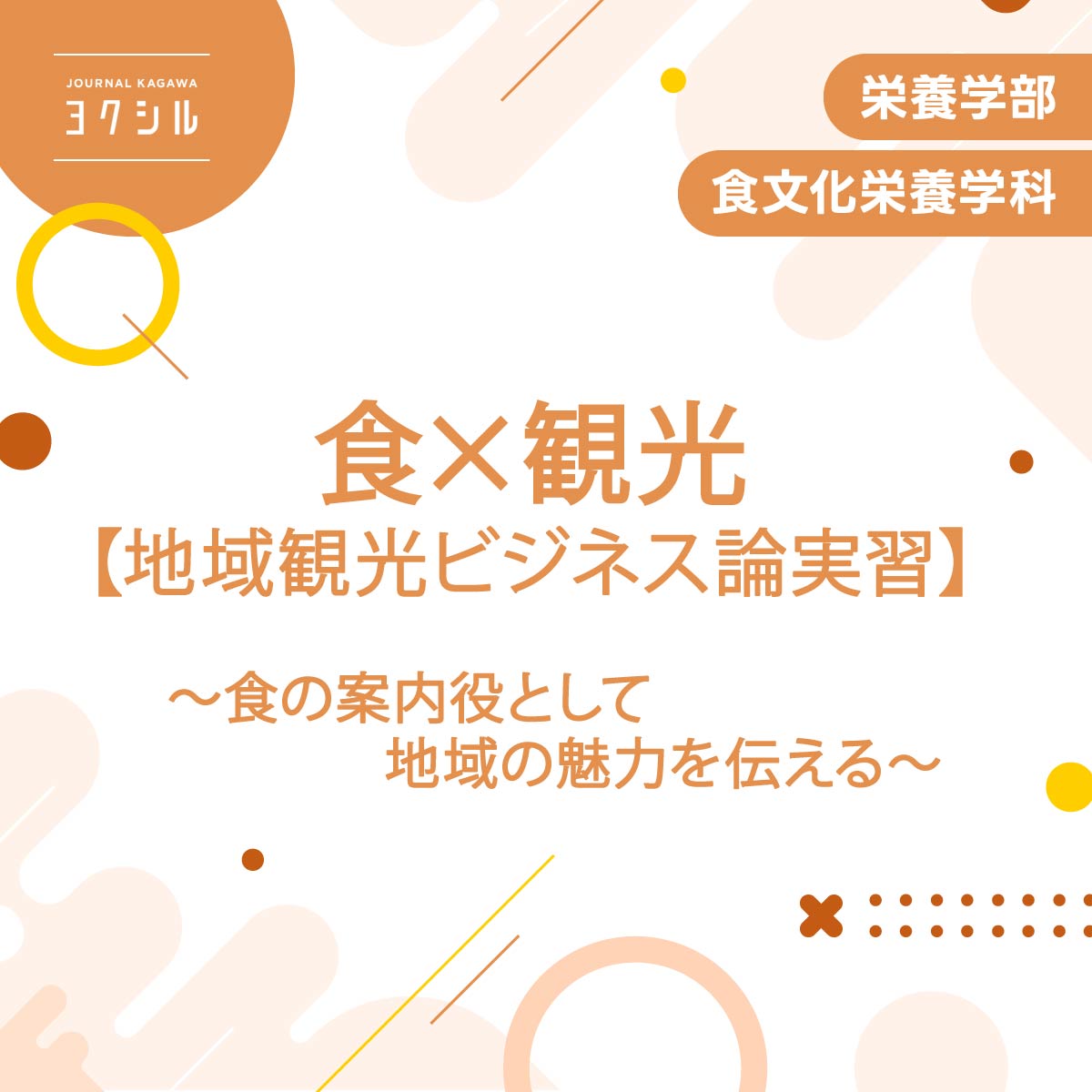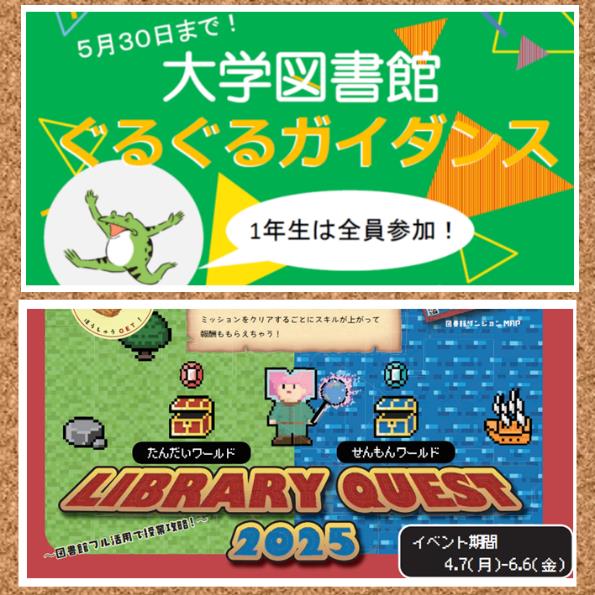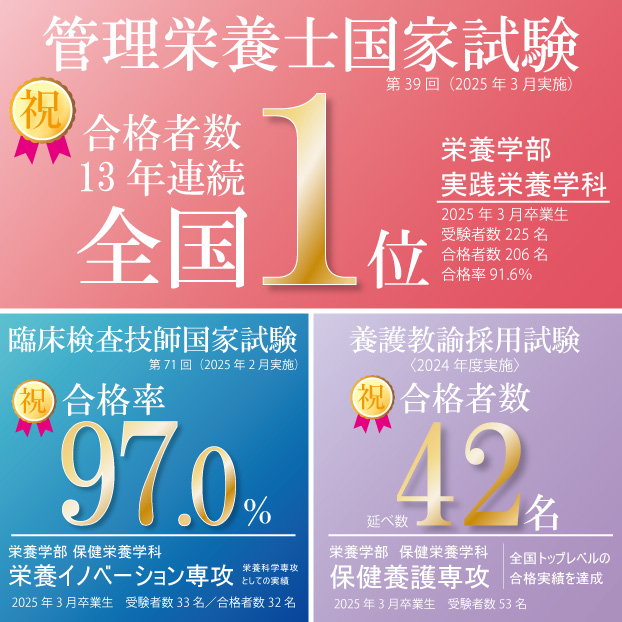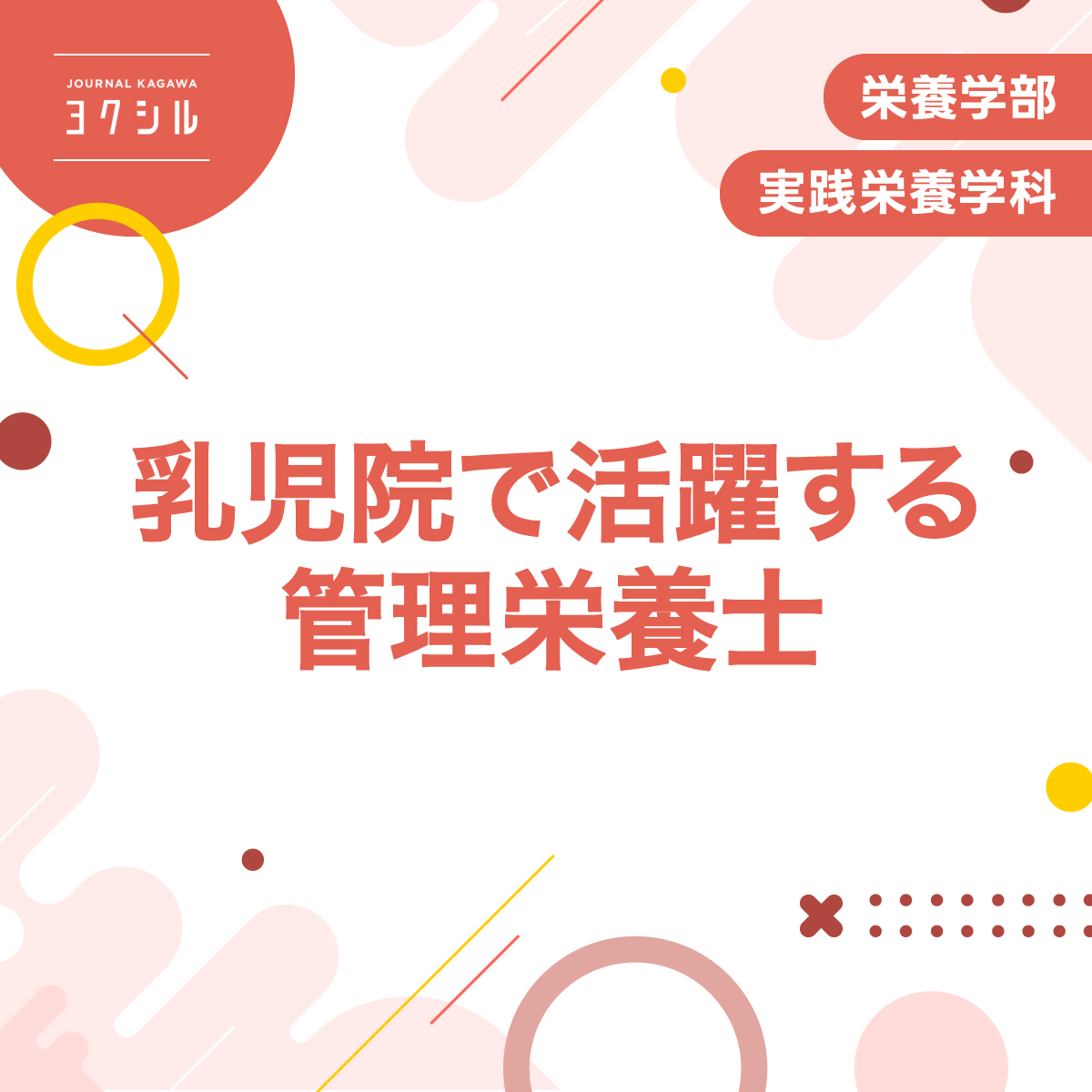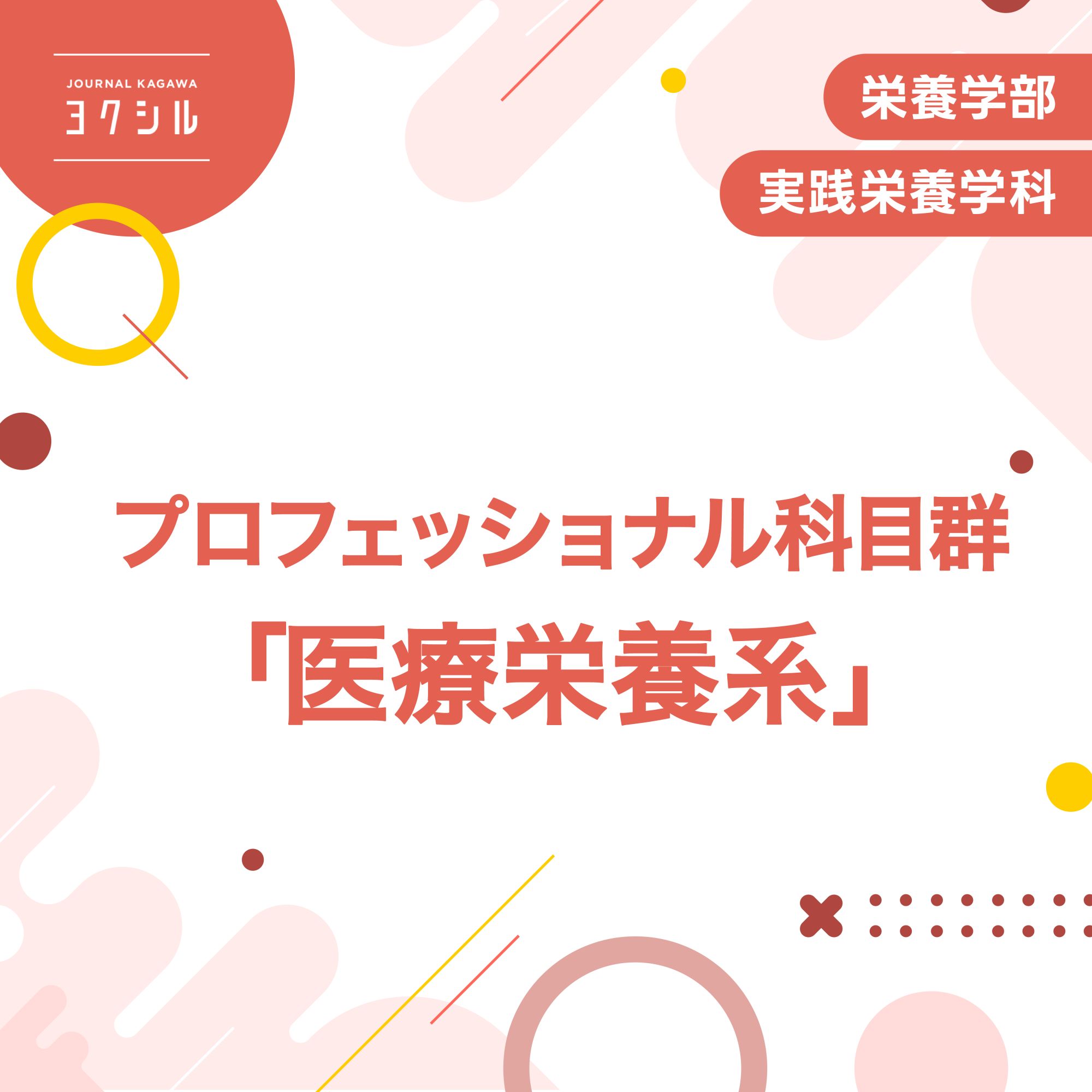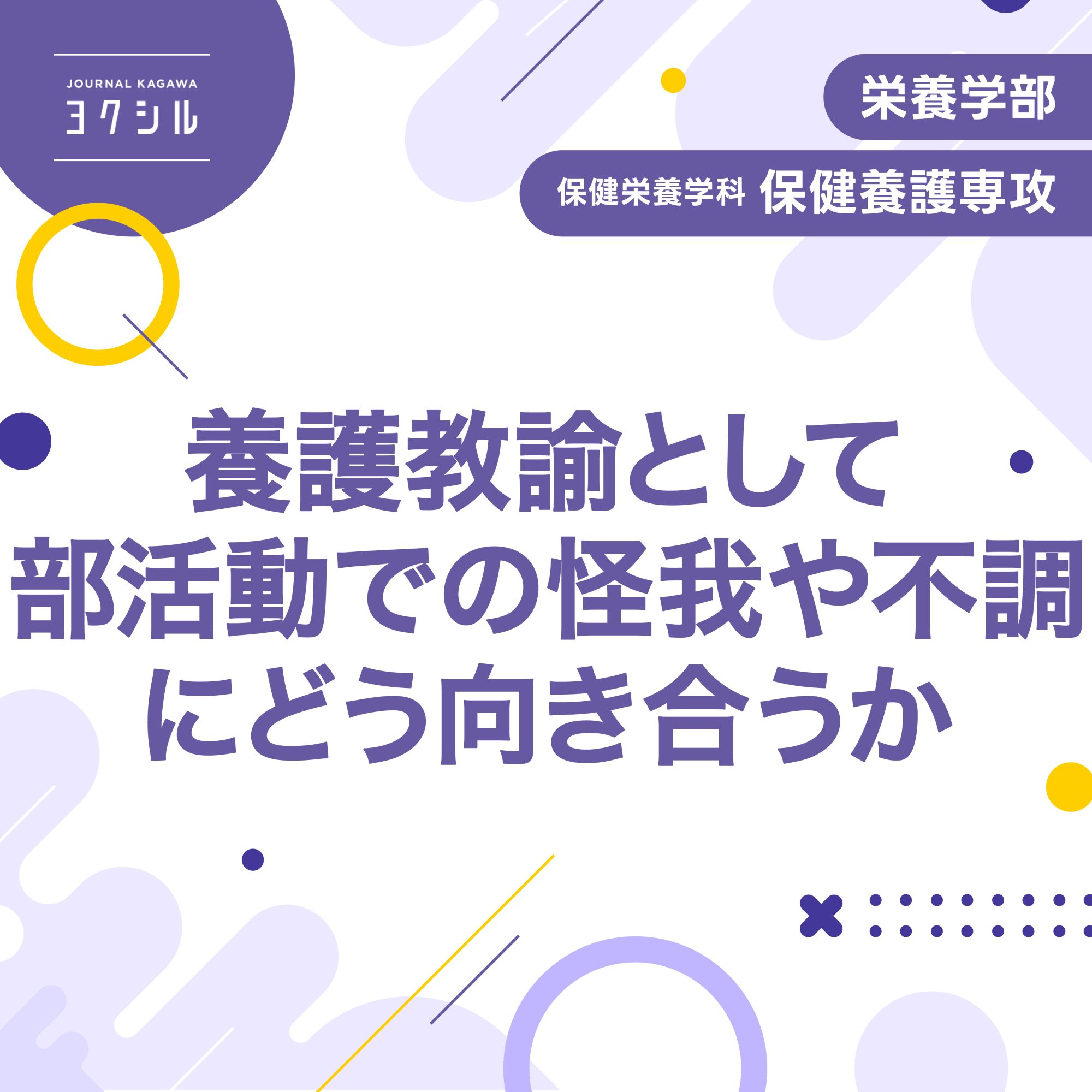保健栄養学科栄養イノベーション専攻には、専門的な学びを深めるための3つの領域があります。その一つであるフード・ウェルネス領域では、栄養学の知識を基盤に、食品の生産から開発、加工、品質管理までを総合的に学びます。特に食品製造や食品開発を中心に、食の安全性や機能性を科学的に探究し、新しい食品の創出に貢献できる力を養います。
また、農業・水産業・林業などの一次産業 から、食品の加工、消費者ニーズを踏まえた商品開発までを幅広く学びます。本学の強みである栄養学を活かして、食の分野を多角的に捉え、変化する社会に対応できる柔軟性を養います。これにより、未来の食品産業における新たな可能性を切り拓く力を身につけることができます。

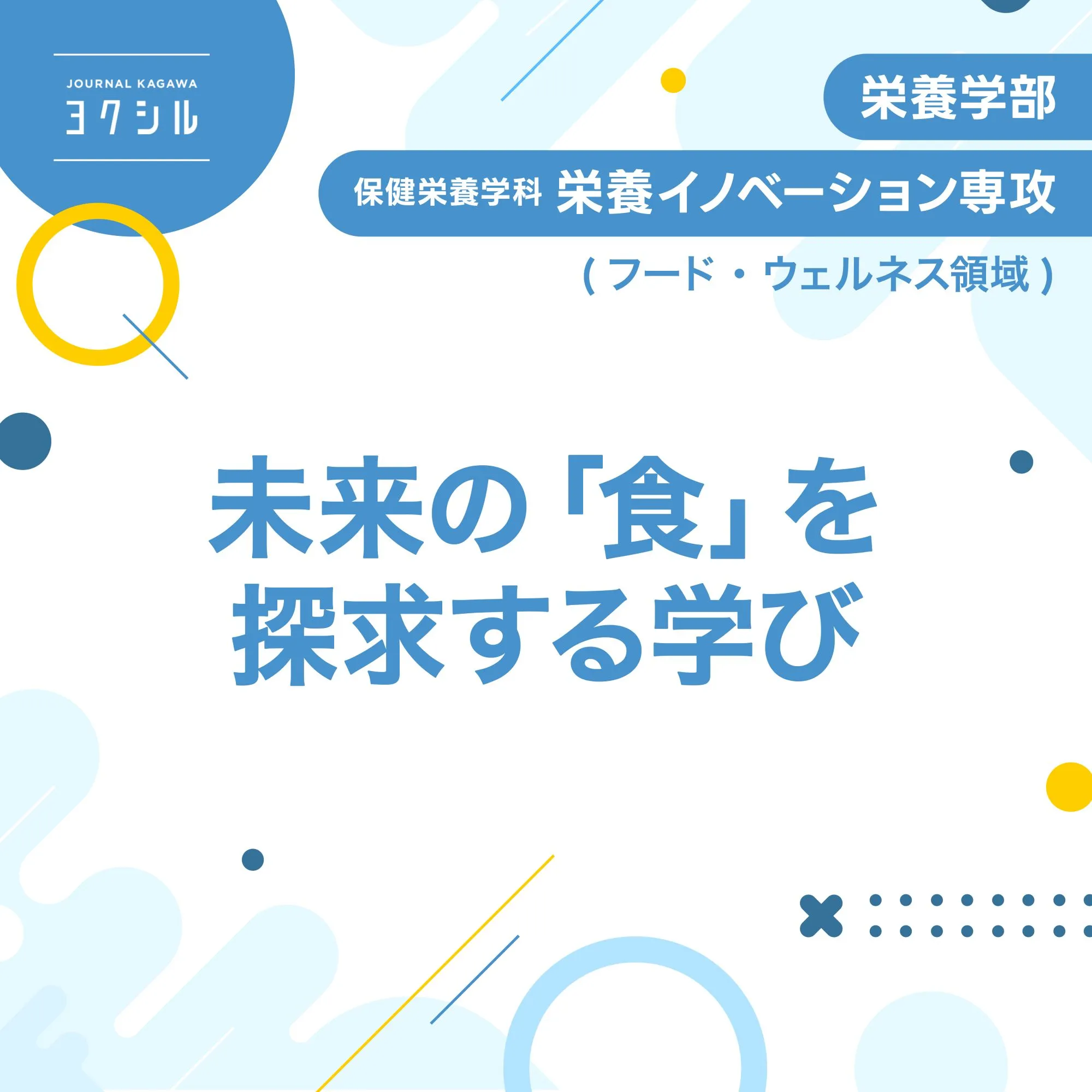
栄養イノベーション専攻
イノベ―ション/食品科学/フードサイエンス
未来の「食」を探求する学び

栄養学の学びを足がかりに「食品」を学ぶ
フード・ウェルネス領域の科目では、本学の特徴である調理学や栄養学などの栄養士資格に必要な科目を学びながら、「食品」に関わる原材料の生産、企画開発、流通、販売、消費などの食品開発や生産のプロセスについて幅広く学び、社会の問題や課題を解決するための考察力を身につけていきます。
各分野の教授陣の授業をはじめ、食品業界で活躍する企業の専門家を特別講師に迎え、最先端の食品開発の現場について学ぶ機会も豊富です。食品の機能性研究や保存技術、品質評価など、実践的な知識を深めます。
生産から消費まで、幅広い学び
1・2年次は栄養士資格に必修の食品学関連の基礎科目が中心ですが、食品開発論で導入を学び、その後フード・ウェルネス論や食品加工学で、応用的な視点を深め、食品がどのように生産・開発され、製品として流通するのかを理解します。
さらに食品分析化学や食品保存技術論、食品加工実習、調理科学実験などを通して、食品の品質や安全性、加工原理を詳細に学びます。また、食品表示・規格論では、食品の法規制を、食品機能研究論では機能性食品の開発について専門的に学びます。
3・4年次は、企業との連携授業や研究を通じて、実践的なスキルを修得します。食品開発・マーケティング論やフードシステム学では、商品開発のマーケティング戦略や研究開発の手法を学び、食品開発の魅力を深く理解します。
食品微生物検査学やバイオテクノロジー概論では、品質管理に関連する食品衛生や食の安全性、有用な微生物や発酵の働きなどについて学びます。食品分析・検査実習では、食品の品質検査に必要な考え方と分析技術を修得します。
近年、食べ物の「おいしさ」 に関する科学的アプローチは、食品の研究や開発において重要視されています。食品官能評価・物理的評価実習では、食品の味わいや食感などを科学的に分析し、コンセプトに最適な調理や加工技術を考える力を養います。
フードPBL演習では、フードサスティナブルの視点を取り入れつつ、問題発見・課題解決型学習として、自治体や社会の組織が抱えるフードシステムに関する課題に対して解決策を考察する力を養います。
視野を広げ、実践を意識した実習と卒業研究へ
企業と連携した実習として、フード・サイエンス実習において、実際の食品開発や製造工程の課題に取り組み、実験と検証を重ね、得られた結果を考察し、解決策を提案します。企業からのフィードバックを受けることで、将来的に食品開発や製造の現場で活躍できる力を培います。
また、本学の充実した研究環境で教員の指導を受けながら、学びの集大成として卒業研究では自身でテーマを熟考し、論文を作成するなど、学術的にも意義のある研究成果を生み出します。
未来の食はどう進化する?— 食の可能性を探究する。
社会が大きく変化し、宇宙での生活も現実味を帯びてきました。そのとき、どのような食品を手にし、それらはどのように作られ、届けられるのでしょうか?
限られた資源の中で安全で栄養価の高い食品を効率的に生産・加工することは、今後ますます重要になります。食品ロスの削減、食糧生産の最適化、作物の廃棄部分の有効活用、新しい食品の開発など、持続可能な食のあり方が求められています。
現在、食品業界だけでなく、化粧品や医薬品メーカー、農業や環境技術関連企業など異業種でも食品開発が進む時代です。学んだ知識を活かせるフィールドは無限に広がっています。
食の生産から加工、品質管理、流通、消費までのプロセスを理解し、課題を発見し、解決策を提案できる人材がこれからの食の未来を支えていきます。
「食」の可能性を探求し、新しい未来を築く学びに、挑戦してみませんか?
お話を聞いた先生

▲西塔 正孝 先生
【キーワード】
Food Science、食品加工、水産食品、タンパク・ペプチド素材、呈味成分