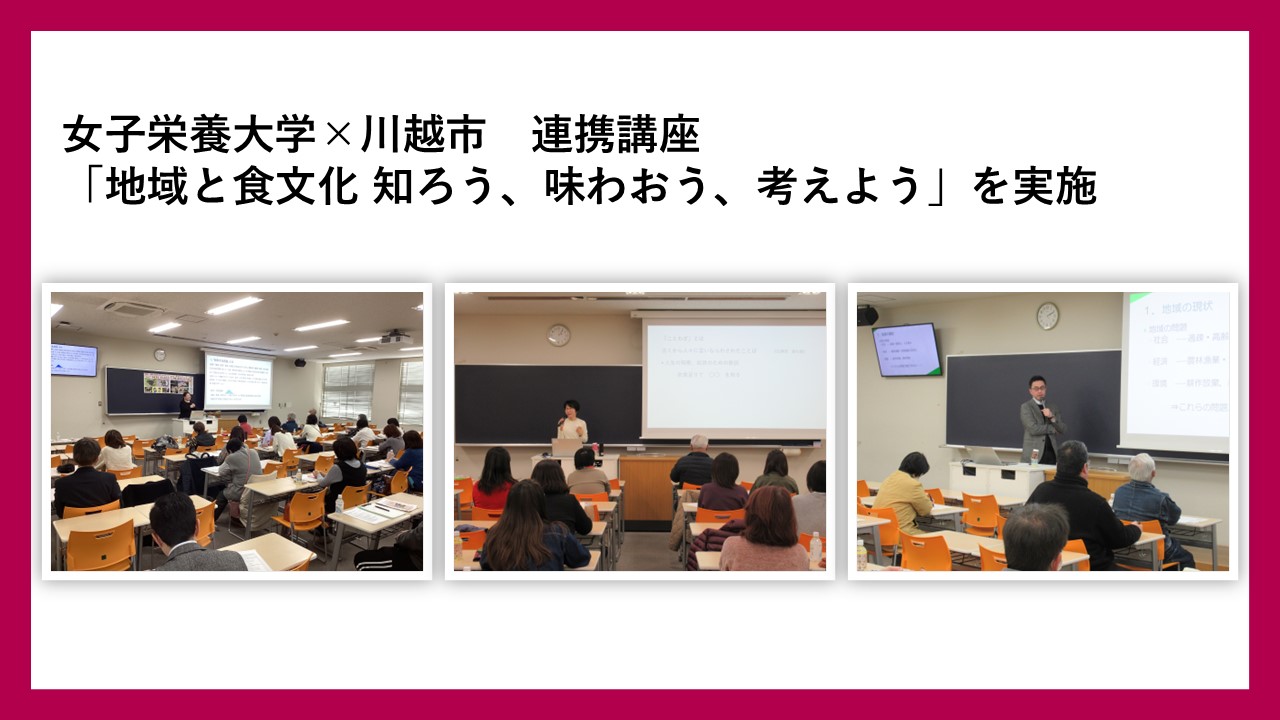
2025.03.06
社会連携
川越大学間連携講座「地域と食文化 知ろう、味わおう、考えよう」を実施
令和7年2月8日(土)・15日(土)・22日(土)の3週に渡り、坂戸キャンパスにて川越大学間連携講座「地域と食文化 知ろう、味わおう、考えよう」を実施しました。
川越市では市民の生涯学習への意欲を応援するために、市内の大学と連携講座を開催しており、包括連携を結んでいる本学も今年度より連携講座の実施に協力することとなり、「地域と食文化 知ろう、味わおう、考えよう」をテーマに、食文化栄養学科の竹内准教授・守屋准教授・平口准教授が講演し、市民の方約30名が参加しました。
初回は竹内准教授が担当され、「無形文化遺産『和食』と日本の食文化」というテーマで講演しました。「和食」および日本の食文化について説明が為され、歴史的な流れとともに日本の食文化がどのように形成されてきたのかを紹介。各地でのお雑煮の違いなどを例に、季節感や年中行事、農山漁村の文化によって食文化が形成されていることなどが解説されました。講義の途中には狭山茶を使ったチョコレートが試食として提供されました。

竹内先生の講演の様子
第2回は守屋准教授が担当され、「ことわざに見る韓国の食文化」というテーマで講演しました。韓国の食文化について、自然環境、社会環境、歴史などを背景に形成され、日本との共通点や独自性などについても紹介しました。韓国食の例として水キムチを試飲してもらい、韓国の諺(ことわざ)に引用されるテンヂャン(味噌)、カンヂャン(醤油)について、韓国家庭における重要性などを解説されました。
守屋先生の講演の様子
第3回は平口准教授が担当され、「食を通した地域振興論」というテーマで講演しました。前半は実際の地域振興活動事例や実習授業の中で学生・教員自身が川越市内で実施した取り組みの紹介と説明が為されました。ゼミの学生が商品開発に携わった「ときがわ山椒」を使ったどら焼きが試食として提供された後、受講者それぞれが「自分が地域でできること」を考え、発表していきました。
3週に渡った講座では毎回活発に質問が出るなど、受講された市民の方々は熱心に講義を受けられていました。
平口先生の講演の様子

