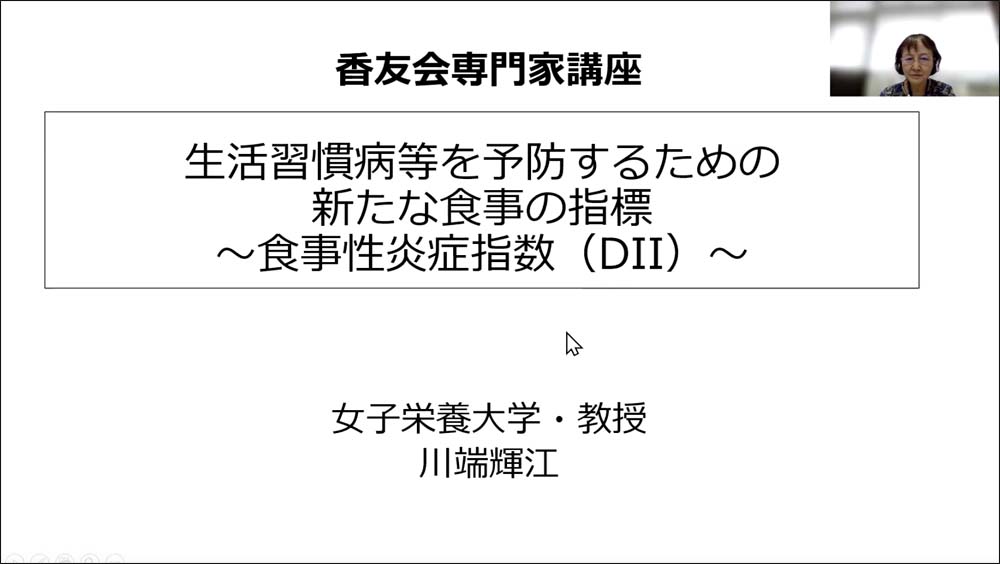 令和7年9月21日(日)14時より、令和7年度第1回「専門家講座」がオンラインにて開催されました。当日は多くの方がライブ配信に参加され、後日オンデマンドでも配信されました。講師は女子栄養大学副学長、栄養学部教授の川端輝江先生です。
令和7年9月21日(日)14時より、令和7年度第1回「専門家講座」がオンラインにて開催されました。当日は多くの方がライブ配信に参加され、後日オンデマンドでも配信されました。講師は女子栄養大学副学長、栄養学部教授の川端輝江先生です。
今回のテーマは「生活習慣病等を予防するための新たな食事の指標~食事炎症性指数(DII)~」です。食事性炎症指数(DII:Dietary inflammatory index)は、2014年にアメリカの研究者によって開発された食事スコアで、数ある食事指数の1つですが、まだ私たちの身近で一般的に使われているものではありません。講座の内容は、
の順で行われました。
まず、DIIの名称になっている「炎症」について、急性炎症と慢性炎症に分けて話をしてくださいました。急性炎症は、けがをしたときや細菌・ウイルスに感染したときに生じる炎症で、普段私たちが生活の中で確認しやすいものです。一方、慢性炎症は軽度の炎症が体内で長期にわたってじわじわと続く状態で、急性炎症のように自覚症状がありません。この慢性炎症が、肥満や動脈硬化などの生活習慣病・心血管疾患・がんなど、さまざまな病気のもとになると説明してくださいました。続いてDIIそのものの内容に入る前に、食事をスコア化することの意義について話がありました。そもそも食事スコアとは何なのかについて、食の「見える化」と単なる「可視化」との違いなど、図表を用いてお話くださいました。また、食事バランスガイドや食のスコア化(見える化)に関する研究についての紹介がありました。
今回のテーマであるDIIについては、その特徴やその算出方法について、とても丁寧に分かりやすく説明してくださいました。DIIは、過去の多量の論文(先行研究)をもとにしていることが強みで根拠がはっきりしている食事スコアであること、食事全体を炎症促進性/抗炎症性でスコア化する指標であること、さらに、DIIに関する論文数は2014年のDII発表後飛躍的に増えていて心筋梗塞やがんなどとの強い関連が示されていることなどが分かりました。また、日本人を対象にした論文はまだ限られていますが、いくつか論文を示していただき、日本人の研究でもDIIが高いほど死亡リスクや炎症マーカー(CRP)が上昇することなどを説明してくださいました。
最後に、実際にどんな食事をするのが良いのかについて話がありました。積極的に取りたい食品や逆に控えたい食品について、ファイトケミカル(野菜や果物、キノコなどの植物性食品に含まれる化合物)や地中海食なども含め説明してくださいました。
講座終了後は質問も出て参加者の皆さまの関心の高さが伺えました。DIIは、まだ基準値がはっきり出ておらず公表されている数値は現時点ではありません。そのため、短時間でおこなう保健指導などでは、すぐには活用しにくいかもしれません。ただ、生活習慣病などを「炎症」という観点で捉え、抗炎症食を意識して指導をおこなったり、普段の食生活に活かしたりすることはすぐにでも可能です。参加者の皆さまの仕事や日頃の食生活にも役立つ学び多い講習会でした。
取材・報告/香友会広報部