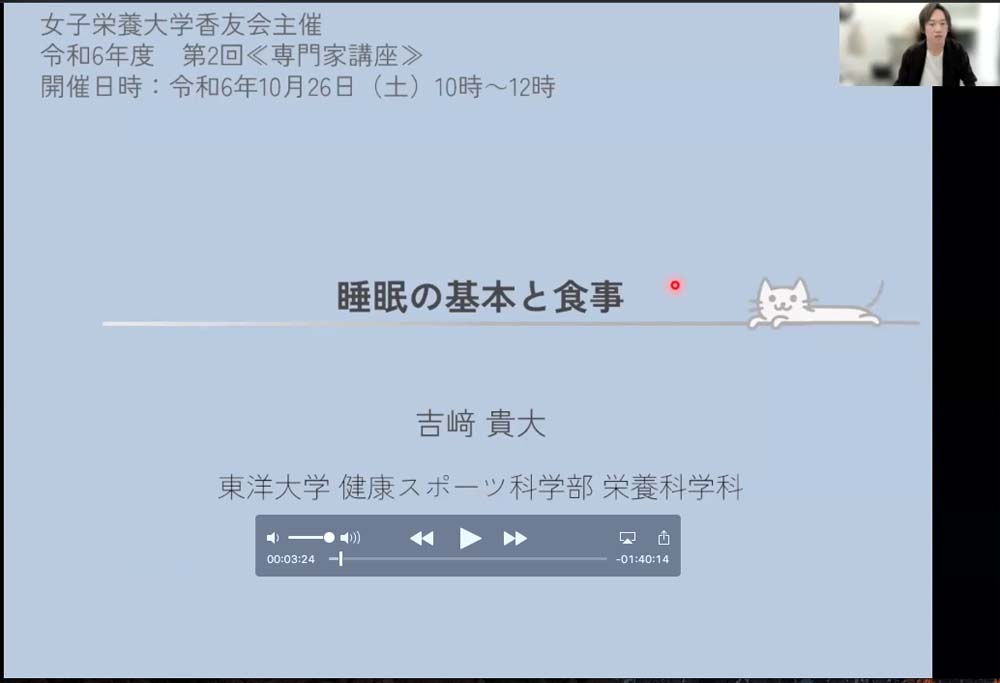 2024年度第2回専門家講座が、令和6年10月26日(土)午前10時よりオンラインライブで配信され、後日オンデマンドにおいても配信されました。
2024年度第2回専門家講座が、令和6年10月26日(土)午前10時よりオンラインライブで配信され、後日オンデマンドにおいても配信されました。
講師の吉崎先生は、東京農業大学大学院博士後期課程を修了され、現在は東洋大学食環境学部の准教授、「健康づくりのための睡眠指針の改定に関する検討会」の委員でもいらっしゃいます。
講演会では「睡眠の基本と食事」をテーマに、2014年から十年ぶりに改訂された「健康づくりのための睡眠ガイド2023(以下睡眠ガイド)」を教材に用い、分かりすく説明してくださいました。
最初に日本人の睡眠状況についてお話しいただきました。「健康日本21(第二次)」の策定時において「睡眠による休養を十分とれない者の割合」は18.4%でしたが、最終評価(平成30年)の報告値は21.7%「増加」となり、目標値として掲げた15.0%を下回ることなく策定時よりも「悪化」と評価され、大変残念な結果となりました。また世界各国と比較して最も短い約1時間短いことが分かってきました。
睡眠時間と死亡や疾病の関連では、睡眠不足は、生活習慣病の発症リスクを高めること、また7時間より少なくても多くても死亡率が上昇することを報告してくださいました。
早急な取り組みの推進が必要であること、健康づくりに寄与する睡眠の特徴を国民にわかりやすく伝え、より多くの国民が良い睡眠を習慣的に維持するために必要な生活習慣を身につける手立てとなることを目指し、最新の科学的知見に基づいた今回の睡眠ガイドが発表されたとのことです。
今回の改訂のポイントは①「睡眠指針」から「睡眠ガイド」に名称変更。「指針」という表現が全ての国民が等しく取り組むべき事項であるという誤解を与える可能性等を考慮したこと。②幼児、大人、高齢者と世代別に最適な睡眠時間や推奨項目の提示。③適正な睡眠時間の具体的数値が示されたこと。④「睡眠時間」に加えて「睡眠休養感」も大事であること、つまり睡眠時間の「量」に加えて休養感という「質」に言及したことです。
睡眠の「質」の部分として、よい睡眠をとる工夫に、睡眠環境づくり(スマートフォンの利用、運動習慣と食習慣と睡眠の関連、睡眠と嗜好品の取り方)も提示されているとのことです。
今回睡眠ガイドには、睡眠と食事について、しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控えると体内時計が調整され睡眠覚醒リズムが整う、夜遅い食事をする場合は夕食を分食(主食を夕食、帰宅後の遅い時間に副食を軽く摂る)とのことでした。ただここで注意しておかなければならないのは、あくまでも食事と直接的な関連を示した論文はごくわずか、食塩摂取量と睡眠についてのみとのことです。朝食・夜遅い食事の睡眠への影響は、体内時計の調整作用を期待して意図されていとのことですので、解釈に注意が必要とのことでした。
一方で運動習慣と睡眠の関係についてはエビデンスが増えており、運動習慣を身に付けることが良質な睡眠の確保に役立つとのことです。今回睡眠障害の定義、就業形態(交替制勤務)と睡眠の関係も明らかにしており、健康づくりのための睡眠ガイド2023は大変興味深い内容になっています。
講演内容をすべて報告させていただきたいところではありますが、吉崎先生のお話をさらに聞きたい方は、先生からご案内がありました「日本時間栄養学会」学術総会(2025年9月5日~6日:高田和子大会長:東洋大学赤羽台キャンパス)にぜひ足を運ばれてはいかがでしょうか。
参考文献:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」
〔取材 香友会広報部〕