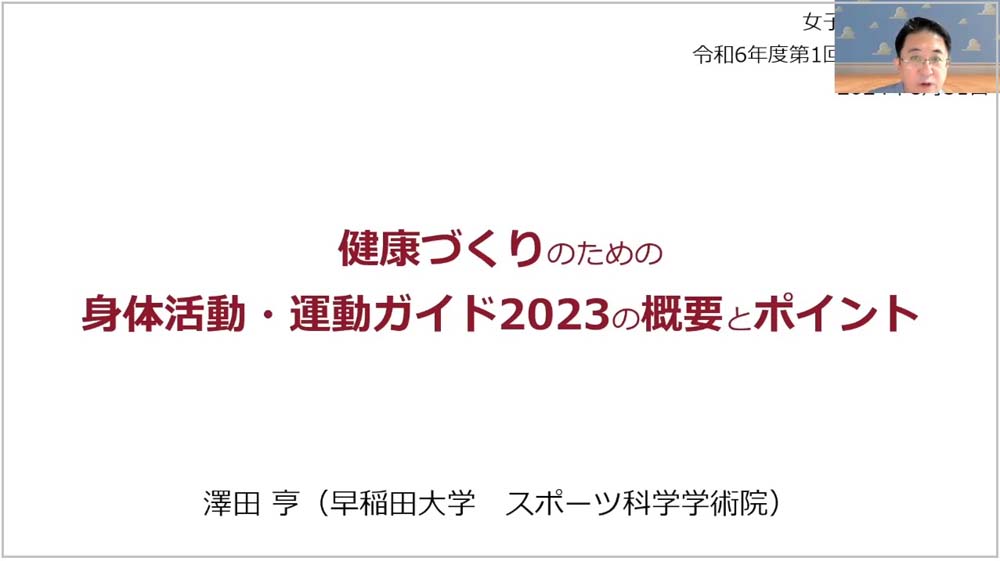
令和6年度第1回専門家講座が令和6年8月31日(土)14時より約2時間、オンラインライブ配信で開催され、その内容は、後日オンデマンドでも配信されました。
「健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会」構成員として改訂に携わられた澤田亨先生を講師にお迎えして「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」の概要とポイントについて解説していただきました。
第5次国民健康づくり「健康日本21(第3次)」が2024年4月より12年計画でスタートしました。「健康日本21」は分野ごとに数値目標を掲げ、エビデンスに基づく健康政策を展開するものです。身体活動・運動分野の目標達成のツールとして「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」が公表されました(2024.2.28)。このガイドは、健康づくりに関わる専門家、政策立案者、職場管理者、健康・医療・介護分野における身体活動を支援する関係者を対象者に、健康づくりのための身体活動や運動に関する推奨事項や参考情報をまとめたものです。
これまで身体活動基準に関して第2次国民健康づくりにおいては「健康づくりのための運動所要量」、第3次では「健康づくりのための運動基準2006」、前回の第4次では「健康づくりのための身体活動基準2013」というように所要量や基準という表現を使用してきましたが、「基準」という表現が全ての国民が等しく取り組むべき事項であるという誤解を与える可能性等を考慮し、今回のとりまとめの名称については「ガイド」に変更となりました。
国際的な動向としてWHOは「2010身体活動ガイドライン」から「2020身体活動・座位行動ガイドライン」に改定しました。2020年版の重要なメッセージは、①身体活動は心身の健康に寄与する②少しの身体活動でもしないよりは良い。多いほうがより良い。③全ての身体活動に意味がある。④筋力強化は全ての人の健康に役立つ。⑤座りすぎで不健康になる。⑥身体活動を増やし、座位行動を減らすことにより、すべての人が健康効果を得られる。の6項目でした。
国際的動向と前回の改定時における課題を踏まえ、澤田先生もメンバーの一員である厚生労働省研究班はガイドライン改定に取り組みました。
「身体活動・運動ガイド2023」における推奨事項の全体の方向性は「個人差を踏まえ、強度や量を調整し、可能なものから取り組む。今よりも少しでも多く身体を動かす」です。そして、その上で、対象者別に独立したシートをそれぞれ作成し、「推奨事項と具体例の説明」「科学的根拠」「現状」「取組むべきことは何か」「よくある疑問と回答(Q&A)」を記載しています。また、筋力トレーニングについても同様にシートを作成して解説しています。
ガイドの改定のポイントは次の8つです。
1)名称を基準からガイドに変更
2)座りっぱなしの時間が長くなりすぎないよう注意喚起
3)成人と高齢者に筋トレ(貯筋)を奨励
4)高齢者に多要素な運動(太極拳・ラジオ体操など、バランスも重要)を奨励
5)働く人が職場で活動的に過ごすためのポイント(昇降デスクの利用等)を紹介
6)慢性疾患を有する人の身体活動のポイントを紹介
7)こどもを対象とした推奨事例を紹介
8)身体活動支援環境の整備が重要であることを示した
また、個別性の原則を踏まえてガイドを指導の場で活用することが望まれます。
ポイントの2)にあるように長時間座り続けないよう注意喚起されていますが、「ブレイク30」と言って、じっと座っている時間を30分に1回は中断することが推奨されています。本講演中も先生から30分ごとに座位行動をブレイク、立って動くことを促されたのが印象的でした。あわせて、高さ40㎝の椅子から片足で立ち上がる「片足立ちテスト」の紹介もあり、立ち上がれなくても立とうとするだけで充分トレーニングになるとのことでした。「片足で立てない」→「両足でも立てない」→「寝たきり」にならないようにと、栄養指導でも筋力の大切さに気づくきっかけに活用できる「指輪っかテスト」の紹介もありました。
なお、一般国民の身体活動・運動の普及啓発を目的とした「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」の改訂については、現在検討中とのことでした。
終了後の質疑応答では、多くの質問にお答えくださいました。
※「身体活動・運動ガイド2023」は厚生労働省のホームページでご覧いただけます。
〔取材 香友会広報部〕