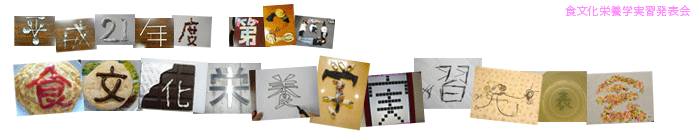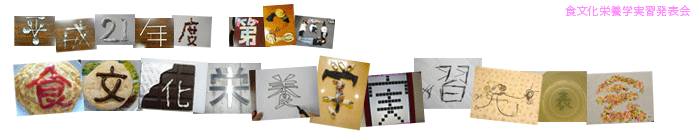|
テーマ / サブテーマ
発表要旨
秋野晃司ゼミ(文化人類学研究室)
韓国の食文化と女性の関わり
韓国料理と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか?キムチ、ビビンバ、チヂミ、トッポギなどでしょうか。これらの韓国食文化形成には、女性が重要な役割を果たしてきました。フィールドワーク・ヒアリング調査を行った結果、儀礼食や家庭料理はもちろん、食堂・屋台での調理、市場での食料品の販売など、食に関わるあらゆる仕事が女性に任されています。この広い女性の領域が女性同士のつながりを強める情報交換の場や楽しみの場となっていることが分かりました。これらの韓国の食文化と女性の関係性について研究し、報告したいと思います。
食を通してみる結婚式の変遷
婚姻儀礼は、時代とともに大きく変化してきました。明治時代からの伝統を引き継いだ1950年代までと、1960年代の高度経済成長期以降では、婚姻儀礼の存在意義がまったく違います。私は、このように変化した背景に興味を持ちました。調査を進めると、婚姻儀礼の変化は婚礼料理にも反映していることがわかりま した。本膳料理からコース料理へ、日本料理から西洋料理へ人気が高まったことで、かつて存在していた「祝いの食材」も見当たらなくなりました。そこで「祝いの食材」の流行や人々のニーズのほかに要因となるものを考察し、婚姻儀礼や婚礼料理が象徴しているものを探究していきます。
日本におけるパンの発展
戦中戦後の日本では、パンは米不足時に食べられる代用食としての役割が主でした。高度経済成長期になると、アメリカから製パン機械や技術が導入され、日本でもおいしいパン作りが可能となりました。これにより好んでパンを食べる日本人が増え、パンの生産量と消費量は飛躍的に増加しました。しかし現代ではパンの需要は横ばい状態にあります。そのため生産者側は消費者の需要を喚起させるパン作りや提案を積極的に行っています。今回の発表ではこうした生産者側の取り組みや、消費者の関心を捉え、現代におけるパンの発展と普及の様子を発表します。
石井和ゼミ(栄養情報科学研究室)
子供のお弁当 / 〜世界から見た日本〜
キャラクター弁当(キャラ弁)の魅力はかわいい、しかし、欠点として親にとっては、キャラ弁作りは時間がかかり作業が細かく作るのが大変で、子供にとっても、場合によっては、泣くほど食べにくいということがわかりました。かわいさと共に食べやすいキャラ弁にする工夫が必要です。海苔の型抜きやおにぎり型などの便利グッズを使用し親も効率よく、子供も食べやすいキャラ弁を考えていきたいと思っています。そして、世界のお弁当(日本以外のお弁当事情や、特徴など)などを参考に、より楽しく食べやすいお弁当を提案していきたいです。
オーガニックライフ始めよう / 〜おいしくてカラダにやさしい食事から〜
普段食事をする時、食べ物を選ぶ基準は何ですか?私は“あなたのからだは、あなたが選んで食べたものでできています”という言葉を本で見つけ衝撃を受けました。コンビニ弁当や加工食品で楽に食事を済ませることも簡単ですが、ただ食べるだけでは本当の健康は得られません。本当の意味での健康な食事とは一体何 がよいのでしょうか?実際オーガニックの料理教室や講習会に参加し、安全性を考えた素材選び、調理技術を磨くことの大切さを再確認しました。私は、食生活を見直し、おいしくて、楽しく心とからだに優しいオーガニックライフを提案します。
NEW 米粉⇔SWEETS
米粉、それはあまり馴染みのないようで、実は昔から日本で使われてきた素材です。文字通り米を粉にしたもので種類はさまざま。上新粉、白玉粉なども米粉の1種です。今回、私はその中でも超微粒子に製粉された米粉を取り上げます。小麦粉の代替としてだけでなく、米粉ならではの良さを生かした和と洋の融合したスイーツを通して、「米」という素材の新しい可能性をもっと広めたいという想いでテーマを決めました。背景にある自給率や安全性にも目を向けて、研究を進めていきます。
体育施設におけるコラムづくり
-
磯田厚子ゼミ(国際協力学研究室)
食と食をつなぐ信頼関係 / 〜フードバンク効果〜
フードバンクとは、様々な理由によりまだ十分に食べることの出来る食品が廃棄される前に、食品関連企業から寄付という形で受取り、様々な福祉施設へ届ける活動である。私は今までセカンドハーベストジャバンの活動をしてきた。その中でフードバンク食品が様々な効果を生んでるのをみてきた。その中でも母子施設に関わることで、母子の関係に変化をもたらし、信頼関係を築く一つの手段になってることを知った。フードバンクはただ食品を届けるのではなく、信頼関係を生むものではないかと考えた。フードバンク食品の力をみんなにも知ってもらえたら嬉しい。
栄大のゴミを削減するには??
私は環境問題について研究し、ゴミ問題に興味を持ち、栄大のゴミ削減に向け調べてきた。学内では普段ゴミを3種類ほどしか分別していないが、実は8種類に業者の方が手作業で最終分別している。昨年度は68964kgものゴミを排出。燃えるごみ(多いのは紙)と生ゴミが、約6割を占めている。そこで、環境に配慮した組織運営の国際基準であるISO14001(環境マネジ??ント規格)を学び、栄大にも取り入れたい!!可能なのでは??と考えた。ゴミ削減を目標に、私なりの環境マネジメントを提案する。環境に対する一人ひとりの意識改善が1番の目的だ。
種子島の黒糖づくりのPR / 〜若者よ、黒糖を食せ!〜
鹿児島県種子島の海沿いにある小さな黒糖小屋、そこに江戸時代から続く手づくり製法で黒糖を作り続けている職人たちがいる。この日本の貴重な伝統をより多くの人、そして若い人達に知ってもらいたい。現在、その独特な風味を生かした黒糖のお菓子製品などをよく目にするようになったが、一般家庭ではなかなか使用されていない。生産者の思いやこだわりと消費者が求めるものとを上手くつなぐことはできないだろうか。販売イベント時に配布するリーフレットなどを作成し、知名度や販促が期待できるようなHPやパッケージデザインの提案をする。
種子島の黒糖づくりのPR / 〜黒糖の食べ方・使い方を提案!!〜
種子島で黒糖が作られていることをご存じですか?私は、鹿児島県の種子島で黒糖が昔ながらの手づくりで作られていることを知り興味を持ちました。実際に現地に出向き黒糖づくりを体験してきました。また、島内で消費されることが多いためあまり知られていない黒糖を島外の人達にも知って欲しいこと。黒糖=お茶菓子のイメージを変えるため、若い層などをターゲットにこんなに手軽に作れるんだ!と思ってくれるレシピを考えました。前回開催された青空市場でリーフレットを配布し、「簡単に作れそう!」「おいしそう!」という声が!
人と人を繋ぐ『農』 / 〜地域に合ったかたち〜
今日、日本の農村部では耕作放棄された田畑が増加している。しかし、そういった土地を都会の人に向けた、クラインガルテン(滞在型の市民農園)やオーナー制度の農園などの農業施設とし、地域活性化に取り組む動きも見られる。だが、想像以上に地域と都会の人々の交流は少ない。より多くの交流を生むためには、どういった工夫が必要か。また、それぞれの地域に合った活性化のかたちとは何か。栃木県真岡市を例として、既存の農業施設に私なりの工夫点をプラスし、交流に特化した、農業を媒体とする地域活性化を提案する。
スーパーにあるの? “朝市”的魅力 / 〜地域との繋がり〜
朝市の魅力とは「新鮮・安心・安全・安い・季節感・売り手と買い手の繋がり」と私は考える。千葉県勝浦市の朝市は活気があった。地域住民にとって昔から繋がりの深い存在であり、現在では新しい目的で市を利用している人もいた。スーパーの青果コーナーでは最近、生産者の顔写真や名前入りの売り場を目にすることが多くある。朝市が希少な流通形態となっている埼玉県のスーパーではこのような“朝市的要素”が盛り込まれているのか、また担えるのか。そして消費者はそれを求めているのだろうか。現代型朝市の在り方を提案する。
NERICA大解剖! / アフリカ人とおこめ
インドと共に米の2大原産地であるアフリカ。そのアフリカの貧困改善対策として始められたのがネリカの普及支援。ネリカはアフリカと日本の米をかけ合わせた新種の米であり、熱や乾燥、病害虫に強いとされている。2005年ギニアでは83kg/年/人の米を消費しており、日本人の61kg/年/人を上回っている。現在米の需要は年々伸びており、生産が追い付いていない。ネリカで貧困改善できるのか!?私なりの答えを出すべくネリカの栄養成分分析を実施。成分表記載の米よりミネラルが豊富であることが分かった。官能評価も行い食味についても分析。ネリカ大・解・剖!!
African Power Food / −知れば食べたくなる、作りたくなる−
日本でアフリカ料理が広まらないのはなぜだろうか?私の研究はこんな疑問から始まりました。それは、私たちとアフリカとの接点が非常に少ない状況にあるからだと知り、「接点作り」を最終目的とし取り組んできました。 アフリカ関連のイベント参加、アフリカ料理店訪問、ケニアでの現地調査から実際に触れた食文化、レシピコミュニティーサイト「COOKPAD」へのレシピ掲載や学内での試食会を通してどのような反応が見られたか、その実験結果をお伝えします。 今まで食べたことのない味に出会えるアフリカ料理、一度体感してみませんか?
磯田厚子・千葉宏子ゼミ(国際協力学研究室)
チョウリシカ攻略法 / Restaurant Little Chef
3年時の1年間、Wスクール制度を利用して調理師科に通った。しかし、そこに至るまでに多くの不安や焦りがあった。ゼミや授業、就職活動…。これから調理師科に行こうと思っている人、興味のある人たちのために不安を和らげられるよう、情報を提供したい。また、その調理師科での様々な学びを基に「料理は美味しいだけではなく、感動を生む!!」をコンセプトとしてレストラン経営を行った。私は、チョウリシカ攻略法と題して、すべての不安要素をまとめるとともに、調理師科での学びを生かしたゼミの活動をまとめた冊子を作成する。
Chef’sコーディネート / Restaurant Little Chef
Restaurant Little chefeは調理師科で学んだ5人で経営しているレストランです。6月の西洋料理に引き続き、中華・日本・フランス料理を提供しました。私達は、食文化や季節をテーマにコーディネートを研究しています。各国の料理に合ったコーディネートを考え、手作りの箸袋を作るなど工夫してきました。食空間では各国の特徴を伝えるためメニューカードや、中国茶器を使ったデモンストレーションを行いました。発表では、今までのコーディネートの内容とそこから学んだコツを説明します。また、デモンストレーションも行ないます。
地域野菜化計画 / Restaurant Little Chef
私は調理師専門学校で学んだことを生かして学内レストランを営業しました。料理に地域の食材を使うことで坂戸産のあまり知られていない野菜や生産量の多い食材を地域に広めていく事が目的です。レストラン営業では日本料理でそうめんかぼちゃを椀盛りに、西洋料理で坂戸産の小麦粉を使ったパンを製作し、中国料理でカブや大根など新鮮な野菜を使用しました。アンケートで坂戸産のほうれん草が有名であると知りディナー料理に取り入れました。更に農家の方のインタビューや坂戸産の食材を使ったレシピを入れたリーフレットを来店されたお客様や直売所に配布しています。
レストラン食After。。。 / Restaurant Little Chef
"記念日やクリスマスなど特別な日に素敵なレストランで食事をする。誰もが一度
は経験があるようなことですが、食事をした後につい気になってしまうことって
ありませんか?こんな食べて体重は増えてしまわないのか、明日は普通にご飯を食べて良いのか…栄養学を学んだ私自身不安になることがあります。このテーマでは日常的な生活での栄養学に関する理解を広めることを目的とし、レストランなどの本格的なフルコースを食べた後、気になる栄養的な面について次の日の食事のメニューの提案などわかりやすく解説するリーフレットを提案します。"
五明紀春ゼミ(食品機能学研究室)
ジャムの眼 / 〜もっと愛して〜
皆さんはパンを食べるとき何を塗りますか?多くの人はジャムやバターと答えるのではないでしょうか。私は普段何気なく食べている“ジャム”についてスポットを当ててみようと思いました。ジャムは保存性と素材の風味や色、香りを生かした身近な食品として、世界中で愛好されています。近頃では、食生活の多様化から保存食としてではなく、甘さを控えたものや虫歯になりにくい健康を考えたジャムも開発されています。私は多種多様なジャムを使い、和食や洋食を作ってみました。また、世界中の珍しいジャムを紹介したいと思います。
おからのある生活 / 〜食う・使う・楽しむ〜
産業廃棄物として捨てられる運命にある「おから」。そんなおからを「いつ見ても冷蔵庫にある卵」のような存在にしてあげたい、と思いテーマに取り上げた。実は魅力たっぷりなおから。食物繊維も豊富で生活習慣病の予防にも効果的。昔ながらの調理法や、おいしくて誰にでも作れちゃうレシピの考案、さらに、食べるだけでなく「こんなことにも使えちゃう!」というような驚きの利用法を考えることで、おからの魅力を余すことなく伝えていく。こんな私が「どこの家にでもおからが存在すること」を目指す、「おからのある生活」を提案していく。
青島みかんファイト!! / 〜静岡県産の魅力を再発見〜
みかんはお茶と並んで静岡県を代表する特産物です。しかし、大学に入学し静岡県出身だと話すと「お茶おいしい?」と聞かれることが多く、それほど有名ではないのかと感じました。しかし、平成19年の静岡県産みかんは生産量、出荷量ともに日本一。また、静岡市で発見された主力品種でもある青島みかんは全国的にも栽培されています。そこで、この実習では静岡県産みかんの知名度をアップさせ、地域発展につなげていく方法を考えていきたいと思います。そして、静岡県産みかんの魅力を伝えたいと思います。
れんこんでイキイキ!! / 〜茨城のれんこんを身近に〜
茨城県の特産物は?と聞かれて思い浮かぶものはなんでしょうか。他の県と比べるとなかなかすぐには浮かんでこないのではないでしょうか。私の生まれ育った茨城県は日本一のれんこんの産地なのです。低湿地帯でれんこん栽培に適しています。私の両親も茨城県で生まれ育ったためよくれんこん料理が食卓に並んでいました。幼い頃からよく食べていた身近な食材でとても好きなものでした。皆さんにもれんこんを身近に感じてもらえるようれんこんの加工品やレシピを紹介していきたいと思います。
ヘチマに恋して♪Fall in LoVe / 〜食べ方&知名度UP大作戦〜
みなさんはヘチマが食べられるって知っていましたか?ヘチマと聞いて思いつくのは有名な“たわし”や“化粧水”だと思います。しかし、私が生まれた奄美諸島の徳之島や沖縄県、海外の南地方ではヘチマを食べています。たわしを食べるの?なんて思っていると大間違い。たわしにする前の若い実を食べます。トロリとしていて甘く、食感は冬瓜とナスの間くらい。実はとてもおいしい野菜です。料理法は、沖縄で有名なチャンプルー、みそ汁に入れたり天ぷらなどにしたりします。今後はヘチマ料理のレシピを提案していき、ヘチマは“食べられる”ということをみなさんに知ってほしい。
お茶漬けと私のラブストーリー / 〜究極のお茶漬けを求めて〜
日本人の食事にかかせないご飯。白いご飯を食べるより味をつけて調理されたご飯の方が箸も進みます。そんな中、お茶漬けは忙しいときにでも手軽に食べられ、尚且つより美味しくご飯が食べるための手段でもあります。江戸時代から現代に至るまで人々に愛され続けてきたお茶漬けにスポットをあて、お茶漬けの歴史、市販品、専門店などの調査に加え、実際に食品メーカーへの訪問をします。お茶漬けのいろはを調査した上で、お茶漬けをより美味しく食べてもらえるよう私なりに考えたオリジナルな究極茶漬けを創作していこうと思います。
梅toゴールイン☆ / 〜梅をプロデュ―ス〜
私の食生活には梅が欠かせません。よりおいしく食べるにはどうしたら良いのか?と考え、このテーマにしました。まずは、市場調査から始めてどんな梅の商品や梅料理が販売されているか、などを追及し、最終的には、そこから梅が苦手な人でも食べられる自分なりの梅料理や梅スイーツをプロデュースしたいと思います。
NO MILK NO LIFE / 〜牛乳のすすめ〜
NO MILK NO LIFE (牛乳のない生活なんて考えられない!)私は常にそう思いながら生きている。しかし現在、牛乳の出荷量、消費量が共に減少している。それに加え飼料価格の高騰により、牛乳自体も値上がりしている。これからも牛乳を安心して飲み続けるために、私たちができることを提案したいと思う。他にも牧場や牛乳工場を写真を織り交ぜて紹介したり、牛乳の味が苦手な人のために牛乳を使ったオリジナルドリンクのレシピも紹介し、牛乳を飲まない人たちが少しでも牛乳に関心を持ってもらえるような発表にしたい。
チロルの窓 / 〜チョコレートの現在〜
中間発表では、私が一番大好きなチロルチョコに絞り込んで研究を始めました。チロルチョコレートの歴史的背景から浮き彫りされた特徴、現在との比較、生産流通の流れ、作られた理由等色々な視点から調べてまとめてみました。後半の発表では、中間発表の補充調査を行うとともに、調査に基づいてチョコレートの駄菓子としての位置等を自分なりにまとめて発表していきます。
米 / 〜江戸・現代を通して見つめる〜
私たちの食生活に欠くことのできない米。米は日本で高い自給率を誇り、昔から主食として食べられてきました。江戸の食文化を背景に当時の人々にとってのお米の価値、あり方、どのようにして食べられていたのかを探求し、それを踏まえ現在にどうつながってきたのかを調べ、当時と比較し、現在の人々にとってのお米 とは?その価値あり方を調べ、今一度お米というものを多くの人に見つめなおして欲しいと思います。また、お米の新しい視点、お米の様々な可能性を見ていきます。
らいふすてーじ弁当 / 〜幸せいっぱい食べて欲しいお弁当〜
最近、スーパーなどに並ぶお弁当の多彩さには目を見張るばかり。お弁当は私たちの日常生活に急速に浸透して来ています。そのお弁当をじっくり見たことはありますか?一見多様に見えるお弁当も似たり寄ったり。なぜ似たお弁当が多いのだろう?あらゆる人たちが弁当を利用する時代、もっと対象年齢を分けたお弁当があってもいいのでは?と考え始めたのが研究のきっかけでした。1弁当の対象年代、2弁当へのニーズ、3ライフステージの見直し、4ライフステージ別のお弁当提案など、人の成長段階というフィルターを通してお弁当を見て研究していきます。
島崎とみ子ゼミ(調理文化研究室)
日本における中国料理
私は3年生になる春休みに中国料理研修に参加しました。そこで中国の魅力を知りました。さらに中国を深く知り、その魅力を多くの方に伝えたいと考えています。中国の良さを中国料理の観点から調べています。第1回発表会には日本における中国料理の調理法を主に調べ、明治、大正、昭和、平成にかけて、煮物や炒め 物が多いことを発表しました。本発表では中国四大料理の食材を4群に分けて、食材、調味料や香辛料などからみた地域の特徴を発表します。実際に北京、上海、四川に訪れたので感じたことを交えながら最終的に中国の良さを伝えたいと思います。
精進料理
精進料理は、植物性の材料のみを使って作られる料理。その味付けや調理法には、さまざまな工夫がおこなわれていることがわかりました。私は茶道をやっていることから、特に茶道とのゆかりが深い大徳寺の精進料理に興味をもちました。そこで、京都にある大徳寺の精進料理店「一久」へ、精進料理を食べに行きました。実際に食べた料理の栄養価を計算し、どのような特徴があるのかを調べました。現在の日本料理の成立に影響を与えてきた精進料理。その根底にある料理を作る際の心構えは、現代においても通じるものがあると思います。
アフタヌーンティーで日本に潤いを・・・
アフタヌーンティーの習慣は、優雅で、ゆったりとした時間を過ごせるものです。この習慣は、イギリスの、上流階級の間で、社交や腹もたせの意味で広まりました。また、現状としては、イギリスでも、日本でも正式なアフタヌーンティーは、専門店で行われていることがわかりました。そこで、日本でも、馴染める、現代風アフタヌーンティーを提案し、実践しました。お茶とお菓子を介してゆったりとした時間を過ごすことで、日本に潤いを与えるものとしてアフタヌーンティーが普及すればと思い研究しています。
高城孝助ゼミ(フードマーケティング研究室)
売れる!食品スーパーの工夫!
最近のスーパーの商品の陳列の仕方は大いに変化を遂げている。陳列棚に種類ごと陳列したり、特売商品を山積みにする売場つくりは従来からあるが、最近良く見かけるのが「食事のメニュー提案」を促す「クロスマーチャンダイジング」という売場つくりだ。これは一体どういう売場なのか。例:鍋の食材(野菜、きのこ)と同じ陳列棚にスープ(キムチ、豆乳、ちゃんこ)が一緒に並んでいる。食品という「モノ」を通して食事という「コト」を生み出すクロスマーチャンダイジングの実態を探る。
Substitute food / 〜代用食品・料理を考える〜
小麦粉の高騰により、米粉が注目され、給食のパンに米粉パンを導入した学校があるそうです。このように、本来の食材を使わずに他の食材をもちいて作られる代用食品は戦時中から数多く存在しています。現代においてはダイエットブームの影響でカロリーを抑えるための代用食品が出回っています。時代背景によって目的を変え求められ続ける代用食品の過去、現在とを比較し、実際に代用食品作りに挑戦します。当日は試食も行う予定です。それらをふまえ、最終的に、今後求められる未来の代用食品を考えていきたいと思います。
野菜をもっと美味しくたくさん食べよう! / 〜ネピュレを利用したグラタン・菓子の開発〜
日本人の野菜摂取量は昭和60年をピークに減少を続け、平成19年になっても減少傾向が続いています。 生活習慣病を防ぐ上でも重要な役割を持つ野菜は、多くの人が「もっとたくさん摂りたい」と思っているはずなのに、なぜ摂取量が減る傾向は止まらないのか?それは野菜をおいしくたくさん食べられるメニューが少ないからではないでしょうか。 私はこうした発想から野菜をもっとおいしく、たくさん食べられるレシピを開発してみたいと思いました。野菜ピューレ「ネピュレ」を利用した今までにないグラタン、お菓子の開発をしました。
食品・メニュー原価を探る
外食産業ではマクドナルドが100円商品の導入などが功を奏し、好調な業績を示しているなか、大手スーパーなどでもNB(ナショナルブランド)よりも多種類の安いPB(プライベートブランド)が大量に陳列されています。このように同じ商品、メニューを他社・他店よりも安く売っているケースを見る度にどうしてこんなに安く売ることができるのだろうか?利益は出ているのだろうかと思います。このような疑問から私はお店の設けの仕組みについて研究をしています。
笑顔商品化計画 / 〜ファストフード店における接客マニュアルの改善〜
2009年、現代の日本におけるファストフードの存在は、「早い・安い・美味い」という従来の売りだけでは、はもはやどの店も当たり前で、消費者側の欲求・選択の幅も日々多様になってきています。ファストフードを含むフードサービス業はその名の通り、注文に応じて「フード」と「サービス」を売り物にしていると言えます。しかし現状は、接客サービスのほとんどはマニュアルに基づいて行なわれています。今後ファストフード業界には「サービス」「ホスピタリティー」が最も重要な課題であるという思いから接客マニュアルの改善を研究します。
学食革命 / 〜学食が変わります〜
「学食」それは学生ならば皆が通る道ではないでしょうか。今や学生食堂の枠を超え進化してきています。外食産業との提携、メニューの本格化・低価格化。学生に愛される為の努力をしています。一般への開放もしておりメディアにも紹介され、高級レストランの風貌も見せている。そこで近隣にある大学の学食に足を運び 最近の学食のトレンドを探り皆さんに紹介しようと思います。それと合わせて、学食業務に進出する外食業務の動向・問題点についても追及していこうと思います。今、学食が変わります。
Bye Bye バリア / 〜おいしく楽しく食べる介護食〜
私の姉は重度の身体障害者で、年を重ねるにつれて食事が普通食から刻み食に替わり、現在ではペース食しか食べられなくなっています。食べ物は舌だけでなく、目で、耳で、鼻で、皮膚で楽しむものといえますが、現在の介護食は、こうした条件を満たしているとはいえません。食べることが好きだった姉にとって、食べる楽しみが奪われたことは大きなショックだったと思います。私は、姉のこうした体験を通して、美味しそうに見え、食欲をそそる介護食の開発をテーマとしました。
女性にもっと日本酒をッッ!!
今、日本酒業界は消費者の日本酒離れに加えて、焼酎や発泡酒やワインなどの需要拡大により国内市場は縮小傾向が続いています。そんな中、日本酒メーカーが力を入れているのが、若い女性をターゲットとした国内シェアの拡大です。しかし、努力の結果も空しく結果はいまいち・・・日本酒の国内市場を担うであろう女性シェア拡大は難しいのでしょうか。どうしたら女性に日本酒を楽しんでもらえるだろうか・・・女性が親しみやすい環境はどんなものか・・・を女性ならではの視点に立って、新しい日本酒の飲み方を提案したいとお思います。
「食育に役立つ物語」の創作
「食育」=「子どもが対象」というイメージはありませんか?子どもを対象とした「食育」への取組みに力を入れる企業が増えています。しかし「食育」は大変幅広い内容を含む概念です。そこで、食育の基本や日常の生活に役立つような知識を提供するにあたって、大人にも子どもにも分かりやすい、「絵本」が有効だと考えました。現代では、「星の王子様」など、大人向けといわれる読み物や絵本もあります。これから、「食」について知識を深めてもらえるような読み物を創っていきます。
日本の食料自給率アップのための地産他消の提案
私は以前から、日本の食料自給率の低さに不安を感じていました。食料自給率を上げる対策の一つとして、『地産地消』という言葉をよく耳にしますが、『地産地消』が本当に食料自給率を上げるために有効な方法なのかということに疑問を持ちました。そこで、前回の発表では、『地産地消』に代わる『地産他消』を提案しました。『地産他消』を行なうには、産地や商品のブランド化や、セールスプロモーションなどさまざまな要素を組み合わせた商品作りを行う必要があります。『地産他消』を行なうために必要な要素を考えていきたいと思います。
戦時中の食生活 / 〜学んで、現代に活かす工夫〜
皆さんお解りの通り、日本は今、かつてないほどの大不況に遭遇しています。生活防衛のため人々の節約志向も高まってはいますが、ほとんどの人は1日3食という生活を、特に意識することなく続けることが出来ています。しかし、祖父から『戦争中と戦後間もない頃は、3食まともに食べられず、飢餓や栄養不良だった人々で溢れ返っていたんだよ』と聞きました。貧しさや飢えを体験していない私達の世代が、窮乏と飢餓を体験し、そこから立ち上がった戦時中の食生活のDNAを学ぶことは今後の食生活改善に大いに役立つと思います。そこで、前発表を土台として、戦時食からヒントを得た、美味しい節約料理を提案します☆
パスタ革命 / 〜私流パスタ料理を紹介します〜
パスタは今や、日本でも人気の料理です。しかしそれに至るまでには長い歴史があります。16世紀の中頃、イタリアからフランスに紹介されたフォークの爪が4本なのは、パスタを食べる際によく絡まって使いやすいからだといわれています。また、イタリアでは「パスタの法律」があるほど重視されている料理です。私は授業で、イタリア料理の歴史や文化を学び、パスタに魅力を感じました。そして普段、主食とされているパスタを「私流パスタ」として新たな形で開発し、楽しみ方を紹介します。
「東松山の名物」を発掘する
私が育った東松山市は女子栄養大にも近く、埼玉県の中心部に位置しています。11月月には『スリーデーマーチ』が開催されます。あまり知られていないかも知れないのですが、東松山市は『やきとりの街』でもあり、東武東上線東松山駅を中心に約100軒のやきとり屋が点在しています。「やきとり」というと鶏肉を焼いたものを思い浮かべるとおもいますが、東松山の焼き鳥は豚のカシラ肉をじっくり焼いたものです。そして辛味の効いた「味噌ダレ」をつけて食べます。このような東松山の魅力をたくさん紹介していきたいと思います。
野菜をもっとおいしく食べられる! / 〜ドレッシングの開発〜
我が国では、これだけ野菜摂取の必要性が叫ばれているのに年々、摂取量が減っているのが現状だ。そこで注目したいのが、近年需要が伸びている持ち帰りの惣菜・弁当などのいわゆる「中食」市場。店に置いてあるドレッシングの種類はあまり多くない。サラダの種類は結構バラエティがあっても、ドレッシングは、和風、フレンチ、シーザーなどありきたりのものしか置いていない店がほとんどである。そこで私は、野菜の摂取量を増やすための対策の一つとして、野菜をもっとおいしく食べることができるドレッシングの開発に取り組むことにした。
高齢者でも利用しやすいカフェのプロデュース
私はカフェのアルバイトをしていて、カロリーの高いメニューや内外装など若者を意識した店が多いと感じました。年々、高齢化率が高まっており、コンビニでも高齢者を意識し揚げ物を少なくした低カロリーの弁当や和菓子などの商品を増やしており、ファーストフードでも高齢者のお客の姿を見かけることが多くなっています。元気で時間的に余裕もある高齢者が外出した時に、気軽に利用できるカフェがあればいいのにと感じました。また、高齢者を意識したカロリー低めのメニューは、メタボリックシンドローム対策として若い世代から幅広く受け入れられると思います。高齢者だけを対象にするだけではなく、高齢者も気軽に利用でき、若い層にも支持されるカフェをプロデュースしていきたいと思 います。
好きです、この街 とごしぎんざ / 〜地元密着型フードビジネスの成功原理を探る〜
綺麗な内装をして、凝ったメニューを持つ新しい飲食店。初めはお客さんに溢れていても、1年もすればそんな様子も見られなくなるというのは珍しくありません。その一方で、数十年の歴史を持ち、いまだに客足の絶えることのない飲食店もあります。私が住んでいる東京・品川区の戸越銀座商店街もそのひとつで、昔ながらの店舗を今も多く抱えながら、平日でも1万人以上が来客するという盛況ぶりです。本当に長く続く飲食店とはどんな飲食店なのか?戸越銀座商店街の特に食料品店、フードサービス店に焦点を置き、その成功の原理を探ります。
高橋敦子ゼミ(調理学第一研究室)
男性料理教室 / 〜きっかけを作るお手伝い〜
自分で料理を作る機会がなく、その反面健康に興味がある年代の中高年男性。そこで、私たちは料理を作る楽しみや健康に興味を持つきっかけ作りを目的とし、坂戸市の中高年男性を対象に月1回男性料理教室を実施している。その中で、受講生が葉酸に興味があることを知り、葉酸の多いメニューを取り入れ、その栄養情報も伝達してきた。そして、11月には、様々な情報に触れるきっかけを作れると思い「葉酸をたくさん食べよう」をテーマに受講生自身でメニューを決めて調理をし、1年間の料理教室の中でどんな変化があったのかを検証していく。
料理が楽しくできるようなレシピを提案する / 〜技術・情報伝達〜
私は、中高年男性の方々に料理が出来るまでのレシピ・実際の調理・食事・後片付けなどの一連の流れを通じて料理作りの楽しさを伝えるために、坂戸市の公民館で月一回、料理教室を行っています。中高年男性の方々が実際に調理をすることによって、経験や技術・情報の向上目的として行っています。料理教室では旬の食材やその季節に合った献立を考え実習をします。また、受講者の方々が自分たちで料理が作れるようになり、その上、人に伝達できるような技術指導を行ない、健康で生き生きとした生活が送れるよう、栄養の話や食材の話、運動について解説し、料理教室を行なったことで生活習慣がどのように変わったのかをまとめていきます。
男性料理教室 / 〜ゆっくり食べて健康〜
中高年男性にとって生活習慣病を予防して長生きしたいでしょう。そのためには食生活習慣改善が必要です。特に特定保健法ではメタボリックシンドローム対策により、肥満防止です。私は、中高年男性料理教室で食生活改善が出来ればと思い、健康教育を実施する事としました。日常の食事から食べる楽しさ、作る楽しさを知ってもらうことを目的とした。池袋のボランテア団体の男性12名を対象に行っている。料理教室では、旬の食材を使い方、料理を楽しく作って会話を楽しみながらゆっくりと食事が出来るような献立を提案し、また、栄養面の話や料理作りのポイントなどテキストを使い説明を行ない、実習しながら一緒に細かい指導を行なっています。
子供たちへの食育情報の発信!! / 〜子供たちは壁新聞のどこを見る?〜
壁新聞という媒体を通じて、子供達に食情報の発信を目的とし、食材を食べると身体にとっての効果や、どんな食べ方があるかを紙面に表し、12か月分作成した。壁新聞は月に1つの食材を取り上げ、3品の料理を提案している。子供達はこの壁新聞を見て、その内容にどのくらい興味を示し、それをどう自分の生活に取り入れているか、興味をもっているかなど調査を行う。アンケート結果をもとに、子供達は壁新聞のどこに興味を持つか、子供達にどう意識変化や影響など与えたかを学ぶ。
埼玉の野菜を楽しく食べよう
私たちは「埼玉の野菜を楽しく食べよう」をテーマに近隣の小学生を対象に埼玉の旬の食材を伝え、その食材を使った献立料理を作り、子どもの料理教室を行っている。食材の旬と産地、食材の特徴を学ばせ実践することを目的に実習をしている。子どもたちが、料理教室に参加したことで家庭でどのような変化があったか、食を通じて家族のコミュニケーションが広がったか、野菜を身近に感じられたかなどを調査する。
高橋勝美ゼミ(情報科学研究室)
塩の魅力 / 〜地球と人間の絆〜
現在ある海水を塩に換算した場合の量を、第一回目の発表で示したが、今回はより具体的に世界の人口一人当たりバケツ何杯分なのかを算出した。また、前回発表した洋風の塩につづき、今回は和風の塩を作り、提示する。これらの製塩法の中で、塩釜製法、天日干製法は、家庭でも手軽にできるが、瞬間結晶は装置が必要となるものの、甘味が強く、サラサラした塩ができるので、これを家庭で作る装置を試作した。さらに、塩の結晶の美しさにみせられ、巨大な結晶を作ったので、展示する。これらを通して塩の奥深さを知ってほしい。
うどんスイーツ
うどんの性質やうどんをスイーツにすることの利点を挙げ、実際にうどんとスイーツを組み合わせて新たなスイーツを考案し、前回発表した。この時は、麺になったうどんを乾燥させて粉に挽き、その粉を使ってクッキー・パウンドケーキ・ロールケーキを作った。結果、粉末の仕上がりが重要なことがわかった。今回は、うどんの形状をそのまま生かした新たなスイーツや、和のスイーツとしてうどんの生地を使ったあげまんじゅうなどを展示・紹介する。このような従来のうどんに関する固定観念を崩すことにより若い世代に広く受け入れられるスイーツに発展させたい。
めざめよ!枝豆
枝豆といったらビールのおつまみとのイメージがあり、それ以外の枝豆に利用法は、「ずんだ」くらいしか思い当たらないのが普通である。こうした固定観念を打開するために、枝豆を加熱してから粉にした『枝豆きな粉』や、枝豆らしい緑色が残った『枝豆豆乳』などを考え第一回の発表で紹介した。今回はさらに発展させ、『ずんだのきんつば』や、『枝豆きな粉』を利用して作った枝豆の風味を味わえる『枝豆落雁』などを紹介していく。私の発表をきいて枝豆の応用範囲の広さと、おいしさ、そして深い魅力を知っていただければと思っている。
NEW 豆腐 DESIGN
豆腐を個体と液体とに分けて豆腐ドレッシングや豆腐の薫製など、これまでにない製品を前回作った。今回はこの発展型として、当研究室で開発した新しい豆腐の製法でコーヒー風味のデザート豆腐など、見た目や食感が楽しめるものを作ってみた。これは私の考える「豆腐を子供のおやつ」として食べる機会を増やせるのではないかと考えている。同時に豆腐をベースにした低カロリーで甘味が強いケーキなどを展示・提案する。メタボリックシンドロームに悩む現代人や痩せ思考の女性にとって福音となるのではないだろうか。
田中久子ゼミ(公衆栄養学研究室)
食育ツールの開発
現在、食育への関心が高まっているため、食育ツールは様々なものが販売されている。ツールにはそれぞれ特徴があるが、子どもにとって難しいのではないかと感じるものや気軽に使用できないツールが多いと感じた。そのため、もっと気軽に使用でき子どもたちが自ら興味を持てる食育ツールがあったらと思い、S食育ネットの「ソイカード」開発に参加した。「ソイカード」がより良いツールになるように、他のツールを調べるとともに、学童や幼稚園において「ソイカード」ゲームを行い、子どもたちの反応や先生方の意見を参考にしてカードの改良を提案したい。
楽しい食卓を / 〜共食観からみた食生活〜
近年、共働きや核家族化、生活時間の多様化など社会情勢の変化のため、子どもの孤食や食生活の乱れが顕在化しています。“子どもだけで”あるいは“ひとりで”食事を食べる子ども達の食卓に並ぶ料理は、質的、量的に貧しくて食事に満足していない子が多く、健康上の不調を訴える子どもが少なくないのです。家族で食事をすることは、会話が弾み、食事内容や家族関係が良好になることが明らかになっています。親子関係を良好にするために親や子供に料理を作る楽しさを伝え、簡単に実践できる楽しい食卓作りの提案をしていきます。
クルマ旅の楽しい寄り道 / 〜サービスエリアでの「地産地消」への取り組みについて〜
高速道路の値下げにより利用者が増加しつつあるサービスエリア(SA)。そんな各SAで実践されている、地域のカラーを意識した「地産地消」への取り組みに、私は大きな関心を抱いた。取り組みの一例として、「どら弁当」が挙げられる。これは、その地域を代表する特産物がふんだんに使用されながらも、500?1000円程度の手軽な価格の範囲で楽しませてくれるという、魅力あふれる弁当なのである。旅の思い出として誰もが気軽に味わえる、そんな「どら弁当」を事例として挙げることで、新たな地産地消の可能性について探っていきたい。
根岸由紀子ゼミ(栄養科学研究所)
乳酸菌のいろいろ
最近CMなどで「植物性乳酸菌」や「人由来の乳酸菌」という言葉をよく耳にします。また、乳酸菌の入った製品が数多く出回っているのを目にします。では乳酸菌とはそもそもなんなのかという疑問をもち、調べてみることにしました。調べていくうちに、なんだか乳酸菌って奥が深そうだと感じこのテーマにしました。中間発表会では、乳酸菌について調べるとともにヨーグルトを中心に市場を見て歩いた結果を発表しました。今回の発表では、ヨーグルト以外の乳酸菌製品を見て歩くとともに、世の中にたくさん出回っている乳酸菌製品を、手軽にとる方法を考え発表します。
日本みそ再発見 / 〜作ろう!マイみそ〜
日本の伝統調味料であるみそ。みそ汁以外に使い方が分からないなんて人も多いのではないでしょうか。まず昨年の12月にみそを作りました。麹と大豆の量を変えて3種類のみそを作りました。夏に天地返しも行い、今回の発表では皆さんに味見してもらえるかと思います。みそはシンプルな材料で作ることができます。自分の好みに合わせて「マイみそ」を作ってみてはいかがでしょうか。みそを使った料理は全国各地に数多くあります。私は今回、みそを使ったスイーツの提案をします。さらに、みそを凍結乾燥(フリーズドライ)し、料理に活用し、レシピ提案を行います。
新・味噌style / 〜味噌のたまりを活用した料理提案〜
「味噌のたまり」とは味噌を作る過程でできる醤油に似た調味料です。この調味料を使って新しい味噌のスタイルを提案し、皆さんに日々の食卓で活用してもらうことを目指しています。前回の発表では「味噌のたまり」とはどのようなものなのかを知っていただき、調理法別に料理案を考え、「味噌のたまり」の幅広い活用法を知ってもらうことを目的としましたが、今回の発表ではさらなる「味噌のたまり」の情報を伝え、自宅で手軽に作れる「味噌のたまり」を生かした調味料(たれ・ドレッシング等)を紹介し、それに合う料理も紹介していきます。
節に恋して / 〜堅いけどイイ味ダシてる奴なんです〜
節からダシをとっている家庭が少なくなっているなかで節の原型、原材料を知らないという人が多い事に驚きました。そこで、節の種類、節の工程を調べ節の素晴らしさについて発表したいと思います。また、『節=和食』という固定観念を打破し、和食以外にも洋食、スイーツなど様々な料理に節を使用してみました。一見、眉を顰める組み合わせが多々あるとは思いますが、斬新なアイディアをモットーに節レシピの試作を試みました。今回の発表では、斬新な節レシピを公表したいと思っております。
蜂蜜と暮らす
昨年の夏“蜂蜜蔵”を訪れたことがきっかけで、実習で取り組むことにしました。蜂蜜と言っても、ラベンダー、レモン、コーヒー等、たくさんの種類があります。 皆さんは蜂蜜をどのようなことに使いますか?蜂蜜は料理に使うだけではなく、石鹸やクリーム等の美容にも、更に優れた殺菌効果を利用して火傷や口内炎にも蜂蜜を使うことが出来るのです。料理以外にも様々な場面で利用することが出来るので紹介します。 実はパリでは養蜂がさかんで、オペラ座の屋上にも巣箱があるほどです。養蜂は個人で小さな趣味として行っている人が多いようなので情報をまとめてみました。
Eating Dandelion / 〜雑草じゃ無くて立派な食物〜
タンポポは春の花や雑草としては有名ですが食べられることを知ってる人は少ないかもしれません。しかし日本にたくさん生えているセイヨウタンポポは元々野菜として海外から入ってきたものです。さらにタンポポは葉は勿論花や根も食べられます。現在でもコーヒーなら飲んだことある人もいるでしょう。私はそんなタンポポで今回はタンポポコーヒーやタンポポの葉のサラダなど、本から調べたものからタンポポコーヒーなどタンポポで作った加工品を使った料理、タンポポの葉と他の食品との組み合わせから考えた料理など様々な料理を作ってきました。今回の発表ではその中から葉を使った料理を試食にだそうと考えてます。そしてそれを通してタンポポに食として興味をもって貰えればと思っています。
マイブレンド茶 / 〜おいしく・かわいく・こだわりの〜
自家製でおいしい飲料をつくることができないかと考えた時、茶樹の葉を自分なりにブレンドして作ることが出来る茶外茶の存在を知りました。今まで試行錯誤しながらレシピを考えてきました。お金をかけずに気軽に・楽しく、皆さんにも試してみてもらいたいと思います。レシピには季節によって合うブレンド、美容 に効くブレンド…その他にも多くの効用や写真を多く載せていますので実際に手にとってもらいたいと思います。私自身、多くの発見と多くの人に知らせたいという気持ちが大きくなりました。是非発表を見に来て下さい!
発酵コーヒー
コーヒー豆の精製とは、収穫した実から種子を取り出して、生豆として製品化することです。コーヒーは豆の品種や品質、焙煎度などにより味が変わりますが、コーヒー豆の精製方法に種類があることを知り、興味を持ちました。コーヒー豆の製品化で、「発酵」という工程を知り、また「発酵コーヒー」「動物コーヒー」というものを紹介されました。この発酵とは何か?発酵とは人間生活において有益なもの、あるいは腐敗豆ではないか?との疑問もありました。今後は動物の腸内の消化酵素の働きや腸内細菌による発酵が関わっているのではないか、探っていきます。
さつまいもの食べ方 / 〜さつまいもを主食・主菜にする〜
さつまいものイメージというと、まず思い浮かぶのは最近の品種に多い“甘い芋”ではないでしょうか?しかし、中には甘味が少なく、コロッケにするとポテトコロッケのような色・味になる品種もあります。それが「オキコガネ」という品種です。そこで、この品種の利用法について研究し、料理や商品を提案します。一方、さつまいもにはデンプンが豊富に含まれるので、主食になってもいいはずです。そこで、甘いさつまいもは果たして主食になるのか、また、甘い品種も甘味の少ない品種も主菜として食べることの提案。さらに、栄養価の高い葉茎の利用についても研究を進め、様々な料理を提案します。
スパイス★コンフェクショナリー
みなさんは「スパイス」と聞くと、どの様なイメージがあるでしょうか?多くの人は「エスニック料理で使われる刺激の強いもの」、と考えるのではないかと思います。市販されているスパイスの説明には、「お菓子やデザート向き」と書いてあるものもありますが、実際に使っている人は少ないと思います。そこで、スパ イスをお菓子(コンフェクショナリー)に利用することにしました。まず、身近で手に入りやすいスパイスの中から使えそうなスパイスの種類を探しました。そして、試作を進めながら、レシピをまとめています。
How to Eat Rice
最近米粉を原料としたパンやお菓子などが増えてきています。さらに、昨年あたりからの小麦の価格高騰から製品の価格上昇を見、小麦粉の代わりとしてもっと米を使えるようにならないかと考えました。アメリカのスーパーでは米は配置として野菜や果物、豆などと並んで売られています。現地のレストランでは米は料理の添え物として出されているところもあり、米は『主食にもなる野菜』というとらえ方がされているように感じられました。私はこの『主食にもなる野菜』という米のとらえ方から米の利用法をもっと広げようと考えています。今回の発表では米を利用した料理をいくつか紹介します。
ベーグる? / 〜凍結乾燥ベーグルのススメ〜
タイトルを見て「凍結乾燥ベーグルって何?」と疑問を持った人、少なくないと思います。一言で言えば、日持ちのするベーグル。今やヘルシーなパンとして、パン屋や専門店で頻繁に見かけるようになったベーグルですが、実は保存性にあまり優れていません。基本的に市販されているベーグルの期限は、だいたい4日前後と定められています。そこで、まず凍結乾燥という方法でその欠点をなくし、より普段の食事に取り入れやすくするため、様々なアレンジを加えて、一つの‘料理’という形で皆さんに提案していきます。具体的には乾燥していることを生かせる料理、例えば現時点ではオニオンスープやパンプティングなどを考えています。今回は、実際にベーグル専門店の店舗・工場に見学に行き、そこで見たことや聞いたこともまとめ、発表に取り込んでいきます。ベーグルの食べ方に改革をもたらす、楽しい食卓の提案を目指します。
なんでもサンド
私はパンが大好きなので、食事になるよう『パン食』をやってみようと思いました。パンを料理と一緒に食べることで、手軽に食べられるし、バランスのよい栄養が摂れます。前回の発表では土台になる生地を数種類紹介しました。今回は、それに合う具を発表します。そして様々なシチュエーションを想定し、生地を工夫したりして明るく楽しくなるような場を提供できたらいいなと思います。また、レシピを作成して展示したいと思います。
平野覚堂ゼミ(ビジュアル・コミュニケーション研究室)
ココチェン / ―食事でココロをチェンジ―
「ちょっぴり気分を変えたい」そう思ったとき、私達は物に頼ることが多い。わざわざ物で気分を変えなくても、私達の身近にある食べ物で気分を変えたらいいのではないか? 今、世の中に溢れている食べ物の多くはおいしさ重視である。そこで私は、おいしさよりも楽しさや面白さ、さらにはエンターテイメント要素を盛り込んだ料理を提案する。食べ物においしさ以外の要素をプラスすることにより、物同様に楽しめて気分を変えることができ笑顔になってもらえるだろう。「料理=おいしさ」の考え方を覆し、食をもっと楽しんでもらいたい。
How to eat? / ─おふくろの味編─
おふくろの味といったら、やっぱり肉じゃがだろうか。代表的な家庭料理はどの家の食卓にもならび、個性を発揮する。肉じゃがの肉は、牛肉なのか豚肉なのか。味噌汁の具は何なのか。それぞれの家庭ごとに具や味つけに特徴があり、それがおふくろの味の最大の魅力である。では、外国人は日本のおふくろの味をどのように作るのだろうか。肉じゃがには何の肉を使うのだろう。味噌汁の具は何か。そこで、5人の外国人と共に、その人の母国風に日本のおふくろの味をアレンジした料理を作った。できあがった料理からわかったことは、世界のおふくろの味文化の共通点だった。
BA-BA / −おばあちゃん、しってる?−
最近おばあちゃんと会話したのはいつだろう? 核家族化が進んだ今、私たち若者の多くはおばあちゃんと接する機会が減っているのではないだろうか。私はおばあちゃんのことをよく知らないことに気づいた。 そこで、知られざるおばあちゃんの世界を徹底調査!おばあちゃんが、日々何を考え、どんなことに興味を持っているのかなど、街中にいるおばあちゃんを突撃取材すると共に、おばあちゃんとの親交をより深める方法を提案する。 おばあちゃんとの交流の楽しさを知ってもらうことで、より多くの人がおばあちゃんに接するきっかけになればと考えている。
お台所FACTORY!
私達の食生活に「台所」の存在は欠かすことができない。特に「キッチングッズ」は料理をする上で、時間節約や利便性など大きく関わっている。最近では、より便利に料理ができるようにと、様々なキッチングッズが販売されている。しかし使う人によって用途は異なるはず。そこで、いくつかのユーザーを想定し、それぞれに対応した新しいキッチングッズを考案していく。台所に立つことが多い主婦を始め、子供の目線に立ったものや、一人暮らしの狭いキッチンを有効に使うためのグッズなど、ユーザーニーズに応え、さらに+αの機能加えたものを提案する。
レンジャーめがねを創る会 / ─チームワークのススメ─
最近、チームについて書かれた本が増えている気がするが、リーダーに視点を置いたものが多く感じる。しかし、本当にチームを高めようとするなら、チームのメンバー各々が力を出し合うことが必要だろう。そうならば、リーダーからの視点だけでなく、メンバーの皆の視点から考えるチームワークの参考書もあっていいのではないだろうか。ただし、普通の参考書では、チームワークに興味を持ちにくく、もともと興味のある人にしか読んでもらえそうにない。そこで、flashを使い、遊びに交えて、チームワークにつながる色々の考え方を提案する。
農食同源 / ―フリーペーパーで伝える農と食―
食料自給率の低下や耕作放棄地の増加など、現在日本には様々な農と食の問題がある。しかし、私たち消費者はこれらの問題、特に農に対して関心が低いのではないか。農や食の問題を普通に伝えると、興味を持てない人も多い。そこで、農と食を「わかりやすく」「楽しく」伝えたい。年齢や性別、職業などによって好みや興味は異なる。情報の受け取り方は人によって様々だ。そこで、対象者別に農と食のフリーペーパーをつくり、農や食に興味を持ってもらいたい。農と食の新しい伝え方を提案し、より多くの人に農について考えてほしいと思う。
自分ブランド / ─飲むときだってわたしらしく─
毎日私たちが使う部屋や持ち物に表れる「自分らしさ」。同じように毎日使うものなのに、なぜ食器には表れづらいのだろうか。そこで、私は10人の人にスポットを当て、それぞれの人の個性の表れた「自分ブランド」の食器をつくることにした。今回は、食器の中でも、コップやグラス、タンブラーなどの、飲み物を飲むための食器に絞る。10人の「自分ブランド」の食器には、どれだけの違いが表れるだろうか。こうしてひとりひとりが「自分ブランド」の食器を持つことで、自分らしさを確立し、個性的になってほしい。
おにぎりに乾杯!! / ―飲み物に合うおにぎりの提案―
おにぎりは、私達の生活の中で欠かせない食べ物のひとつだ。おにぎりを食べるとき、私たちはたいてい飲み物を飲む。そのとき選ぶ飲み物は何だろうか。大半はお茶か水だと思う。それは私たちが、無意識におにぎりには、他の飲み物が合わないと思っているからではないだろうか。しかし、果たしてそうだろうか。世の中には様々な飲み物があるように、食べ物もいろいろな種類がある。ひとつの飲み物に対して、必ず合うおにぎりはあるのではないだろうか。普段私たちが飲むような飲み物と合う、今までにないおにぎりを提案していこうと思う。
松田康子ゼミ(調理学第一研究室))
C6 Cafe / 〜カフェの宣伝について〜
松田ゼミは6人で今年の4月から香友会館の一階「C6カフェ」を運営しています。営業は前期と後期の週2回の活動に加えて、若葉祭と夏休みのオープンキャンパスへの参加も行いました。カフェオープン直後の前期では宣伝不足があり、思ったように集客をすることができませんでした。より多くのお客様に興味感心を持って頂けるように写真の大きさ、文字、配色に工夫をしたポスターや立て看板を作成しました。また、新たな方法としてカフェのレシピや営業日をお知らせするブログを使っての宣伝活動を行いました。
C6 Cafe / 空間に魔法を
くつろげる空間、入りたくなるカフェとはどのようなものでしょうか。私は4月からのC6 Cafeの営業で内装をやってきました。前期(4月から8月)での内装がシンプルだったので、後期(10月から12月)ではイベントを取り込んだ内装を考え、テーマに寄り添って内装をすることにしました。内装に力を入れることで、お客様はどのような反応をしてくれるのでしょうか。また、カフェの内装によってお客様はカフェで過 ごす時間を楽しんでいただけたでしょうか。カフェの写真、アンケートなどをもとに、前期と後期の内装を比較します。
C6 Cafe / 〜ランチメニュー開発〜
私達が学内で運営しているカフェは、学生自らメニューの決定、仕上げ、材料購入から接客まで行い、店内の内装も手掛けています。ランチメニューは学生、教職員の方が多いので、手早く提供できるメニューにしようと考えています。発表ではカフェの運営を通してランチメニューの開発で苦労した点・工夫した点を中心にお話したいと思います。また、お店で出せなかったメニューや今までのメニューのアレンジについても発表します。カフェで提供したランチメニューをまとめ、レシピ集を作りますので、是非見に来てください。
C6 Cafe / シフォンケーキデモ2〜基本編〜
C6カフェのメイン商品はシフォンケーキです。ベーキングパウダーなどの添加物を使わずに、メレンゲの力だけで膨らませています。そのためメレンゲが命!!私たちが作るシフォンケーキのメレンゲは他とは違い独特な製法のため、習得するのに約半年かかりました。そんな大変なメレンゲ作りのデモンストレーションを中間発表でもお見せしましたが、伝わりにくかった点もあったようです。なので、どうすれば伝わるのかを検討し、発表したいと思います。また、失敗例も含め映像と実演でお見せします。
C6 Cafe / シフォンケーキデモ2〜応用編〜
基本をマスターしたら、次はアレンジ。シフォンケーキは副材料を加えたり、材料の一部を変えたりすることで、いろいろなアレンジができます。しかし、副材料を入れるタイミングは物によって様々。そのタイミングを間違えるとすべてが台無しになってしまうこともあります。とくに注意すべきは「油分」と「水分」。ア レンジする上でのポイントを、失敗例を参考に、映像と実演で解説します。また、私たちが作ったアレンジシフォン(油分を含んだココア、水分の多いバナナ、固形物を加えたドライフルーツなどなど)もご紹介します。
C6 Cafe / 〜オーブンの機種によってシフォンケーキの仕上がりに影響はあるのか?!〜
1年間シフォンケーキを作ってきました。そのなかで、電気オーブンやガスオーブン、容量の大きいオーブンなど、今まで様々なオーブンでシフォンケーキを焼いてきました。そこで、オーブンの種類によって焼き温度と時間を変えなければいけないことに気づき、興味を持ちました。オーブンの違いによって、シフォンケーキにとっての最適な焼き温度と時間を、実験を通して見出して発表します。また、庫内容量の大きいオーブンは、置く位置によっても焼きあがりに変化があるのかも見て、報告します。
宮内正ゼミ(文化学研究室)
中高年向けのカフェ / 〜アクティブシニアが求めているもの〜
ふだんみなさんが利用するカフェで、中高年の人を見かけたことはありますか?よく見ると大半の利用者は高校生からわたしたちのような20代、30代の人が多いことに気付きます。若者がよく利用するカフェを、なぜ中高年の人はあまり利用しないのだろうか。それには何か理由があるのではないか。そこで、中高年の人たちが利用しやすいカフェとはどのようなものなのか、について研究しようと 思いました。私たち若者と中高年の人のカフェに対して求めているものの違いを探り、その上で中高年の人が利用しやすいカフェとはどういうものか、を探っていきます。
和カフェ / 〜くつろぎの空間〜
近年、六本木や表参道や汐留を歩くと、和風のカフェが目立ちます。日本独自の「和」とヨーロッパに起源をもつ「カフェ」を組み合わせた和風カフェ、つまり「和カフェ」。店内には、和風ならではの「なごみ」や「くつろぎ」の雰囲気があり、柔らかな空間が広がっています。いったい人はどんなときにこうしたカフェを利用するのでしょうか。また誰と立ち寄るのでしょうか。その魅力や利用の実態について調査しました。じっさいには、いくつかのカフェとそれらの周辺地域を訪ね、観察を中心にしたフィールドワークを実施しました。
アパレルブランドもカフェの時代へ / 〜アパレルブランドのカフェがもたらすもの〜
近年カフェの形は多様化しています。これまで食の分野とは無縁であった業種がカフェを出すことも少なくありません。アパレルブランドが展開するカフェもそのひとつです。アパレルブランドがもっている、「流行(ファッション)」という時代の新しい空気と「ブランドイメージ」の個性的な魅力は、メニューだけでなく食空間づくりにも見事に反映されているようです。では、こうしたアパレルブランドカフェは、他のカフェと比べて、どのような違いがあるのでしょうか。若者の外食行動に与える影響に注目しながら、探っていきたいと思います。
カフェにおけるテラス席 / 〜どうとらえ、どう使うのか〜
現代人にとってなくてはならない当たり前の存在であるカフェ。誰もがそこに、他の飲食店とはどこか異なる、おしゃれで落ち着いた、くつろぎのスペースがあると感じているでしょう。では、そのくつろぎのスペースから街路に開け放たれているテラス席はどうでしょうか。いわば内部と外部が融合する空間であるテラス席。そこには、単なるくつろぎのスペースという捉え方では納まりきらない、何か固有の特性をもった空間があるのではないでしょうか。利用者の行動や心理を観察することによって、その空間の特徴を明らかにしていきます。
宮城重二ゼミ(保健管理学研究室)
食料自給率と食料のムダ
日本の食料自給率は1965年には73%でしたが、ここ数年は約40%と低迷し、2006年度には39%になり、2008年に再び41%になりました。主な先進国と比べると、日本の食料自給率は最低の水準となっています。しかし、輸入が増える一方で、飲食店や家庭における食品廃棄が問題となっています。国民一人一日当たりに供給される食料は2552kcal、そのうち実際に摂取される食料は1891kcal。この差約660kcal、供給量の25%以上を廃棄していることになります。日本の消費者のみなさんに、もっと自給率について考えてほしい。自給率を考えるきっかけを作り、食料廃棄を減らす方法を紹介します。
冷え
“冷え性”と聞くと、まだ若いから大丈夫!健康だから関係ない!と思ってはいませんか?しかし、今日では年齢や性別に関わらず健康問題となってきている。冷えは冬だけでなく、家やオフィス、乗り物に冷房が普及した現代は、夏の冷えも深刻化している。冷えの症状はや対策は、書籍や新聞、健康番組などより詳しく、そして年々情報量が増加している。大量の情報の中で、私たちが冷えの対策としてまず何をしていくのがいいのか一緒に考えてみませんか?
青森県から見える私たちの健康
あなたの思い浮かべる「青森」は何だろうか?青森はリンゴ農業や漁業が盛んな、全国でもトップクラスの自然大国である。しかしその背景には、平均寿命が男女共に全国ワースト1という暗い影も存在するということを皆さんはご存知だろうか?私は、その原因を大きく4つにまとめて文献調査を行ってきた。その原因を解決することが、一人ひとりのライフスタイルをよりよくする糸口になると考え、後期は実際に青森の方のライフスタイルを、フィールドワークを通した生の姿として調査してきた。そこから見えてきた生活における健康を、「私」の生活に下ろして見つめていきたい。
武藤志真子・藤倉純子ゼミ(健康情報科学研究室)
米粉の現状と展望
現在日本では、米の消費量が年々減っている。そこで、注目が集まっているのが米粉である。皆さんに米粉を身近に感じてもらいたいと考え、米粉の種類、産地、製法、現状、実際に販売されている米粉を使った食品の調査、レシピの調査を行い、誰でも家庭で簡単に作れるオリジナル米粉レシピ開発に挑戦した。その結果「米粉FOODコンテスト2009(http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-350/untitled_0001.html)」で審査員特別賞を受賞することができた。米粉の知識や現状と展望をホームページで発信し、米粉キットの開発や誰でも簡単に作れる米粉レシピを公開し、米粉について理解を深めてもらいたい。
お茶は自然の健康水
お茶は、人が手を加えなくても体に良い成分が多い。つまり「お茶は自然の健康水」なのだ。健康機能があるとして注目されているお茶だが、何の成分によってどのような効果があるか正確に知っている人はどのくらいいるのだろうか?飲み物を自分で買い始める高校生に、お茶の健康機能に関するリーフレットを作成し、配布前後でアンケート・クイズを実施して正解率・正しい知識の向上を目指した。また、日本全国それぞれのお茶やお茶を利用した名産品を集めた「お茶商品の日本地図」を作成している。お茶に関する情報やアンケートなどの結果に関するHPを作成し、情報提供を行う。
食料廃棄について / 〜生産者と消費者を結ぶコミュニケーションツール作成〜
私たちは、食べられる食料を大量に廃棄しています。食品リサイクルなどで活用されているものもありますが、同時に食品ロスを減らすことが大事ではないかと思います。実習では実際に生産者の方にお話を会い、食料廃棄のことや消費者の行動、生産物などについて伺いました。廃棄の現状、廃棄となった食品がどのように利用や処理されているかの他に、農家の方々に伺ったお話から、彼らが消費者に知ってほしいことを中心に情報を届けることで、消費者側が食に関心を持ち、信頼関係を築けるようなホームページを作成して情報を発信したいと思います。
山内喜昭ゼミ(情報教育研究室)
食文化学生帳
“食文化の学生の役に立ちたい!”そんな思いからこのテーマに取り組み始めました。私自身が食文化の学生として今まで過ごしてきた中で不便だと思ったことや、先輩からアドバイスが貰いたかったことなど、各学年に合わせて学生の立場からアドバイスなどを行います。その手段としてメールマガジンの配信やホームページの運営、ゼミの相談会などを行ってきました。メールマガジンでは履修科目選択の手順・基礎調理学実習についてのアドバイス、その他の連絡事項を配信しました。ホームページでは履修登録の手順について、メルマガでは載せきれなかった物を掲載しています。<http:www.eiyo.ac.jp/djoho/benri/sbkgakuseicho/index.html>
|