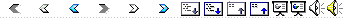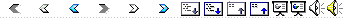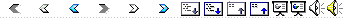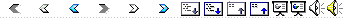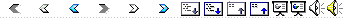|
|
|
|
|
江戸時代の行事の中から五節供をとりあげ、人々がどのように祝ったのか、節日に食された飲食物と生活とのかかわりについて調べる。 |
|
|
|
|
文献調査及び博物館等での調査:江戸時代の生活や行事を知るのに、文献や資料を収集するため博物館で調査した。 |
|
五節供を錦絵で表現してみたいと考え、絵画の部門の常設展はもちろんのこと、特別展にも注目することにした。 |
|
|
|
|
|
|
国立歴史民俗博物館 |
|
東京国立博物館 資料館 |
|
東京都江戸東京博物館 |
|
深川江戸資料館 |
|
東京都水道歴史館 |
|
品川歴史館 |
|
文京ふるさと歴史館 |
|
神奈川県立歴史博物館 |
|
国立国会図書館 |
|
太田記念美術館 |
|
|
|
|
|
根津美術館 |
|
栗田美術館 |
|
MOA美術館 |
|
虎屋ギャラリー |
|
ニューオータニ美術館 |
|
仙台市博物館 |
|
瑞鳳殿 資料館 |
|
青葉城資料展示館 |
|
瑞巌寺宝物館 |
|
みちのく伊達政宗歴史館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五節供とは人日(正月七日)、上巳(三月三日)、端午(五月五日)、七夕(七月七日)、重陽(九月九日)の総称である。 |
|
江戸時代、徳川幕府により定められた。 |
|
五節供はちょうど、季節の変わり目であり、生活の節目にあたる。 |
|
|
|
|
|
|
|
月日 節供 別名 |
|
正月7日 人日(じんじつ) 七草の節供 |
|
3月3日 上巳(じょうし) 桃の節供 |
|
5月5日 端午(たんご) 菖蒲の節供 |
|
7月7日 七夕(しちせき) 七夕の節供 |
|
9月9日 重陽(ちょうよう) 菊の節供 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正月七日を人日というのは、中国の古俗による。元旦から七日までを、一日鶏、二日狗、三日羊、四日猪、五日牛、六日馬、七日人とそれぞれの日に当て、七日が人の日に当たるので、人日と称した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七草(全種):粥、浸し物 |
|
せり: 汁、和え物、芹焼き、なます、煎り鳥に |
|
いれる。 |
|
なずな: 汁、和え物 |
|
ごぎょう(ははこぐさ): 草もち |
|
はこべら(はこべ): 汁、和え物 |
|
ほとけのざ(たびらこ): 和え物、浸し物 |
|
すずな(かぶらな): 汁 |
|
すずしろ(だいこんな): 汁、なます、煮物、干して、 |
|
そのほかいろいろに使う。 |
|
『日本料理秘伝集成』 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上巳とは最初の巳という意味である。この日中国では、漢代に踏青といって、川辺で草を踏み、川の水で禊を行ない、酒を飲んで穢れを払う行事を行なった。この上巳の節供はその名のとおり、三月の上巳の日に行なわれていたが、魏の時代に三月三日に移され、固定されたという。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魚にも青物にも紅藍の色を使い、美しくする。 |
|
寄せ物やかまぼこに模様をつける。 |
|
左右対称にならないように詰める。 |
|
色の取り合わせが重要である。似た色がひとところに集まらないようにする。 |
|
|
|
『料理早指南二編』 |
|
|
|
|
端午の端は月の初めの意味で、午とは午(うま)の日をいう。端午が五月五日になったのは、漢代以降で重日思想によるといわれている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粽 |
|
粳米の粉を湯でこね、まこもか笹の葉で巻き、 |
|
ゆであげる。 |
|
柏餅 |
|
粳米の粉を絹篩にかけて湯でこね、小豆をよく |
|
煮て塩味を付け、それをつぶして中へ入れ、小 |
|
さな玉子形にして、柏の葉で包んで蒸す。 |
|
|
|
『古今名物御前菓子秘伝抄』 『古今新製名菓秘録』 |
|
|
|
|
粽の食べ方 |
|
葉先の括ってある所のにごを抜き、捻ってあるのをほ |
|
どき、あとの四筋は本の方に押し下げるようにして葉 |
|
先からむく。塩でもきな粉でもあれば、一度だけ付けて |
|
食べる。箸がない時は、葉の一枚で持って食べる。置 |
|
く時は右手で持ち、左に房がくるようにして置く。 |
|
粽を頂戴する仕方 |
|
台に沢山のせてある時は、手を畳につけず中腰になっ |
|
て取る。少しだけならば畳につけて戴く。いずにしても |
|
取ってから左に戻して頂戴する。 |
|
|
|
『飲膳作法』 |
|
|
|
|
七夕は「しちせき」と読み、七月七日の宵という意味である。これを「たなばた」ともいう。「たな」は棚、「はた」は機である。七月七日の夜、乙女(棚機津女)が水辺の機屋にこもり、棚の構えのある機で布を織り、神の迎え送りをして、神に人々の穢れを持ち去ってもらう行事があった。日本語の「棚機」に漢語の「七夕」を当てて、たなばたといわれている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
そうめんは小麦粉に水と塩を加えてこね、植物油をぬってほそく引きのばして干した、ごく細いめんである。 |
|
そうめんは後段といって、もてなしをするとき、食後に出す食べ物である。 |
|
『料理伊呂波包丁』 |
|
そうめんの汁 |
|
煮貫:生垂れにカツオブシを入れ、煎じて漉した |
|
もの |
|
垂れ味噌:みそを水で溶き、煮て木綿袋で漉し |
|
垂らした汁 |
|
『料理物語』 |
|
|
|
|
|
|
|
|
「重陽」とは、「重」は重なる意味で、「陽」は太陽の意味であるが、数でいうと奇数をあらわす。月と日がともに陽の数の最大である九が重なるところから名が付けられ、重九ともいい、めでたいとされた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
菊酒の作り方 |
|
糯白米 一升 よく蒸す。 |
|
麹 二升 |
|
上酒 一升 (1.8ℓ) |
|
干し菊花 四十匁 (150g) |
|
菊花へ水一升を加え五合(900cc)に煮つめ、酒水によ |
|
くひたす。日数は七十日ばかりおく。もし濃いようなら酒 |
|
を少しさし加える。 |
|
『漬物秘伝集』 |
|
|
|
菊酒の効能 |
|
目をはっきりと見えるようにし、何日もおさまらない頭痛 |
|
を治す。 |
|
『飲膳摘要』 |
|
|
|
|
|
|
栗の保存法秘伝 |
|
栗の水をふきとる。 |
|
茶の湯釜の中に並べて入れる。 |
|
蓋をしっかりして、さらに箱に入れる。 |
|
上記のようにすると来年まで持つ。 |
|
栗の先端のとがっているところを火でこがし |
|
ておくと、芽も出ずに保存できる。 |
|
|
|
『和漢精進料理抄』 |
|
|
|
|
|
|
栗飯:栗は上皮と渋皮をむく。二つかさいの目に切 |
|
り、飯がなかば煮えた時にその上に置き炊き |
|
上げる。 |
|
『料理伊呂波包丁』 |
|
鮎の子付膾:鮎を三枚におろし、細切りにし、炒っ |
|
た鮎の卵とせん切りの栗、生姜をま |
|
ぶしつける。 |
|
『伝演味玄集』 |
|
花栗:栗を花、鳥、木の葉などの形に切った細工物 |
|
で、料理の飾りに使う。 |
|
『精進献立集』 |
|
|
|
|
栗白和: 白味噌と豆腐をすり合わせ、油で炒めた |
|
栗と木耳を一緒に入れて和える。 |
|
栗あんぺい:生の栗と山芋をすり合わせる。水とき |
|
した葛粉を加え、茶碗に入れて蒸す。 |
|
葛あんをかけ、すり生姜をのせて出 |
|
す。 |
|
栗田楽:焼いた栗を串に三、四個刺し、唐辛子味 |
|
噌、ふき味噌、山椒味噌などを塗って田 |
|
楽にする。 |
|
『素人包丁』 |
|
|
|
|
|
|
指身:ゆでた栗、牛蒡、生姜をせん切りよりさらに |
|
細かいものにして、もり合わせる。 |
|
羅漢菜: 栗、慈姑、人参、牛蒡をだし汁で煮る。 |
|
水でとい た葛粉を加えとじ、器に盛る。 |
|
砂糖をふりかけて出す。 |
|
|
|
『和漢精進料理抄』 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国から伝わる。 |
|
日本古来の信仰や風習と結びつき、年中行事として定着していった。 |
|
江戸時代に五つの式日として定められ、五節供となった。 |
|
呼び名も月日も中国から学んだものを取り入れている。 |
|
邪気を祓い、無病や長寿を祈った。 |
|
それぞれの節日に飾り物を飾って、供物を供えて、行事食を食べて祝った。 |
|
|
|
|
私はこの実習で、博物館、資料館、美術館を訪ねたり、“江戸”と名のつく展示会が目に入ると、都合がつけばすぐ出かけて行った。いつも、“江戸”
“江戸”と頭がいっぱいだった。 |
|
江戸時代の人々は、五節供をたのしみに待ち、大切にしていたように思える。季節の節目にあたる節日に供物を供え、邪気を祓って健康や長寿を祈願するだけでなく、農耕にかかわる時季でもあるから、神に豊作を祈り、また、収獲物を感謝することが込められていたこともよみとれる。 |
|
封建社会を形づくる階級制度の厳しい時代の中で、庶民は自分達の出来る限りのことをやって節日を楽しんでいるように見えた。錦絵や挿絵からも分かるように、子供達も節供の支度の手伝いをしたり、節日には遊んだりして、楽しそうな様子である。そして、供物をみんなで食べて節供を祝った。 |
|
私はこの実習を通して、江戸時代の庶民のたくましさと知恵を学ぶことができた。江戸は過去のことだから古くさいといって、すててしまうのではなく、現代、未来を考えるのにおおいに役立てたいと思う。 |
|
|
|
|
菊池貴一郎著 鈴木棠三編 『絵本江戸風俗往来』 平凡社 1992年 |
|
喜多川守貞著 朝倉治彦・柏川修一編 『守貞謾稿』 第4巻 東京堂出版 1992年 |
|
儀礼文化研究所編 『諸国図会 年中行事大成』 桜楓社 1978年 |
|
斎藤月岑著 朝倉治彦校注 『東都歳時記』 第1巻 第2巻 平凡社 1989年 1988年 |
|
宗懍著 守屋美都雄訳注 『荊楚歳時記』 平凡社 1993年 |
|
高橋幹夫
『江戸あじわい図譜』 青蛙房 1995年 |
|
中村喬
『中国の年中行事』 平凡社 1993年 |
|
中村喬
『続中国の年中行事』 平凡社 1994年 |
|
武士生活研究会編
『絵図でさぐる 武士の生活』 第1巻 第2巻
柏書房 1982年 |
|
三谷一馬 『江戸年中行事図聚』 中央公論社
1998年 |
|
吉井始子 『翻刻 江戸時代料理本集成』 全10巻 別巻 臨川書店 |
|
『原色
浮世絵大百科事典』 第5巻 第6巻 大修館書店 1980年 1982年 |
|
『日本料理秘伝集成』
全19巻 同朋舎出版 1985年 |
|
|
|
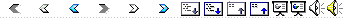
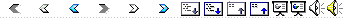
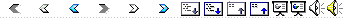
 ノート
ノート